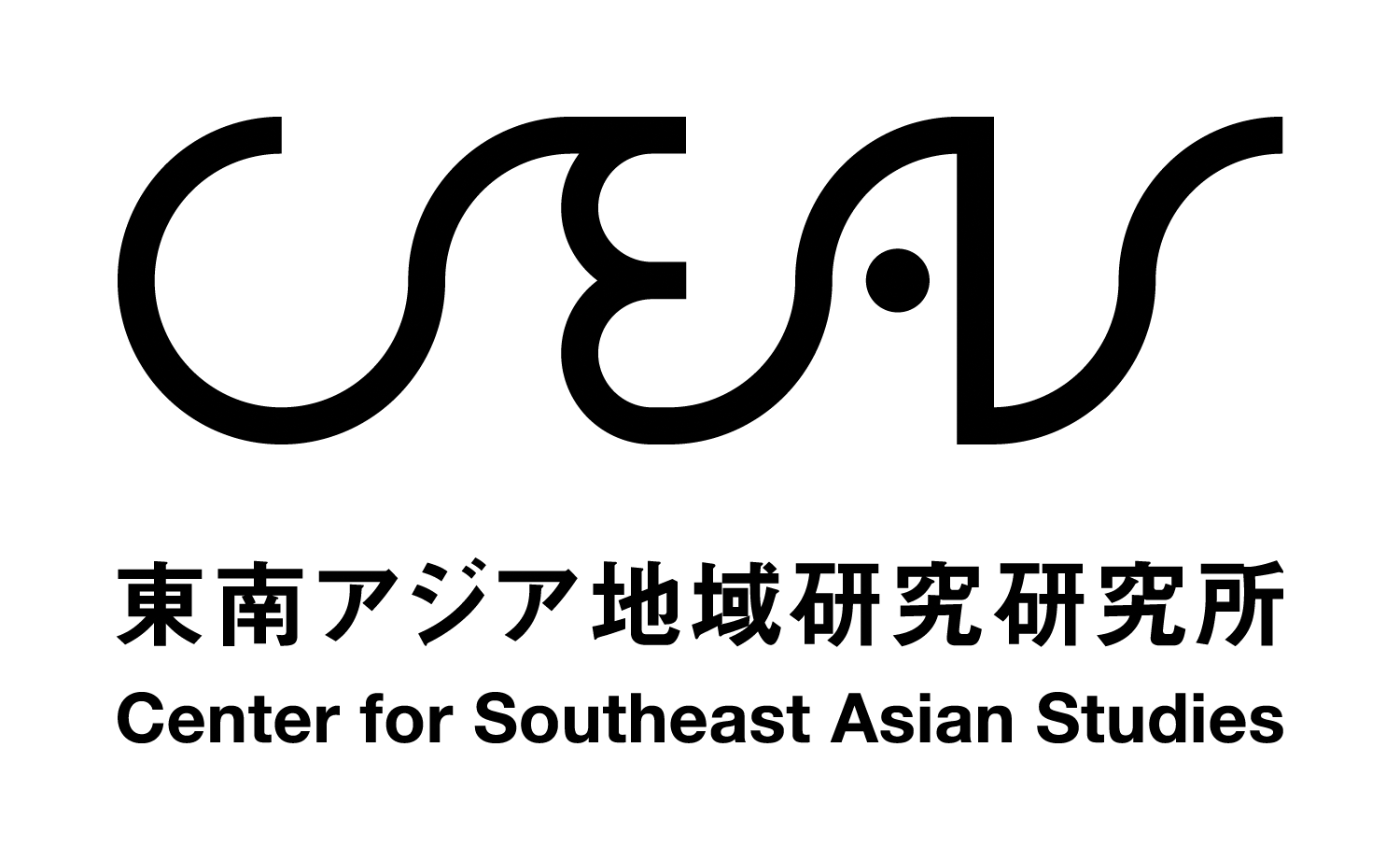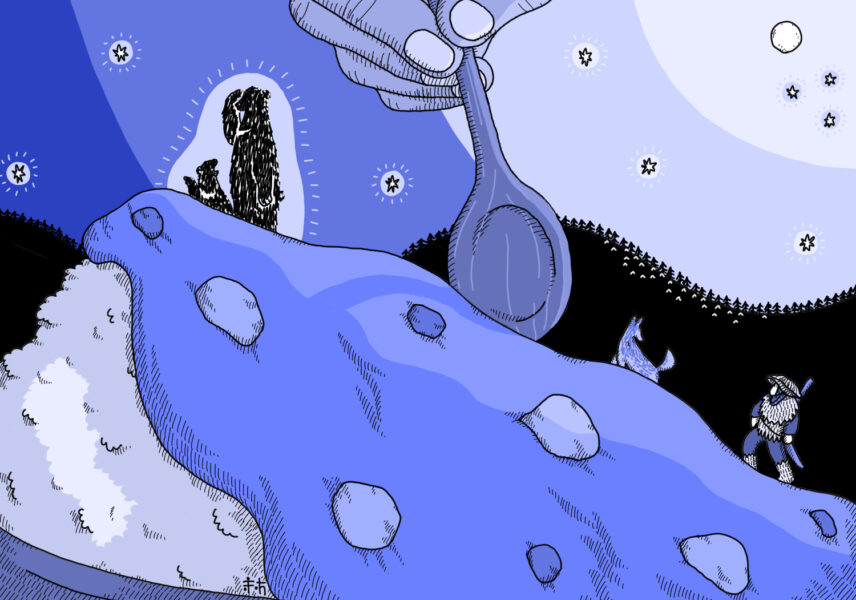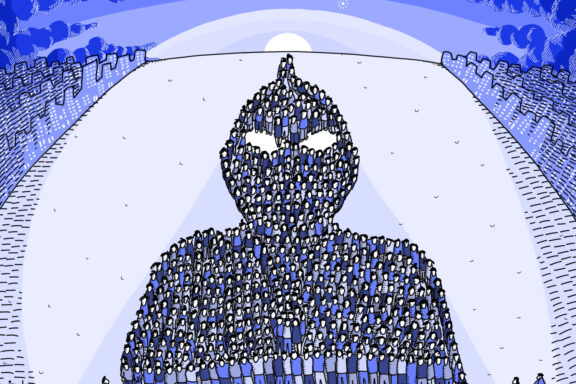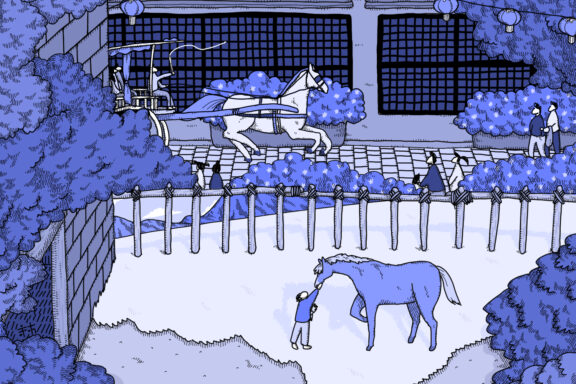ネイサン・バデノック(言語学)
日本で生活していると、身の回りのいろんなものに毎日話しかけられていると感じる。近所のコンビニに入る時、吉田山に登る時、市バス205号系統に乗った時、私にはオノマトペという「周囲の声」が常に聞こえている。日本語には、音と意味が特別なつながりをもつオノマトペ層があると思う。食品名やコスメ商品名にはオノマトペが非常に多い。髪がツヤツヤになると言われたら、その意味を「わかる」というより「感じる」と言った方がいいかもしれない。聞き手に何かを直接に感じさせるこのような言葉は、英語にはないが、世界のほとんどと言っていいほどの言語にはオノマトペが豊富にあるということは、あまり知られていない。
私がフィラデルフィアにあるビラノバ大学で担当する日本文学の授業では、宮沢賢治の短編『なめとこ山の熊』を英語訳で読む。主人公の小十郎が谷をぼちゃぼちゃ歩く場面。これをどういうふうに説明すればいいか。谷川の流れに「濡れる」音だけれど、大自然の中を苦労して歩いていることを見て納得する熊の気持ちも大事。宮沢はオノマトペの名人、あるいは変人、としてよく知られているが、杉田淳子の『宮沢賢治のオノマトペ集』(ちくま文庫、2014年)で読む例文と解説は深く、楽しい。一風変わったオノマトペの使い方が宮沢の作品の魅力となっていることがよくわかる。変わったオノマトペといえば、私の友人で京都の北の方に住むオノマトペ名人ないし変人がいる。彼女は時々オノマトペを作る。何それって聞くと、そんな感じがするの、と答える。ある日彼女は、自分の作ったカレーが「ドゥルドゥル」していると言った。ドゥという発音は、彼女の喋る関西弁にも標準語にもない音だけれど、ネイティブでない私でも彼女が言おうとしていることはその場でわかる気がした。カレーで普通によく使われるドロドロは、人間関係についても言えるけれど、ドゥルドゥルでもいけるかな。それは微妙、と彼女でも確信はない。
この友人のオリジナルなオノマトペを聞いた人は、彼女の想像が本当にわかるのか。音が大切だからと、それを勝手に変えてもいいのか。日本語話者は、トロトロとドロドロの違いが感じとしてわかるのと同じように、「ウ」と「オ」の違いに対する感覚があるはず。言葉の方言による違いは当然とされても、こういう個人差はどこまで認められるのか。オノマトペ辞典には載っていない、その場のノリで口をついて出たオノマトペはそれほど珍しくないかもしれない。日本語話者にとっては、あるオノマトペの意味は耳にした音のままに伝わるだろう。しかし、辞書は真面目なものであって、ある程度個人の言葉遣いを制御する働きもある。4500語に上る『日本語オノマトペ辞典』を作った小野正弘先生の言葉を借りるとオノマトペは「和み」であると。
実は、私もオノマトペ辞典を書いた経験がある。東インドで話されるムンダ語には、日本語のようにオノマトペが想像を絶するほど多い。言語学者の長田俊樹先生と母語話者のマドゥ・プルティさんが、数十年前から集めていたムンダ語のオノマトペ集を辞書にする共同研究に私を誘ってくれて、新しい言語世界への扉を開けてくれた。その成果として出たのが『ムンダ語擬音語擬態語辞典 A Dictionary of Mundari Expressives』だ。ムンダ人の日常生活で使う言葉の意味を探るのに、オノマトペの豊かにある日本語とそれが乏しい英語で説明と例文を書いていくのは、一つ一つが言語と文化の繋がりを感じさせる冒険だった。マドゥ・プルティさんがムンダ語で歌う歌は、オノマトペの響きが印象的。民話を語る時にはオノマトペに満ち溢れる。インドのカレーにまつわるオノマトペがあまりにも多くて、しかもその違いが面白くて一緒に論文を書いたこともある。カタカナで書けば「レデペデ」「ロドポド」「ラダパダ」のような音に近い。私の京都の友人と同じように、マドゥ・プルティさんもそのカレーの特徴を伝えるために音で「遊ぶ」。
ラオスの山奥で農業をしている親友がいる。彼はビット語という言葉の話者であって、またオノマトペ名人。彼の家に遊びに行くたびに、たくさんのオノマトペを教えてくれる。調子のいい日には10でも20でも会話の中で当たり前のようにどんどん出てくる。あえて普通の単語を使わずに、しばらくオノマトペを並べて話を盛り上げることもざら。ビット語を喋る人は、世界に2600人ぐらいしかいない。10年前から作っているビット語の辞典は今7000語を超えたが、全体の3割ぐらいがオノマトペ。ムンダ語もビット語もオノマトペが尽きない、とまで言える気もする。そして日本語でも、新しいオノマトペを耳にする毎日だ。
子供の頃から色々な言葉を習ってきた私は、「そんなにたくさんの言語を喋るというのはどんな感じ?」とよく聞かれる。ユーモアの感覚がそれぞれ違ってとても楽しいというのが私の好きな答え。もう少し大きくいうと、喋る言葉によって、日常生活で触れ合う身の回りが違って感じる。オノマトペを通して、その世界で声をかけてくれるものが違って聞こえる。それぞれの言語には音や文法の違いがあるが、私にとってはオノマトペが描く宇宙の音と意味と触れ合いの繋がりにあるコトバの面白さが何より大切。あなたのそのお皿にあるカレーは今、どんな話をしてくれている?
(イラスト:Atelier Epocha(アトリエ エポカ))
本記事は英語でもお読みいただけます。>>
“When Your Curry Speaks to You”
by Nathan Badenoch