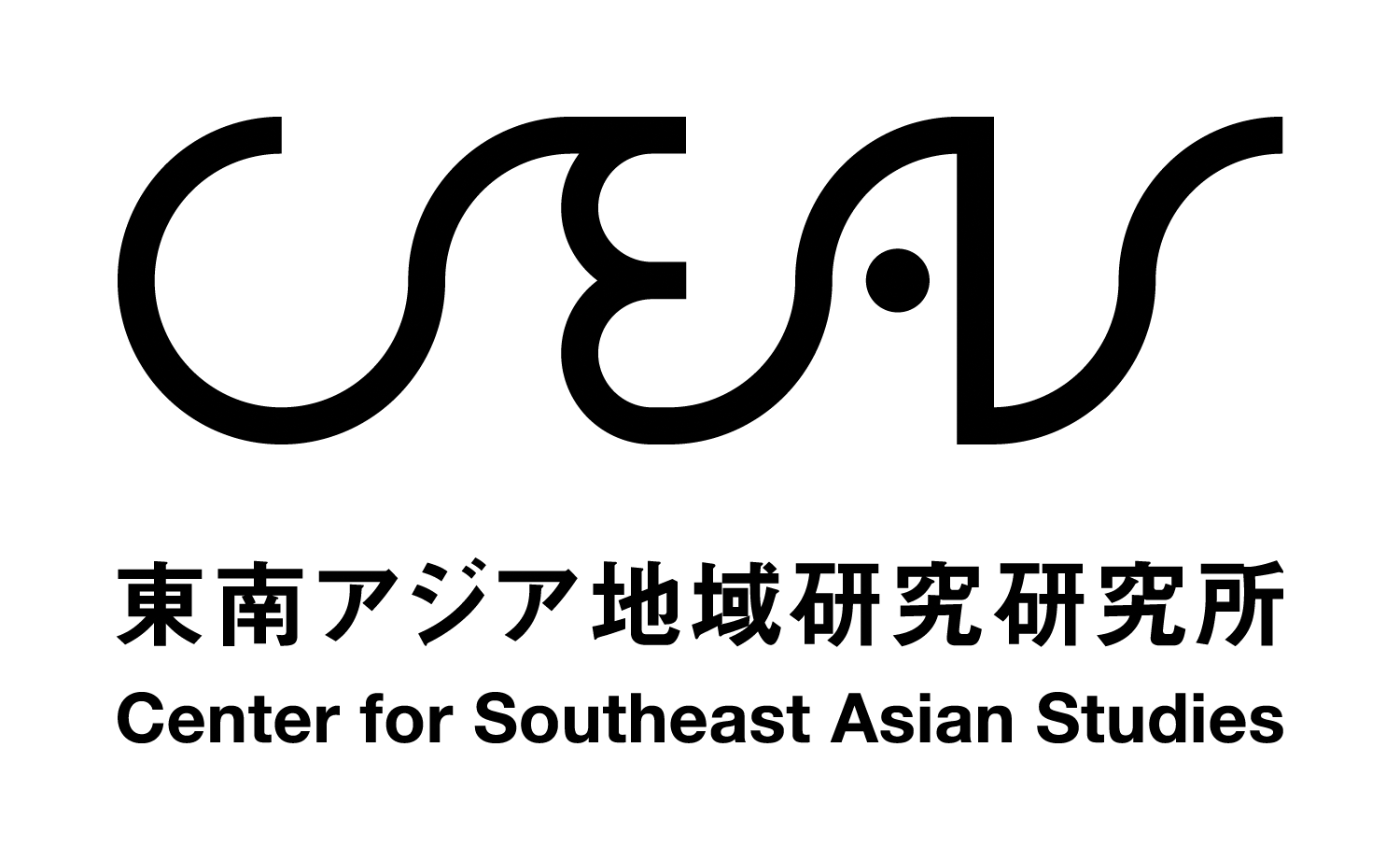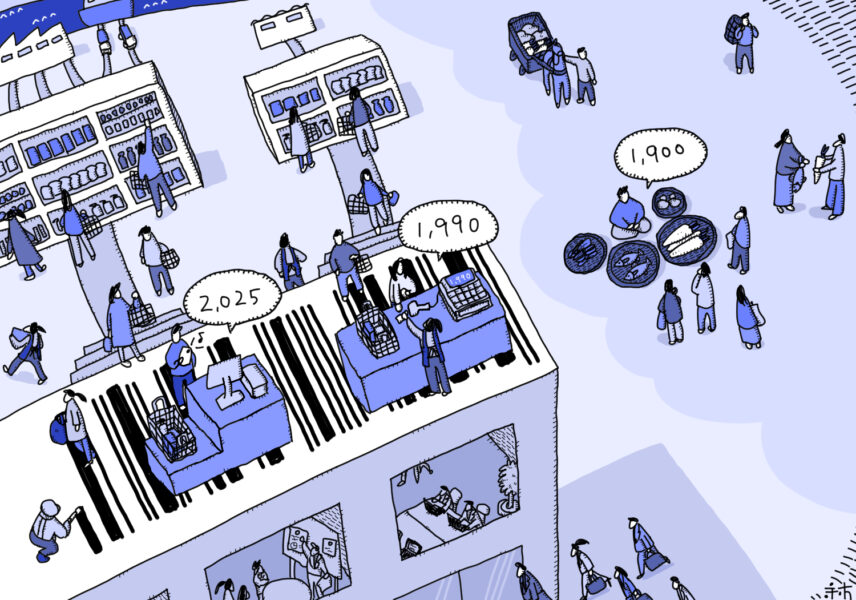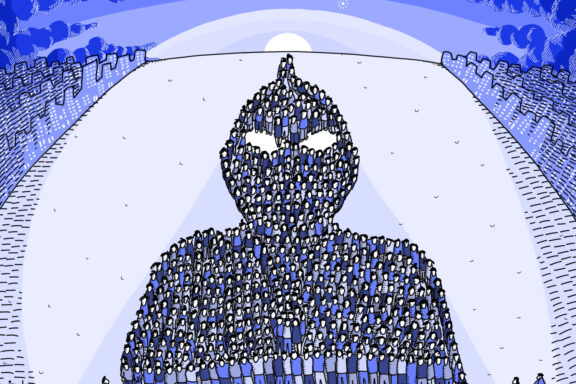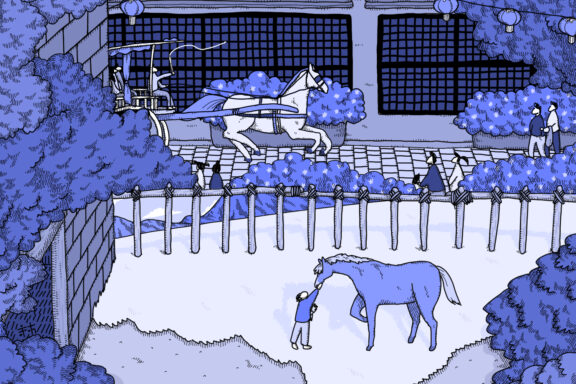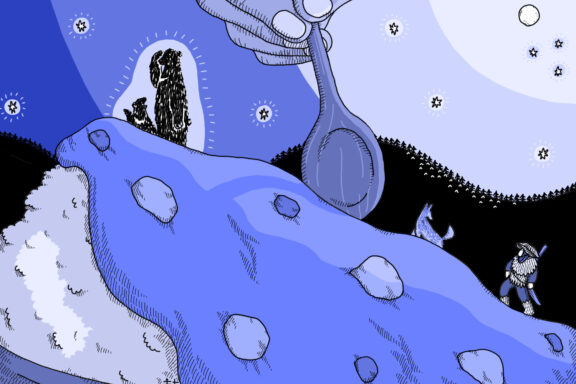町北 朋洋(労働経済学、産業発展論)
最近はセルフレジを設ける店が多くなり、商品を入れたカゴを手前に置き、レジの向こうのハンガーに買い物袋をかけ、商品のバーコードの部分をレジの黒い窓にかざします。ピッと鳴れば合格ですが、この商品のどこにバーコードがあるんだっけと悩み、もたもた。箱をくるくる回転させてそれを探す自分の姿とレジ係の熟練度を比べながら、バーコードへの興味が増しています。
バーコード登場は1970年代半ばのこと。異なった太さの線がいくつも縦に並んでいますが、その直下にはUPCと呼ばれる12桁の商品識別番号が、そして日本ではJANコードと呼ばれる13桁と8桁の番号が記されています。当初のアイデアは同心円状の縞模様でしたが、長方形の方が読み取りやすいことが分かり、今に至ります。ティム・ハーフォード著、遠藤真美訳『50(フィフティ)いまの経済をつくったモノ』(日本経済新聞出版)は、私たちの生活を変えてきた50個の発明の一つとして、この縞模様を特筆しています。太さの異なる線を組み合わせて情報を集約するというアイデアは驚くべきものですが、これのどこが現代経済を形作ったイノベーションというのでしょうか。
バーコードを商品に印字するコストを負担するのは製造業者ですが、スキャナーつきのレジ導入のコストを負担しているのは小売・卸売業者です。製造業者は小売・卸売業者がスキャナーを導入してくれない限り印字コストを負担したくない。小売・卸売業者にとっては、商品に印字する製造業者が少ないと、高価なスキャナーとシステムを買っても損をするだけ。経済学ではネットワーク効果という考え方を使って、こうした流通チャネル上の問題の分析に取り組んできました。1990年代初めまでの米国の製造業者を対象とした研究[1]によれば、販売先にあたる小売・卸売業者がシステムを導入しているほど、商品ラベルにバーコードを印字してきたことが分かりました。その研究によれば、製造業者はバーコード導入後に商標を増やし、収益も増加し、企業規模が拡大しました。
それではなぜ、小売・卸売業者の側でスキャナーの普及が始まったのでしょうか。得するのは誰かを考えることがヒントになりそうです。本書によれば、米国のウォルマートに代表される大型スーパーマーケットです。先発組は食品関係。バーコードとスキャナーの導入によって、食品の在庫管理が自動化され、多様な品揃えを維持するコストが一気に下げられ、店舗の総合化、巨大化が加速しました。また1970年代当時は予想できなかったことかもしれませんが、流通チャネルでのスキャナー普及は、外国製品の参入を容易にし、サプライチェーンの国際化を促しました。後発組のアパレル産業も巻き込み、競争が激しくなった結果、ウォルマートは中国のサプライヤーを見つけやすくなり、消費者は安価な製品を買いやすくなったはずです。
革新的な技術が世に出た時に、誰に何が起きるのか。本書は具体的な発明の技術的要素を詳しく取り上げつつも、なぜそれが私たちの生活を良いようにも、また悪いようにも変えてきたのかを掘り下げて説明します。発明は別の発明とつながり、モノとサービスの価格を変えます。価格の変化はプレイヤーの間の力関係やプレイヤーの構成を変え、予期せざる広範な影響をもたらします。その経験の繰り返しが、発明からみた人類史であることを本書は教えます。
注
[1] Emek Basker and Timothy Simcoe. Upstream, Downstream: Diffusion and Impacts of the Universal Product Code, Journal of Political Economy, 2021 129:4, 1252–1286. 本論文著者による要約はこちらのVoxEU Summaryおよびその日本語翻訳記事を参照のこと。
(イラスト:Atelier Epocha(アトリエ エポカ))
本記事は英語でもお読みいただけます。>>
“Barcode: Unintended Pervasive Consequences”
by Tomohiro Machikita