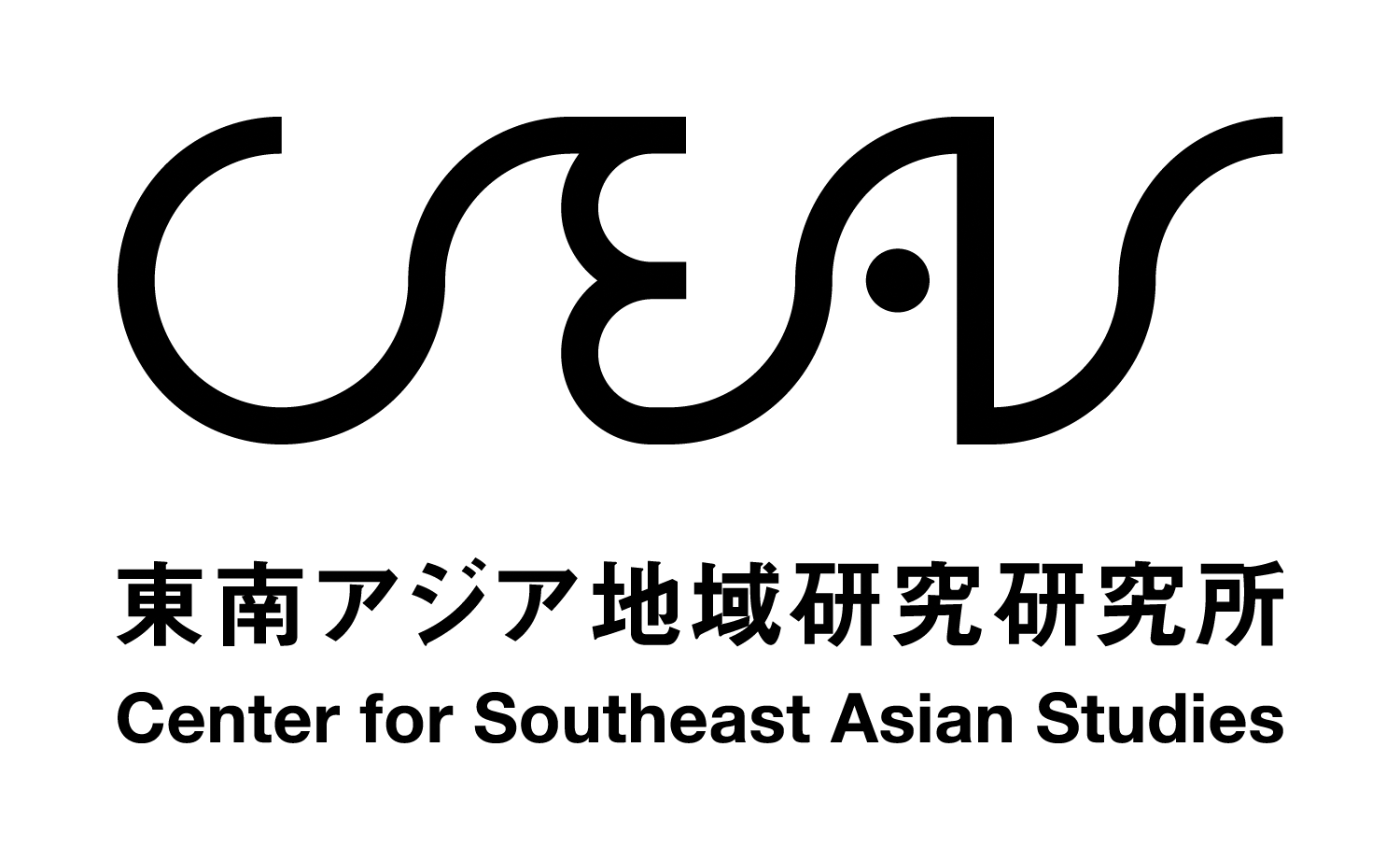柳澤 雅之(東南アジア生態史、ベトナム地域研究)
農村研究って何?
「私は、ベトナムの農村を研究しています。」
こういうと、1990年代は、「そうですか、なるほど」と納得されましたが、今では、「そうですか、なぜですか」と聞き返されます。こうしたことが起きるのは、研究される側とする側に大きな変化があったからです。
研究される側とはこの場合、ベトナムの農村です。農業が国の重要な産業であり、農村人口が国全体の過半数を占めていた90年代と、工業化が進み農村労働力が不足するようになった2010年代以降とでは、農村の様子は大きく異なります。かつて、ベトナムで農村を研究することは、国の主要な経済活動や社会構造の基盤を理解することに直結していました。ベトナムの文化を理解するにも農村は重要な役割を担っていました。
しかしその後、ベトナムは急速に経済発展を遂げました。経済の基盤は工業やサービス部門に移行しました。人口は増加し、人びとは都市に向かいました。農村では、若い世帯の多くが農業以外の職業に就き、農村で農業を担う労働力が不足するようになりました。農村や農業の社会経済的な重要性が相対的に低下するにつれて、農村研究の意義についても問い直されるようになりました。

上が1996/97年、下が2016/17年に撮影した、同じ村の中の同じ場所の比較。道路が舗装され、生垣がフェンスに置き換わった。

上が1996/97年、下が2016/17年に撮影した、同じ村の中の同じ農地の比較。広かった水路はコンクリートで整備され、幅も狭くなった。その分、農地が増えているのがわかる。また、農業用の電線が引かれるようになった。
また、国際社会における当時の時代背景も重要でした。1986年以降のベトナムは、市場経済システムを導入し、多くの国と関係を築き、国際社会の重要な一員としての役割を担うようになっていました。90年代は、新興国ベトナムを理解するという、大きな課題に対して一定の説得力があったと言えるかもしれません。そして、そのために農村研究は重要な柱だと認識されていました。
もう一方の、研究する側にも大きな変化がありました。第一に、ベトナム農村の変化に対応して、研究する側の課題が多様化したことがあげられます。その他に、ベトナム人によるベトナム研究の増加や、学術雑誌の多様化、学術研究における成果主義の増加など、さまざまな変化がありました。ここでは、課題の多様化について、もう少し掘り下げてみましょう。
研究課題の多様化
現在のベトナムを対象にした研究は、政治経済、社会文化、生態環境など、さまざまな分野に拡がっています。多様な研究関心を持った多くの人びとがベトナムでの研究に参画し、その結果、対象とする研究分野が拡がりました。関わりの多様性を反映し、きわめて個別具体的な課題から、研究分野を総合する必要のある大きな問いまで、幅広い研究が行われています。
90年代以降の30年間ほどの中で、個々の研究者の研究課題も当然変わってきました。たとえば筆者は1994年からベトナムで農村研究を開始しました。当初は、高い農業生産を実現する集約的農業とそれを実現する村の農村組織に関心を持って調査を行っていました。しかし、先述したような農村の変化の中で、農業そのものに変化が現れました。村人の経済基盤が農業から非農業部門に変化する中で、筆者の研究課題も、生計の多様化や村での暮らしの変化、狭小で分散した農地の整理、村の役割の変化等に移っていきました。農村研究であることに変化はなかったのですが、具体的な研究課題は時代と共に変化しました。
大きな問いと特定の課題
多様な研究課題の中には、分野を横断し総合的に考察する大きな研究課題と、専門分野(ディシプリン)の研究アプローチを適用した特定の研究課題の両方が含まれます。前者には、さらに根源的な研究関心が含まれています。たとえば、ベトナムにおけるガバナンスや、東アジアにおける信仰、自然との関わり、開発と社会といった課題です。それらを「大きな問い」と呼んでおきましょう。ひとりの研究者の中にも、大きな問いと、そこから派生した、時代ごとに特有の課題解決型の問いの両方があります。筆者にとっての、ベトナムで研究する際の大きな問いは、「農村社会とは何か」や「自然と人間の相互作用の蓄積としての自然環境とはどのようなものか」というものです。特に前者の関心を持って、ベトナム北部の稲作地帯である紅河デルタで村落調査を継続してきました。
紅河デルタでの長期定着村落調査
筆者らは、1994年から、紅河デルタで村落調査プロジェクトを実施してきました。この共同プロジェクトでは、参加者個々の研究関心に応じて村落の変容を明らかにするため、ひとつの集落の全世帯を対象とした、網羅的社会経済調査(comprehensive socioeconomic survey、以下CSES)を5年ごとに実施してきました。200世帯ほどを訪問し、質問票を使って世帯ごとの社会経済状況を調査しています。1995年の最初のCSES以降5年ごとに調査を重ね、当初のプロジェクトリーダーであった桜井由躬雄先生が2012年に逝去された後も、筆者がプロジェクトを引き継ぎ、30年にわたる長期の村落調査となっています。
初回のCSESの目的は、他の多くの質問票調査と同様、村の基礎的な情報を得ることでした。調査項目は世帯構成員の学歴や職歴、生業活動、消費生活等、多岐にわたりました。しかし、2回目以降の調査では、5年ごとの村の変化を知ることが重要な課題となりました。時代を越えて比較が可能となるよう、基礎的な調査項目に変更は加えませんが、それぞれの時代や村人の状況にあわせて、質問内容を調整してきました。たとえば、2000年代までの調査では、農業生産の詳しい調査が可能でした。水稲だけでなく、野菜や果樹栽培、家畜飼育のそれぞれについて、化学肥料や農薬、飼料等の投入量や価格、栽培や飼育の方法、収入と経費など、詳しい回答を得ることができました。しかし、もっとも最新の2024年の調査では、曖昧な回答が多くなりました。村における農業生産は、かつてほど細心の注意を払って実施されなくなったからです。
また、私たちは現地の事情に即してCSESを実施してきました。すべての質問票はベトナム語で作成しベトナム語で聞き取っているのはもちろん、質問票の作成も、村で研究を共にしてきた研究者仲間と村人の双方で検討しました。したがってそれは質問票を用いるものの、村の概略を知るためのものというより、長期継続調査であることを最大限に生かした、世帯ごとの事情に応じたインタビュー調査、質的調査に近いものとなりました。
筆者にとってこのCSESは、ベトナム農村の急激な変化の中で、変わるものと変わらないものを分別し、時代ごとの個別の研究課題に答えることが第一の目的です。そこから得られた知見を、学際的に検討したり、他の村やより広域の事例と比較したりすることで、農村社会とは何かという大きな問いに対する答えを得たいと考えています。
再び大きな問いについて
冒頭で述べた、研究する側の変化のひとつに、学術研究における成果主義があります。成果の数が特に重視されると、短期的に成果の出る研究がますます増えるおそれがあります。また、その中には、特定分野からのみ地域社会を切り取った視野の狭い研究が増えることも含まれます。成果主義のせいか、大きな問いについて議論を交わす機会が少なくなったように感じます。
成果主義が、大きな問いを持つことができない元凶であるとはいえません。そもそも大きな問いは答えることが簡単ではなく、いくつもの具体的な研究課題をクリアしながら、解答を考えるべきものです。また、短期的な成果、あるいは、特定分野の研究に従事しているからこそ、大きな問いを持たなければ、いったい何の研究をしているのかがそのうちわからなくなります。大きな問いが研究の指針になるわけです。したがって、成果主義の時代だからこそ、大きな問いが必要になるはずです。
私たちのプロジェクトに関していえば、大きな問いへのアプローチと特定の課題を追求することのバランスをどうとるのかは、常に考えどころです。研究メンバーとの議論、学会での発表、あるいは、こうしたエッセイを書きながら考えをまとめることを通じて、両者のバランスを見つけていきたいと思います。

2016年9月撮影。左手前は校長先生
より詳しく知りたい方のための参考文献
ピエール・グルー著、村野勉訳(2014)『トンキン・デルタの農民:人文地理学的研究』丸善出版。
桜井由躬雄(1987)『ベトナム村落の形成:村落共有田=コンディエン制の史的展開』創文社。
Yanagisawa, M. (2000) “Fund-raising Activities of a Cooperative in the Red River Delta: A Case Study of the Coc Thanh Cooperative in Nam Dinh Province, Vietnam.” Southeast Asian Studies 38: 123–141.
柳澤雅之・新美達也・藤倉哲郎・澁谷由紀・小川有子(2025)『百穀社通信 23号Thông Tin Bách Cốc』GCR Working Paper Series No. 5、京都大学東南アジア地域研究研究所。