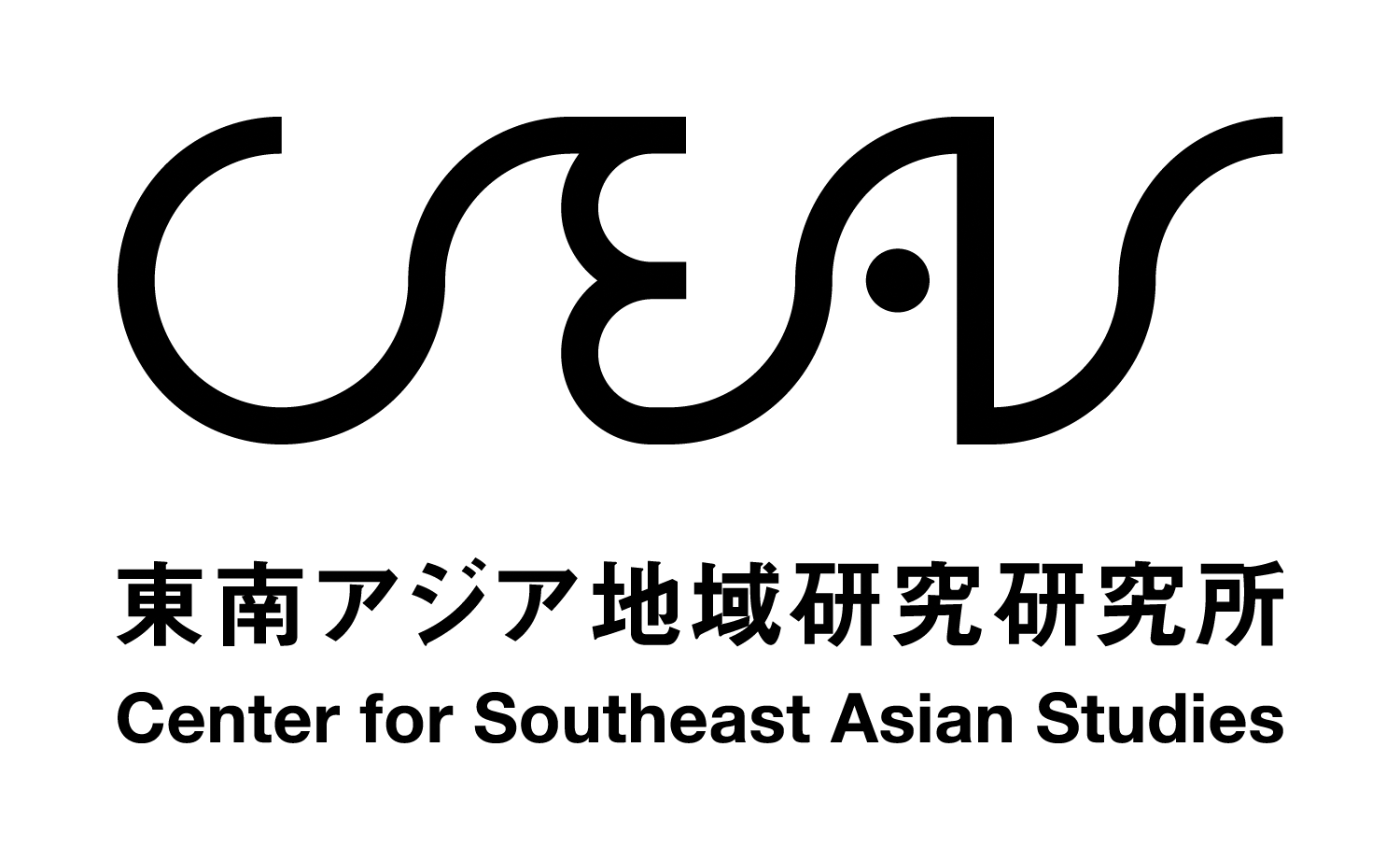石井 周(海事考古学、戦跡考古学)
私が初めて「水中考古学」という言葉に出会ったのは、砂漠の真ん中であった。オレゴン州の高原砂漠で行われていた発掘実習で、私は毎日洞窟に入って砂まみれになっていた。日没後の肌寒さを紛らわすために囲んだ焚き火で、地ビールを飲みながらとある大学院生が発した「水中考古学者」という言葉は、妙に非現実的かつ神秘的で私に強い印象を残した。その後私はアメリカ留学中に、この「水中考古学」という言葉に事あるごとに思いもよらないところで遭遇するが、この考古学の一専門分野が私の人生の舵を大きく取っていくとは当時はまだ知る由もなかった。
湘南地域の漁村で育った私にとって海は常に身近にあった。しかし残念ながら私が日本で過ごす間に「水中考古学」という言葉に出会う機会に恵まれることはなかった。私にとって「水中考古学」とは太平洋を渡って初めて見えてきた故郷への新たな視点である。島国に住む私たち日本人にとって海は外との隔たりの象徴であると同時に、外との繋がりの象徴でもある。稲作、仏教、鉄砲、近代工業技術等、日本の歴史を紐解いてみても、海を渡ってやって来た変革には枚挙にいとまがない。
水中探索技術の進歩やスキューバダイビングの普及と共に発展してきた水中考古学は、世界的に今後ますますの成長が見込まれる考古学の最先端分野である。日本が持つ海岸線の総距離や海域の広さを鑑みれば、そこにどれだけの考古学的発見の可能性が眠っているのかは安易に想像が付くはずである。しかし日本は世界有数の海洋国家であるにもかかわらず、水中考古学の認知度はまだまだ低い。そんな現状下で、もっと多くの日本人に水中考古学とその魅力を知ってもらおうと書かれた本が佐々木ランディ氏の『水中考古学:地球最後のフロンティア』である。
本書は船の専門家である船舶考古学者の著者が、自身のアメリカ留学経験や水中考古学との出会いなどの個人的な話とユーモアを交えながら、日本と世界の水中遺跡やその歴史、水中探査技術について易しく紹介してくれる。著者の溢れかえる水中考古学愛と相反する紙幅の都合上、終盤駆け足にはなるが、本書は水中考古学に初めて触れるには最適な入門書である。
本書の中で著者は「水中考古学」という言葉があまりよくないと言う。水中考古学者と言っても、結局は考古学者である。考古学者は研究の対象によって定義されるべきであって、働く環境で定義されるべきではない。船舶や交易品、水没地形など研究の対象がたまたま水の中に残ることが多いだけである。水中という特殊な環境を克服し、場合によっては活用して水中考古学者は人類の痕跡を探究し続ける。その特殊さゆえに水中考古学者は興行師のように現場を点々とする場合もある。そんな苦労を覚悟しつつも著者は水中考古学の魅力を語り、いつか日本でも水中考古学者や水中遺跡が当たり前に認知される日を夢見る。
(イラスト:Atelier Epocha(アトリエ エポカ))
本記事は英語でもお読みいただけます。>>
“The Potential of Japanese Underwater Archaeology”
by Hiroshi Ishii