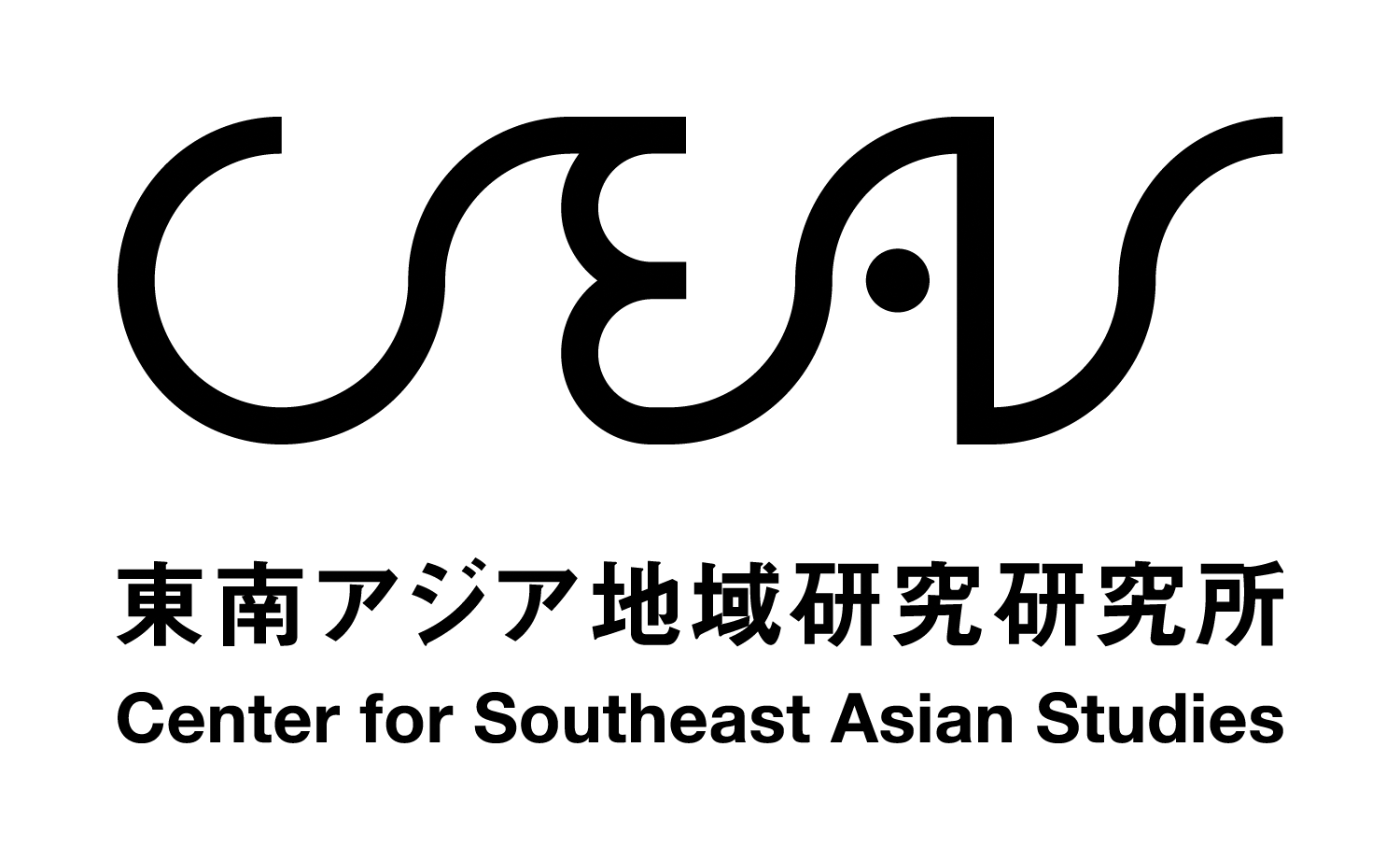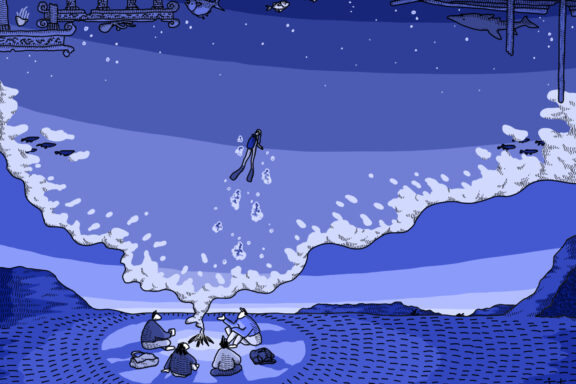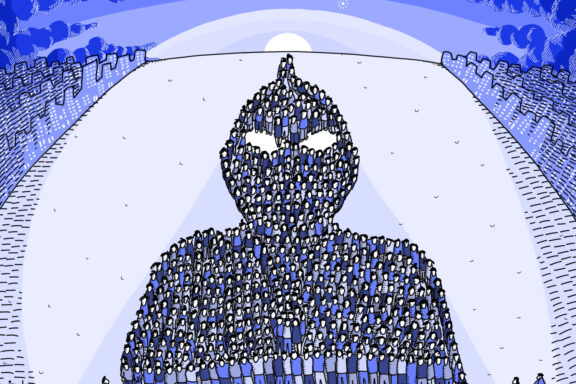ジュリー・アン・デロスレイエス(地理学、政治生態学)
私の母国フィリピンは暴風雨によく見舞われる。毎年平均20の熱帯低気圧がフィリピン諸島を通過する。台風は珍しいものではなく、その接近を予想したり、遭遇に耐え忍んだり、どうにか切り抜けたりといったことは生活のリズムに組み込まれている。しかし2009年9月の台風オンドイ(国際名ケッツァーナ)は猛威をふるい、備えが盤石な住民をも不安に陥れた。ほんの数時間で1カ月分の雨をマニラ首都圏(メトロマニラ)に降らせ、首都は広域にわたって浸水した。
暴風雨が脆弱なコミュニティを襲い、インフラが崩壊する──オンドイはメトロマニラの都市化のもろさを露わにする最初の猛烈な台風となった。そしてクリスチャン・サグイン著『都市生態系の周縁にて』(原題Urban Ecologies on the Edge、邦訳は未刊行)はこのよく知られた話から始まる。道路が川になり、車がおもちゃのように積み重なり、人々が屋根の上にうずくまって救援を待つ姿を多くのフィリピン人は忘れないだろう。
もっとも、サグインの記述は文字どおりの意味においても、概念の上でも、メトロマニラの領域にとどまらない。メトロマニラ南東部と接するフィリピン最大の湖・ラグナ湖に読者の目を向けさせ、ラグナ湖が川や用水からあふれ出た水を吸収し、首都の洪水対策に重要な役割を果たしていると論じる。市街地の浸水被害を防ぐには、あふれ出る水を計画的に湖に放流し、洪水リスクを湖岸沿いのコミュニティに転嫁する必要があるのだ。
このように本書は、私たちにとって既知と思える事柄をまったく別の観点から考えさせる。都市はイノベーションや経済成長、進歩の中心地とみなされがちだが、都市生活を支える作用は覆い隠されている。目に見える地理的境界や行政区分の向こう側で動いていることが多いからだ。本書は、メトロマニラのような都市の日常の機能が「周縁部」での資源の流れや労働、生態環境に依存していることを想起させる。
ラグナ湖の設計と変遷は首都のニーズや脆弱性と密接につながっているという。洪水など「望ましくない危険要因」を吸収する機能とは別に、ラグナ湖は都市の食料生産、水の供給、干拓に「格好のフロンティア」だとも考えられ、用途が再創造されてきた。ラグナ湖はティラピア、ミルクフィッシュ(フィリピン名バンガス)、コイなど食用魚の主要な養殖場になっており、これらの魚はフィリピン人にとって欠かせない食材であり、メトロマニラで広く消費されている。またラグナ湖の養殖生産量は従来の捕獲漁業を上回って増加傾向にあり、人口が増え続ける首都の食料需要を満たし、手ごろな蛋白源の供給に資するものとされている。
湖が媒介する資源の流れが首都マニラの成長を静かに支えてきた。戦後1950年代から60年代にかけて人口が急増し、今では1300万人を超える巨大都市になっている。ラグナ湖への多年にわたる技術的・政治的・経済的介入は発展や保全のために必要とされ、それはつねにメトロマニラの開発と関連づけて再構築されてきた。とはいえ、ラグナ湖は受動的な空間であるばかりではない。国の計画、投機資本、厳しい自然、隅に追いやられたアクターの日々の営為が(たいていはやみくもに、唐突に、予期せず)ぶつかり合いながら、都市存続の要求をめぐってせめぎあっている。そこはリスクや資源、所有をめぐって熾烈な闘いが展開される重要な場である。
都市開発の主要なナラティブにおいては、ラグナ湖は完全に使い捨てにはされずとも不可視化されている。しかし本書は、ラグナ湖が都市形成に重要な役割を果たしていると強調する。サグインの言葉を借りると、ラグナ湖はメトロマニラの「トイレであり水槽」、つまり排水場であると同時に生活用水の水源でもあるという矛盾した役割を抱え、望まれないものを吸収する一方で、必要不可欠なものを供給してもいる。こうした二重の役割は偶然の産物ではなく、首都存続の基盤を成している。
したがってラグナ湖はメトロマニラによって形成されるだけでなく、メトロマニラを能動的に形成してもいる。台風オンドイなどがもたらす直接的な惨状の先に何を思い描くのか。都市の脆弱性とレジリエンスを生み出す力学はどのようなものか。また一連のプロセスのコストは誰が負担するのか。大きな問いが投げかけられている。
(イラスト:Atelier Epocha(アトリエ エポカ))