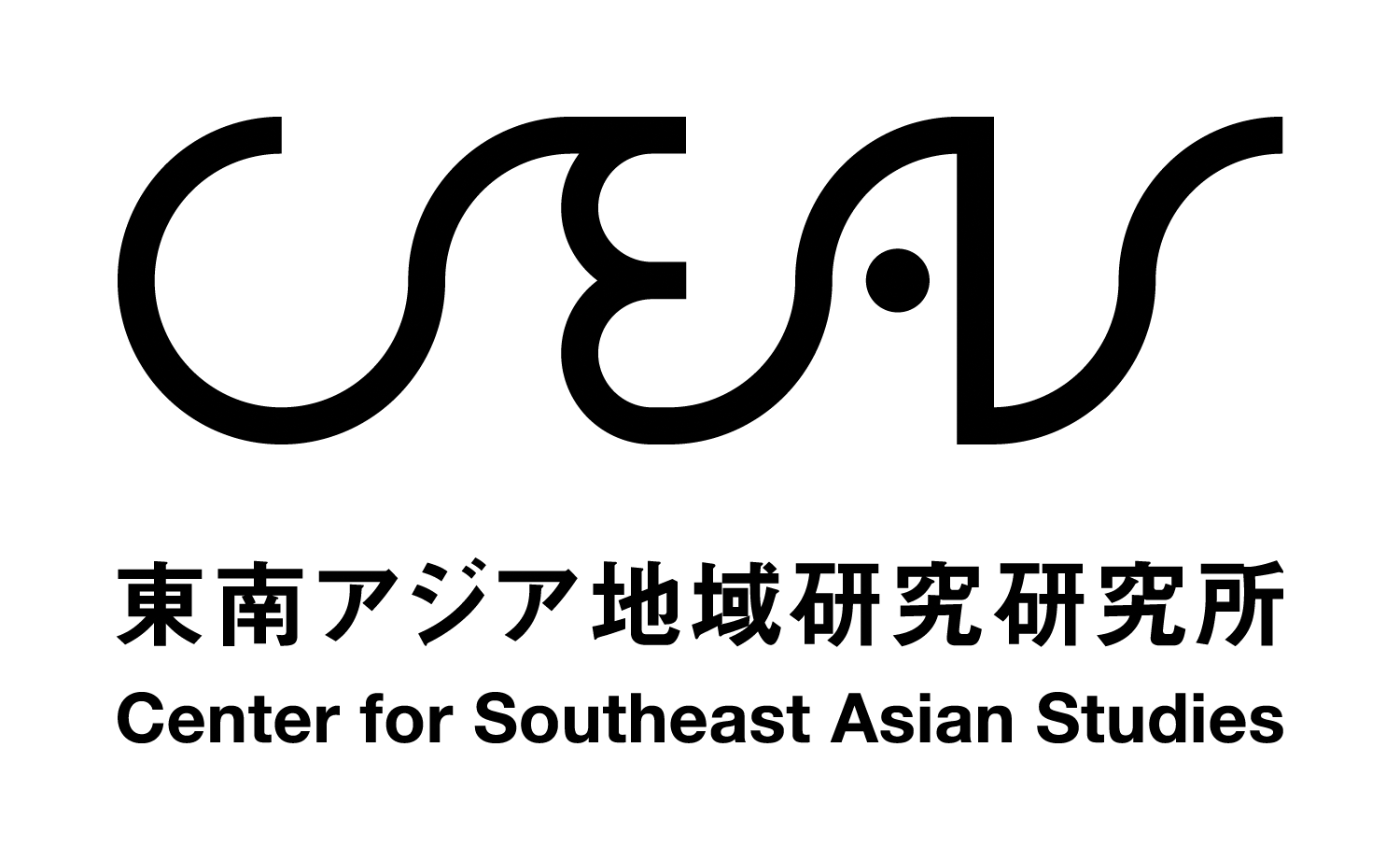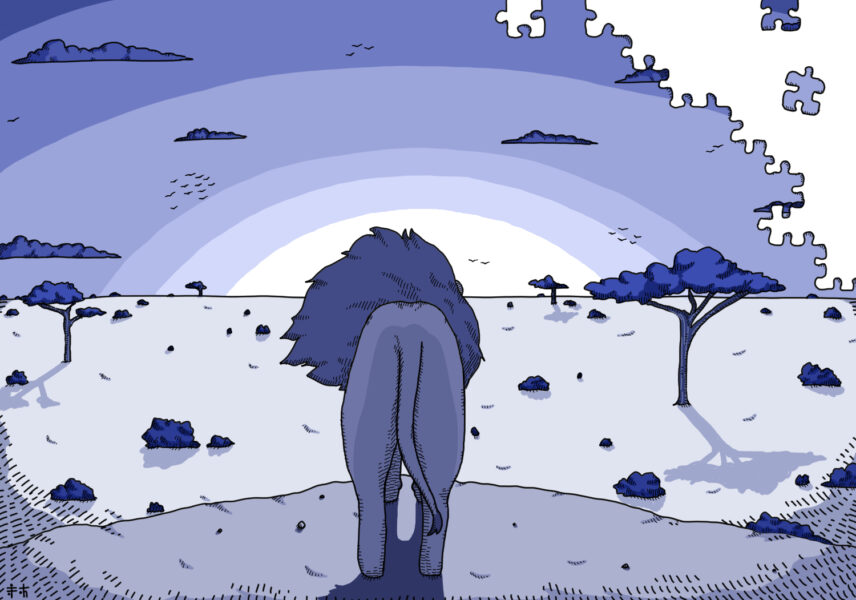河野 泰之(東南アジア研究、農学)
私は東南アジアの農業や農村社会や自然環境の保全について研究している。にもかかわらずと言っていいかどうか分からないが、最近、立て続けにアフリカを舞台にした本を読んだ。東南アジアは一通り歩き回った、アフリカってどんなところなんだろうという興味がふつふつと沸き起こっているからかもしれない。そんな深い気持ちはなく、たまたまかもしれない。
そんなマイブームのきっかけになったのは、『ルワンダでタイ料理屋をひらく』(唐渡千紗、2021)だ。副題にある「日本人シングルマザー、アフリカで人生を変える!」というキャッチコピーもだが、「タイ料理屋」という言葉がひっかかった。私の研究の本拠地はタイなので、アフリカの真ん中でどうやってタイ料理を作るの?、アフリカの人ってタイ料理のことをどう感じたの?、日本人なのになぜわざわざタイ料理を選んだの?とかの疑問がタイトルを見たときに浮かんだ。決してたくましくはない主人公(作者)が、決してしっかり者ではないが柔軟に生き抜こうとする人々とともに成長する姿が描かれていた。ルワンダではかつて、ツチ族とフツ族の凄惨な紛争があった。その記憶を背負いながら生きる人々の葛藤を垣間見ることができた。
次は『たまたまザイール、またコンゴ』(田中真知、2015)。この本にはネットで何かを調べているときに出会った。アフリカの大河、コンゴ河の川下りにも興味をひかれたのだが、著者の川下りの相棒が偶然にも私の講義をかつて受講した学生だった。私は、大学院修士課程で「開発生態論」という講義を担当していた。この講義には東南アジア研究を専攻する学生もくるし、アフリカ研究を専攻する学生もくる。両方の学生がともに受講する数少ない講義である。授業は、講義というよりも、議論中心なので、学生同士、自然と仲良くなる。それをいいことに、彼は授業が終わるとすぐに女子学生に声をかける。そんな、少しちゃらちゃらした学生だった彼が、フィールドでどのような経験を積んで立派な研究者になったのかを知りたかった。結果は、予想にたがわぬものだった。川下りをしていると、とんでもないことが次から次へと起こる。そんなハプニングを楽しみながら、フィールドでもちゃらんぽらんに生きている。だからこそ、失敗を恐れず、ちょっと無謀かなと思うようなことにもチャレンジしていく。こういう経験の積み重ねが彼の力量を磨いた源泉に違いない。
最後に『太陽の子 日本がアフリカに置き去りにした秘密』(三浦英之、2022)。1970年代にアフリカで鉱山開発に従事していた日本人が現地の女性との間にもうけた子どもたちのその後を追ったドキュメンタリー。ある日突然、父親が日本に帰国し、そのうち連絡が取れなくなるという家族の出来事は、子どもたちの生きざまや感情の揺らぎに決定的な影響を与えている。ただ、それを「決定的」にしたのは、彼ら/彼女らが生きている社会の文化や歴史と密接に関わっていることを学んだ。
自分が描くことができる、想像することができる世界がある。でも、それは現実のごく一部でしかない。イマジネーションを磨けば、描くことのできる世界は広がるだろう。それでも、イマジネーションの向こう側にもっと広く深い現実があるんだろうなあ。アフリカの本を読みながら、そんなことを感じた。
(イラスト:Atelier Epocha(アトリエ エポカ))