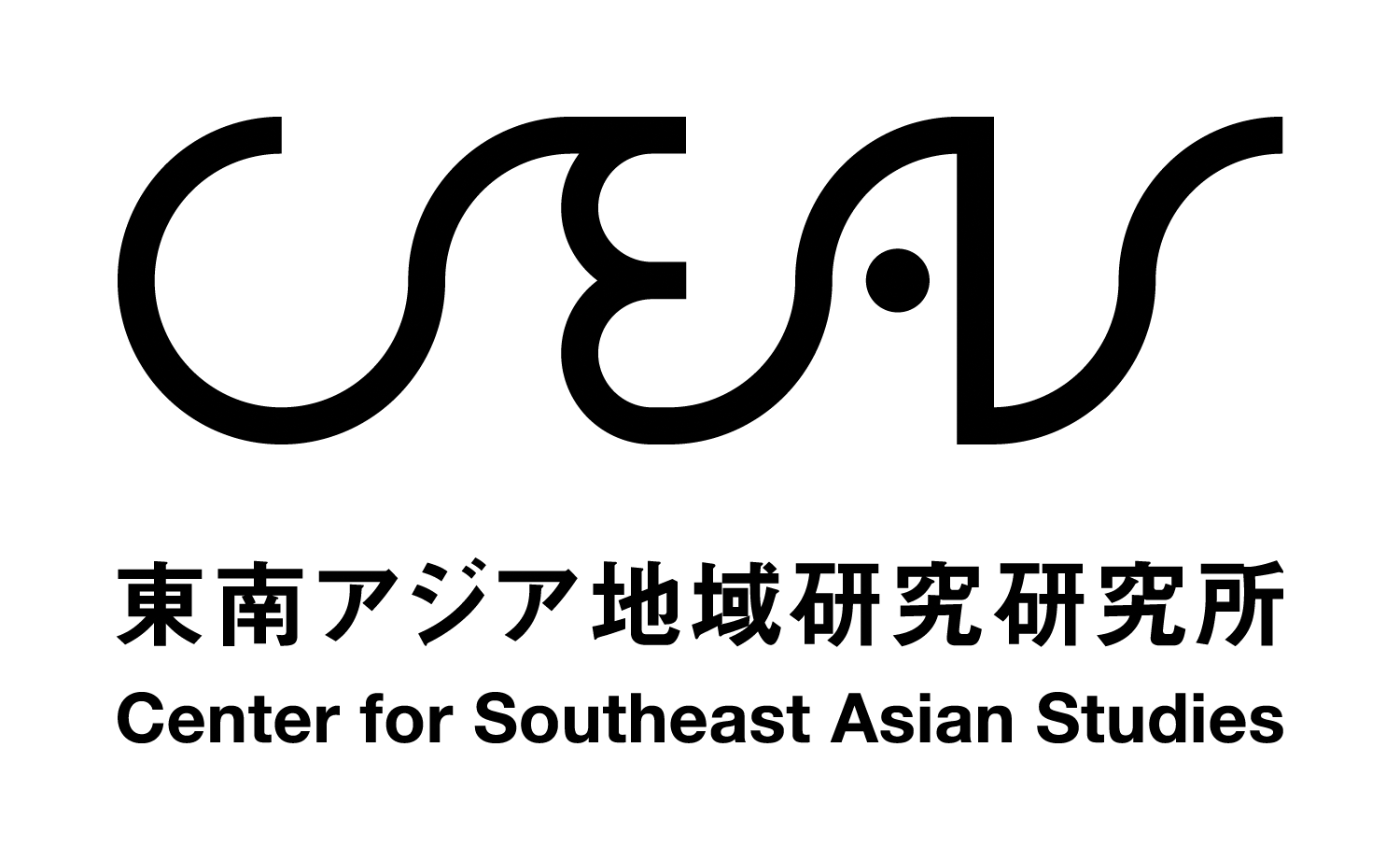山田千佳さんインタビュー

略歴
山田千佳氏は、2020年に京都大学東南アジア地域研究研究所の特定研究員に着任、2022年より同助教。国立精神・神経医療研究センターの客員研究員。京都大学で看護、東京大学で公衆衛生、四川大学で中国語を学び、地域保健行政及びNGOに従事した後、2019年に神戸大学で博士号(保健)を取得。健康と社会の接点に関心を持ち、日本、中国、フィリピン、インドネシアにて定性・定量研究を行ってきた。現在、インドネシアにて物質使用障害の治療法評価や精神作用物質の下水疫学開発を行いつつ、同国の薬物をめぐる社会史を調査している。ダイキン工業との共同プロジェクトでは、東南アジアにおける近代化と空調の社会史を学び、気候変動時代の都市居住を考える研究を行っている。
「ハーム・リダクション」という言葉を耳にされたことがあるでしょうか。狭義には、HIV感染や過量服薬など薬物使用による健康への害を防ぐための公衆衛生プログラムとして知られているかもしれませんが、本質的には、社会から排除されてきた薬物使用する人たちの権利回復を目指す運動として、ハーム・リダクションは世界中で展開されてきました。現在、インドネシアでハーム・リダクションの調査を進めながら、社会と薬物との関わりの歴史をたどり、ボトムアップの草の根実践とトップダウンの公衆衛生政策との間にある運動のダイナミクスを批判的に追跡している山田千佳助教にインタビューしました。
──ご研究について教えてください。
私はインドネシアで、ハーム・リダクションと呼ばれる運動について学んでいます。ハーム・リダクションとは?と考えること自体が課題の一つでもありますが、簡潔に言えば、薬物使用を禁止や削減することなく、薬物を使用する人たちの権利や尊厳を守ろうとする運動です。この運動は、薬物使用する人たちが自分や大切に思う人の命を守ること、そして、刑務所に入れられたり、治療やリハビリテーションを強制されたりすることへの抵抗として始まりました。私はこのハーム・リダクションを、20世紀後半に生まれた世界で最も重要な社会運動の一つだと考えています。今日「薬物」と呼ばれるものの使用や取引を犯罪とすることが世界中に広まったのは、1960年代以降と、比較的近年です。ハーム・リダクションとは、犯罪者とラベル付けられた人々が連帯し、権威による権力行使の正当性に疑義を唱え、奪われた市民権を取り戻そうとする過程とも言えるでしょう。
インドネシアにおいてこのハーム・リダクションを研究する面白さは、ポスト・コロニアリズムやネオ・コロニアリズムを考えることに通じる点です。時に、ハーム・リダクションの理念は人権などの概念と同様、東南アジア諸国のリーダーから西洋思想の押し付けであるとして一掃されることがあります。しかし皮肉なことに、薬物との関わりを基準に人々を処罰するという考えは、冷戦時代に西側諸国と国際連合によって規範化されたものであり、独立後まだ年数浅く、反共産主義政策をとったインドネシア・スハルト独裁政権はこれを採択し、法律化したという経緯があります。当時の背景として、例えば米国では、人種・民族的マイノリティに犯罪者とラベル付けし排除するという政治的な目的があり、大麻を黒人、コカインをメキシコ系、アヘンは中国系移民と関連付け、処罰を正当化しました。さらに時代を遡れば、オランダ植民地政府と日本占領軍は、ジャワを舞台にアヘンやコカを商品化し、先住民を労働力として搾取し、華人・華僑に監督させ、大量生産して富を築きました。植民地化される前を見れば、現在インドネシアと呼ばれる地域では何世紀にも渡って、精神作用のある物質は食べ物や治療薬、虫除け、儀礼などに使われていましたが、国内外の政治・社会的な影響を受けて、歪められてきました。
それにもかかわらず、ハーム・リダクション運動はインドネシアでも90年代終盤以降、民主化と地方分権化が進んだ時代に開花しました。その運動の、特に草の根レベルでは何が起こってきたのか、その担い手はどんな社会を生きてきた人々なのかを学ぶのが、私の研究課題です。
──研究で出会った印象的なひと、もの、場所について、エピソードを教えてください。
現実を単純化していた自分の認識が、フィールドで壊されたとき、印象に残ります。例えば、宗教と薬物使用は必ずしも対立するものではありません。ハーム・リダクション運動家たちには宗教への信仰心が強い人が多くいます。プロテスタントのBelindaさんは「薬物を使うという罪をたくさん犯してきたからこそ、他の人の役に立ちたい。だから薬物をより安全に使えるようにする活動をしている」と言います。ムスリムのWan Traga Duvan Barosさんは毎日5回のお祈りを欠かさず、自分や友人が過量服薬しないように神に祈るそうです。同じくムスリムのSuryana Nugrahaさんは自分のことを「ジャンキー・シャリア」と呼び、ラマダン月には昼間に断食し、夜明け前のサフールとしてヘロインを使います。他の例としては、インドネシアのハーム・リダクションが私が想像する公衆衛生ではあり得ないエピソードで溢れていることです。メタル音楽やバイクのツーリングといったカウンターカルチャーによって広まった運動であり、時にプレマンと呼ばれるゴロツキをハーム・リダクションのスタッフとして雇い、ある地区のギャングと良い関係を作って、その地区の薬物を使う人たちにアウトリーチをしていたこと等は良い例です。それでも、メタルTシャツを着て、長髪で刺青を入れたハーム・リダクション運動家の口から語られるのは、私が学部生の頃に公衆衛生の講義で習ったオタワ憲章の中のコミュニティ・エンパワメントの話であったりします。そんな点に魅了されています。


──特に影響を受けたものや本を教えてください。
社会学者の佐藤哲彦先生のご研究に大きな影響を受けています。ハーム・リダクションについてより批判的に学びたいと思ったのも、佐藤先生が欧州のハーム・リダクション現場でされたフィールド・ワークについて報告されているのを伺ったのがきっかけでした。また、戦後日本の覚醒剤取締法の制定過程を分析し、政治・社会・経済的文脈の中で、覚醒剤が在日朝鮮人、共産主義、違法経済活動、精神異常者などと結び付けられ、「我われ」と「他者」の境界線をひく装置となったことを示されています。これら欧州、日本での研究から学ばせていただきながら、インドネシアと比較し、地域の関係性を考える相関研究に発展させられればというのが私の夢です。
また、最近、イタリアの理論家ジョルジョ・アガンベンの著書『ホモ・サケル』に興味を持っています。アガンベンはその著作の中で、主権国家の政治的領域は、その国家が代表する社会や市民そのものの一部を例外とすることによって構成されると説いています。
薬物を使う人たちは、アガンベンの言うところの、国民国家によって例外化された「剥き出しの生」です。政治の主体である「人民」と、政治の対象でしかない「剥き出しの生」の峻別に利用されるのが、生物医学的な知です。本来、「薬物」は使用する文脈によってその作用は千差万別であるにもかかわらず、少数の医学実験や症例報告が取り上げられ、あたかも「薬物」を使えば脳や身体、そして人格まで破壊されるかのような言説が支配的になっていきました。そして、薬物を使用する者は市民としての権利が認められないのが当然だとされました。そのような処遇は、健康な国民を再生産し生産労働させるために、現代の国民国家から必要とされました。
もともと薬物を使用する人たちの「剥き出しの生」は死と隣接していました。それが、HIV/AIDSの世界的な蔓延をきっかけに、死とぴったりと重なる事態となりました。しかも、当時は不治の感染症であったために国民国家の危機として認知され、薬物を使う人たちは感染源としての負の烙印が追加で押されることにもなりました。一方、生存の危機はクィア運動と同様、薬物を使用する人たちが集体化し、主体化する契機ともなりました。
このように生まれた波はグローバルなうねりとなってインドネシアにも届きましたが、そこにはネオ・コロニアリズムが影を落とし、国際保健とその援助を受けた国家のアジェンダが見え隠れしているのも事実です。即ち、薬物使用する人を感染源とし、その脅威に晒されているグローバルでナショナルな「公衆」をいかに守るかという「公衆のための衛生」という大義名分があるからこそ、ハーム・リダクション運動は正当化され、トップダウン式にプログラムが展開されている側面もあります。
しかし、薬物を使用する人たち自身が、政治の中で対象化された自分たちの状況を批判的に考察し、主体化しようというボトムアップ型の動きが見られることも確かです。それは生物学的事実としての生への権利だけではなく、市民として生きるということへの権利を取り戻そうという運動です。インドネシアのハーム・リダクションを考える時、「公衆衛生」の「公衆」には誰が包含されるのか、何をもって「衛生(もしくは健康)」だと言うのか、そしてそれらを決めるのは誰なのかが問われているように思います。

──フィールド調査を行う上での苦労や工夫をお聞かせください。
子育てとの両立でしょうか。私は娘が生まれてから東南アジアでの研究を始めたので、最初の調査から悩みました。幸い、指導教官の松尾博哉先生は産婦人科医の先生で、1歳半だった娘との渡航も温かく応援くださり、平日日中はフィリピンの保健センターの方に娘の面倒を見てもらって、何とか調査をすることが出来ました。今は娘は小学生で、1週間渡航するのも、特に自分の研究のためだと罪悪感を感じて悩むことが多いです。しばらくは短期で通うのを積み重ねるつもりです。ただ、娘が小さい時に初めてのフィールド・ワークに付いてきてくれた(勝手に連れて行ったと言った方が正確ですが……)ことに大変感謝しています。それは、最近はそんなこともなくなりましたが、私は1人で調査に行くと、緊張と興奮のせいか2日以上寝られなくなったりしていました。それが娘がいると強制的にスイッチ・オフするのでメリハリがつき、元気にフィールド・ワーク出来るからです。また、子どもが一緒だからこそ覗くことのできた世界もあったと思います。
──若者におすすめの本についてコメントをいただけますか。また、これから研究者になろうとする人にひとことお願いします。
若者という括りでは私はコメント出来る立場にないのですが、医療系など実学と呼ばれる分野で学んで来られた読者には、共感いただけるのではと思うことを述べます。こういった分野にいると、「この研究が実践にどう役にたつのか?」と問われ、目指すべき状態についての規範に縛られることがあります。そうすると、目指すべきと思っている状態は、本当に良い状態なのか?という大切な疑問を持ちにくくなりますし、フィールドで自分の純粋な好奇心から湧いてくる疑問を追いかけることが、望まれていないように感じたりします。その場合、自分の関心事が人文・社会科学の中でどのように議論されてきたのか、学んでみることをぜひお勧めしたいです。そうすると、取るに足らない事象であると追いかけるのを諦めていた疑問に関連して、すでに圧倒されるような研究の蓄積があり、そこに一生をかけているような先人に出会って好奇心を取り戻すこともあると思います。その過程では、自分の視点や実践、研究方法論への批判に出会い、所属している学術や専門職コミュニティが相対化され小さく萎んで、どう次の一歩を踏み出して良いか分からなくなったりもします。そんな時、地域研究をされている先生方は素人になる大切さをよく説いておられるので、それを思い出し、フィールドでの色々な見方を養っているのだから寄り道をして良いんだと自分に言い聞かせています。
(2024年2月8日)