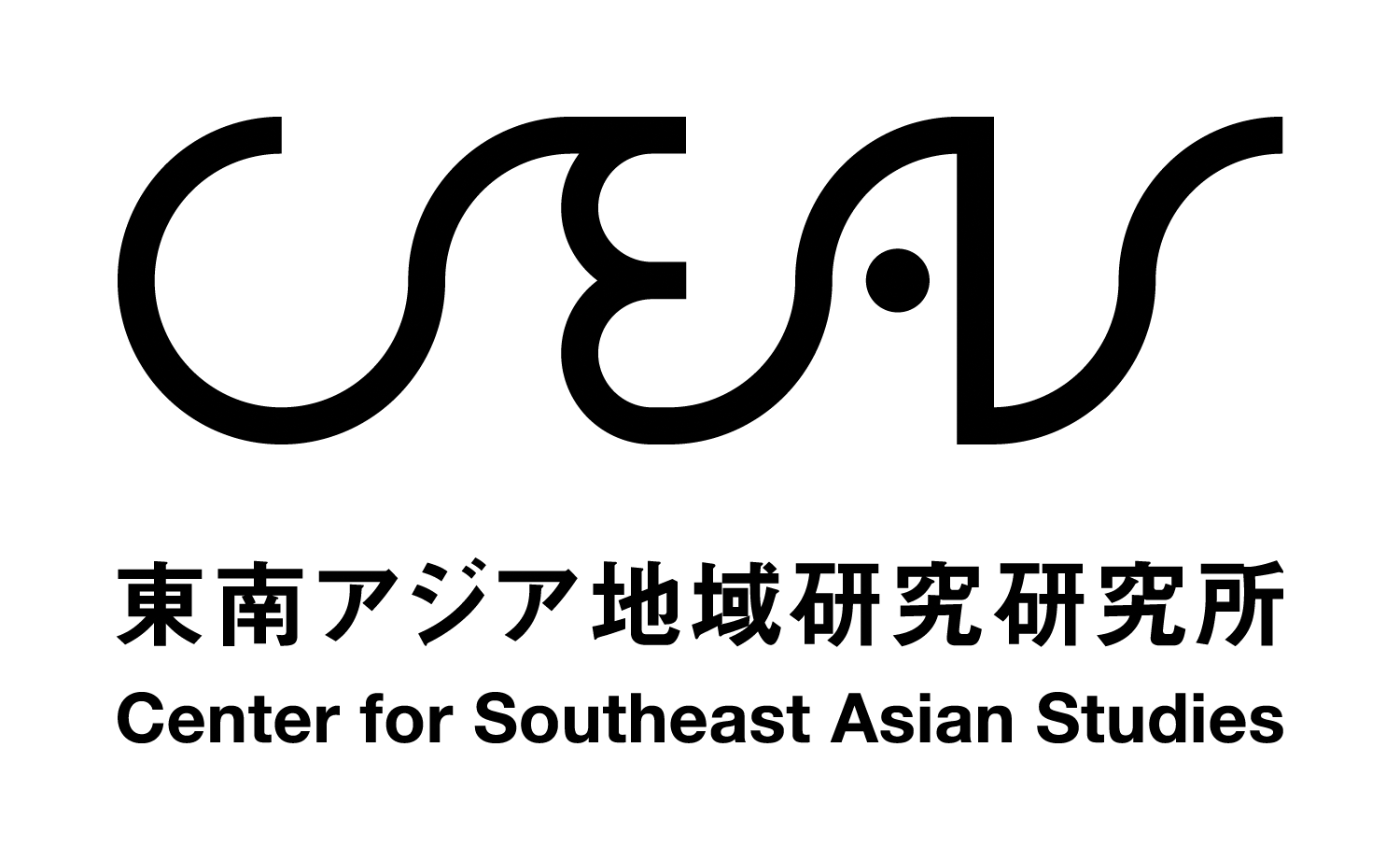マリオ・ロペズ(文化人類学)
2025年2月22日、清水展名誉教授が逝去されました。人類学者であり、フィリピン研究の専門家である清水教授は、友人たちから「Hiro」の愛称で親しまれ、長年にわたり数多くの学生の教育と指導に尽力され、その功績は学界内外で広く認められています。先生は、その輝かしいキャリアの中で、日本語で5冊、英語で3冊、計8冊のモノグラフを著し、また両言語で約70本の論文を発表されました。東京大学大学院を修了後、同大学で助手を務められ、その後、九州大学大学院比較社会文化研究科(1985–2006)、京都大学東南アジア地域研究研究所(2006–2017)において教授として研究と教育にあたられました。
清水教授は、第二次世界大戦後の神奈川県横須賀市に生まれ、戦後同地に駐留していた米海軍の圧倒的な存在感のもとで育ちました。人格が形成される重要な時期に米軍の影の下で暮らした経験は、現代日本社会におけるグローバルな権力構造や大衆文化の影響に対する清水教授の深い関心を呼び起こしました。この体験はやがて、戦後日本を形作ってきたアメリカの強大な影響力を「学び直す」手段として人類学を志すという、清水教授にとってきわめて個人的かつ知的な旅の出発点となったのです。
1976年、博士課程の大学院生だった清水教授は、後に40年以上にわたって生涯を通じて関わり続けることとなる、フィリピンルソン島の山岳地帯に暮らす先住民族アエタとの共同生活を始めました。人類学者の中根千枝教授の指導のもと、フィールドワークを重ね、その成果として最初の2冊の主著、Pinatubo Aytas: Continuity and Change(1989年)および『出来事の民族誌:フィリピン・ネグリート社会の変化と持続』(1990年)を出版しました。これらの著作は、アエタの歴史を丹念に掘り下げ、彼らの社会生活におけるダイナミズムと、環境や社会の変化に対するしなやかな適応力を描き出した重要な研究として高く評価されています。
日本の学界においては、清水教授はフィリピンで1986年に起きたエドゥサ革命(ピープル・パワー革命)に関する画期的な分析で評価を得ました。3冊目の著書『文化のなかの政治:フィリピン「二月革命」の物語』は、マルコス独裁政権に対する民衆運動の背景を探求したものです。この民族誌では、カトリック教会が果たした極めて重要な役割や、革命の展開に深く影響を与えた宗教的背景について検証しています。本書は政治運動家や一般市民の精神世界を理解しようとする試みであり、政治プロセスを政治家や政党の闘争と妥協として捉える従来の見方を超えようとしました。清水教授は文化や宗教の語りが政治運動を形作る重要な要素であることに注目し、従来の分析の枠組みを超えて、「ピープル・パワー」革命の基盤を再考するという新しい視点を提示したのです。
1991年6月ピナトゥボ山が大噴火を起こし、清水教授の調査地のひとつも深刻な被害を受けました。周辺に暮らしていた先住民アエタは避難を余儀なくされ、大きな打撃を受けました。当時、清水教授はサバティカル中でしたが、この災害によって、学問の枠を越えて行動することを求められることになります。先生は9か月間にわたりNGOのボランティアとして、緊急援助や復旧・復興支援に従事しました。この経験は彼のキャリアに大きな転機をもたらし、研究者としての社会的責任を見つめ直すきっかけとなりました。すなわち、従来所与とされてきた受動的な観察者としての人類学者の役割に疑問を抱き、より積極的に関与する参加型アプローチへと移行していったのです。その転換は、のちに出版された第4・第5作The Orphans of Pinatubo: Ayta Struggle for Existence(2001年)および『噴火のこだま:ピナトゥボ・アエタの被災と新生をめぐる文化・開発・NGO』(2003年)に色濃く表れています。これらの著作では、噴火当時の人びとの証言を記録するとともに、避難と再定住によってアエタ社会がどのように変化し、新たな生活様式に適応していったかが丹念に描かれています。これらの仕事は、彼にとって人類学的転換点であったと同時に、人生を大きく揺るがす逆境に直面した人々の現実に寄り添い、行動することの重要性を人類学者たちに問いかける、実践志向のアプローチでもありました。
アエタ研究およびフィリピン研究への清水教授の深い関わりは、彼の著作の出版の順序からも読み取ることができます。最初の著書Pinatubo Aytas(1989年)と4冊目の著書The Orphans of Pinatubo(2001年)は、いずれも対象読者に届くよう英語で執筆され、まずフィリピンで出版されました。特に後者は、英語だけでなくフィリピン語との対訳でも刊行されました。これは、彼自身の研究を学術的議論に留めることなく、研究の対象となったコミュニティがその成果にアクセスできることを清水教授が強く望んでいたことの表れです。

フィリピン社会への長年にわたる関わりの中で、清水教授はフィールドワークの範囲をルソン島北部イフガオ州の山岳地帯にある辺境の村、ハパオへと広げ、そこで16年間にわたって調査を続けました。この調査の成果は、世界遺産にも登録されている棚田の村で、グローバリゼーションがどのように展開していくのかを問いかけた第6作『草の根グローバリゼーション:世界遺産棚田村の文化実践と生活戦略』(2013年)にまとめられています。本書では村人たちによる森林再生活動や文化復興運動、さらに著名なフィリピン人映画監督キッドラット・タヒミックの芸術的貢献などを取り上げ、グローバリゼーションの周縁に位置する村の人びとが、それをどのように受け入れ、応用し、自らの文化と生活に活かしているのかについての清水教授の深い洞察が示されています。この研究を通じて、彼は「応答する人類学」(Anthropology of Response-ability)という概念を提唱しました。これは、研究者が関わるコミュニティに対してより深い責任感を持ち、積極的に関与する姿勢を促すものです。清水教授はこの視点をより広い国際的読者層にも伝えるため、2019年には本書を改訂・英訳し、Grassroots Globalization: Reforestation and Cultural Revitalization in the Philippine Cordillerasとして出版しました。この翻訳は、異文化間の対話に対する彼の取り組みをさらに強化するとともに、グローバリゼーション、文化の持続可能性、そして道徳・倫理の人類学に関する世界的な学術的議論に貢献する重要な一歩となりました。
最後の著作となった『アエタ 灰の中の未来:大噴火と創造的復興の写真民族誌』(2024年)は、先住民アエタとの半世紀にわたる関わりを凝縮した写真民族誌であり、長い旅の集大成とも言える一冊です。ビジュアルな工夫が凝らされ、研究者にとどまらず、一般の読者にも強く訴えかける内容となっています。1991年のピナトゥボ山の壊滅的な噴火前後のアエタの生活をたどりながら、彼らのレジリエンス(回復力)に焦点を当てた本書は、災害後のコミュニティの復興において人類学者が果たすべき「スローワーク」の重要性を強調しています。すなわち、目先の短期的な介入ではなく、持続可能な長期的視点に立った復興支援のアプローチが求められることを指摘しています。本書に込められたこのメッセージは、清水教授のこれまでの著作に一貫して見られるテーマ、つまり「創造的復興」という考え方と深く結びついています(清水・飯嶋 2020)。自然災害は確かに自然や生活を壊滅させますが、一方で、個人やコミュニティにとっては変革、再生、そして前向きな変化のきっかけにもなり得る。そうした視点が、清水教授の研究と実践の核心にありました。
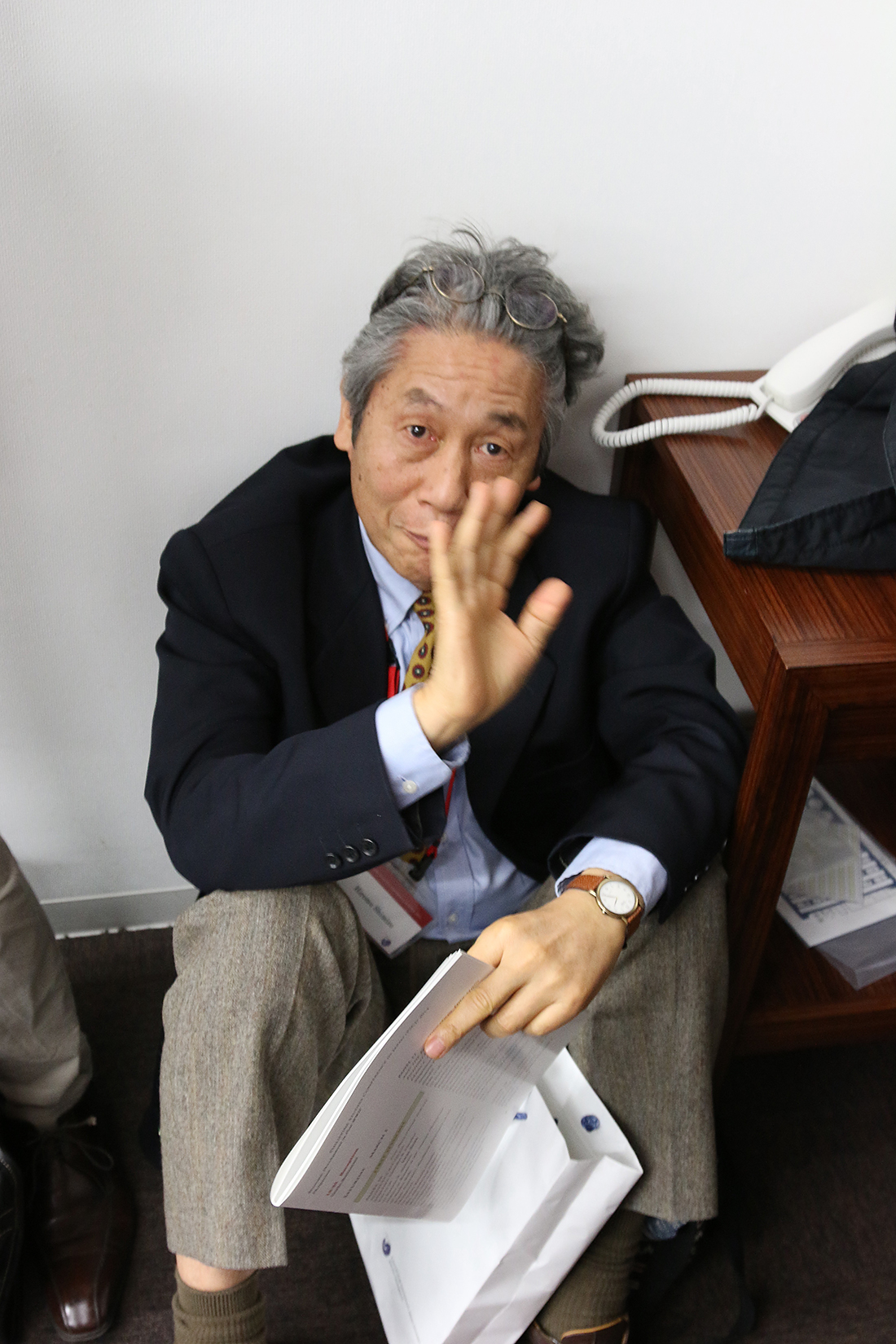
人間性にあふれる研究者であった清水教授は、フィールドワーカーとしての強いコミットメントのもと、コミュニティの変革に真摯に取り組みました。フィールドで過ごした長い年月は、彼の人類学に対する考え方を形成しただけでなく、彼自身の歩みの意味や、その背後にある社会的・政治的文脈を捉える手がかりとなり、この分野の未来に対する明確なビジョンを育む土台ともなりました。清水教授は自身のアプローチについて、「フィールドワークの基本である参与観察の、参与という活動をラディカルに(過激に、根本的に)追求する選択肢を成りゆきで選ばざるをえない次第となったのだ」と表現しています(清水 2016: 398)。この姿勢こそが、彼のフィールドワークの基礎となりました。彼は、従来の受動的な観察を超えて、意味ある行動へと移行することの重要性を説き、人類学のあり方そのものを再定義しようとしました。彼にとって、人類学は単なる知的探究の道具ではなく、人類学者が理解しようとする人々の闘争や日常に深く根ざした方法論でした。生涯を通じて、研究対象となるコミュニティに対して積極的に応答する人類学を提唱し、参加型活動の拡大を力強く訴え続けました。
清水教授は、1991年に『出来事の民族誌』で澁澤民族学振興基金の澁澤賞を受賞。2016年には日本文化人類学会賞を、2017年には『草の根グローバリゼーション』で日本学士院賞を受賞されました。そして2024年、長年にわたる功績が認められ、瑞宝中綬章を受章されました。
2006年、清水教授は九州大学から京都大学東南アジア研究所(当時)へ移籍されました。研究所に所属することで、ゆっくりとフィールドに没頭して過ごせるだろうと期待していたものの、その後、2010年から2014年にかけて所長に任命され、その願いは叶いませんでした。在任中、彼は「東南アジア研究コンソーシアム(SEASIA)」の設立や、英文ジャーナルSoutheast Asian Studiesの創刊に尽力されました。これらの取り組みを通じて、CSEASを世界的な研究拠点として確固たる地位へと押し上げたことは、間違いなく彼の重要な功績の一つです。所長としての重責により、フィールドでの時間は制約されましたが、その分、研究所を通じて国際的なネットワークを強化し、発信に力を注ぎました。このようにして、彼の学術的貢献は、現地での実践のみならず、制度的・組織的な基盤づくりの面にも色濃く残されています。
かつて学生であり、後に同じ職場で苦楽を共にした私にとって、清水教授のことを最も懐かしく思い出すのは、何よりも教育者としての姿です。彼は、多年にわたり一貫して全力を尽くし、数え切れないほどの大学院生を熱心に指導し、惜しみなく助言を与えてこられました。ビールを片手に、笑顔で誇らしげにこう語っていたことを鮮明に覚えています──「全打席全安打!私の教え子はみんな就職した」と。その言葉には、教え子たちへの深い愛情と、教育への確かな自信がにじんでいました。九州大学で受けた指導の中でも、夜遅くに行われていた「博士論文構想ゼミ」はとりわけ忘れ難い思い出の一つです。そのゼミでは頻繁に教室を飛び出し、地元の居酒屋「ふぁむ」へと場所を移して続けられました。そこで彼から「本物の参与観察」とは何か──つまり、人と酒を酌み交わしながら関わることの大切さ、そしてその楽しさ──を教わったのです。CSEAS退職後も、彼の教育への情熱は衰えることなく、関西大学政策創造学部の特任教授としてその熱意を注ぎ続けました。教授の影響は教室の枠をはるかに超えて、多くの教え子たちにも広がり続けました。

清水先生の鋭い知性と分析力、そしてときに自虐的に聞こえるユーモア──その本質は物事のすべてに両義性と重層性を認め、それゆえに自身を含むあらゆる権威を相対化して笑い飛ばせる語り口──が記憶に強く刻まれています。多くの場面で機知と洞察に富んだ言葉を紡ぎ、温かな人柄が滲む数々の逸話を語り、笑いと深い思索をもたらしてくれました。静かな土曜の午後、研究室にこもって原稿と向き合う彼のもとから、ふと廊下に流れてきたローリング・ストーンズやビートルズの旋律──あの音色が、今となっては懐かしく、胸を締めつけるような思い出として蘇ります。
彼はしばしば、自らを「どっちつかず」(Betwixt and Between)と仄めかしましたが、まさにその姿勢の中にこそ、文化や思想、人々の間に橋を架ける力があったと思います。清水先生の他界は寂しさを伴いますが、彼が築いたつながり、そして出会った人々の中に、彼の精神は今も息づいています。
謝辞
本稿執筆にあたり、貴重なご助言を賜りました速水洋子 京都大学名誉教授(日本学術振興会監事)、日下渉 東京外国語大学教授、鈴木哲也氏(京都大学学術出版会前編集長)に、心より感謝申し上げます。
参照文献
清水展. 1990.『出来事の民族誌:フィリピン・ネグリート社会の変化と持続』九州大学出版会.
───. 1991.『文化のなかの政治:フィリピン「二月革命」の物語』弘文堂出版.
───. 2003. 『噴火のこだま:ピナトゥポ・アエタの被災と新生をめぐる文化・開発・NGO』九州大学出版会.
───. 2013.『草の根グローバリゼーション:世界遺産棚田村の文化実践と生活戦略』京都大学学術出版会.
───. 2024.『アエタ 灰のなかの未来:大噴火と創造的復興の写真民族誌』京都大学学術出版会.
───. 2016. 「巻き込まれ、応答してゆく人類学:フィールドワークから民族誌へ、そしてその先の長い道の歩き方」(第11回日本文化人類学会賞受賞記念論文)『文化人類学』81(3): 391-412.
清水展・飯嶋秀治編著. 2020.『自前の思想:時代と社会に応答するフィールドワーク』京都大学学術出版会.
Hiromu Shimizu. 1989. Pinatubo Aytas: Continuity and Change. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
───. 2001. The Orphans of Pinatubo: Ayta Struggle for Existence. Manila: Solidaridad Publishing House.
───. 2019. Grassroots Globalization: Reforestation and Cultural Revitalization in the Philippine Cordilleras. Kyoto: Kyoto University Press and Transpacific Press.