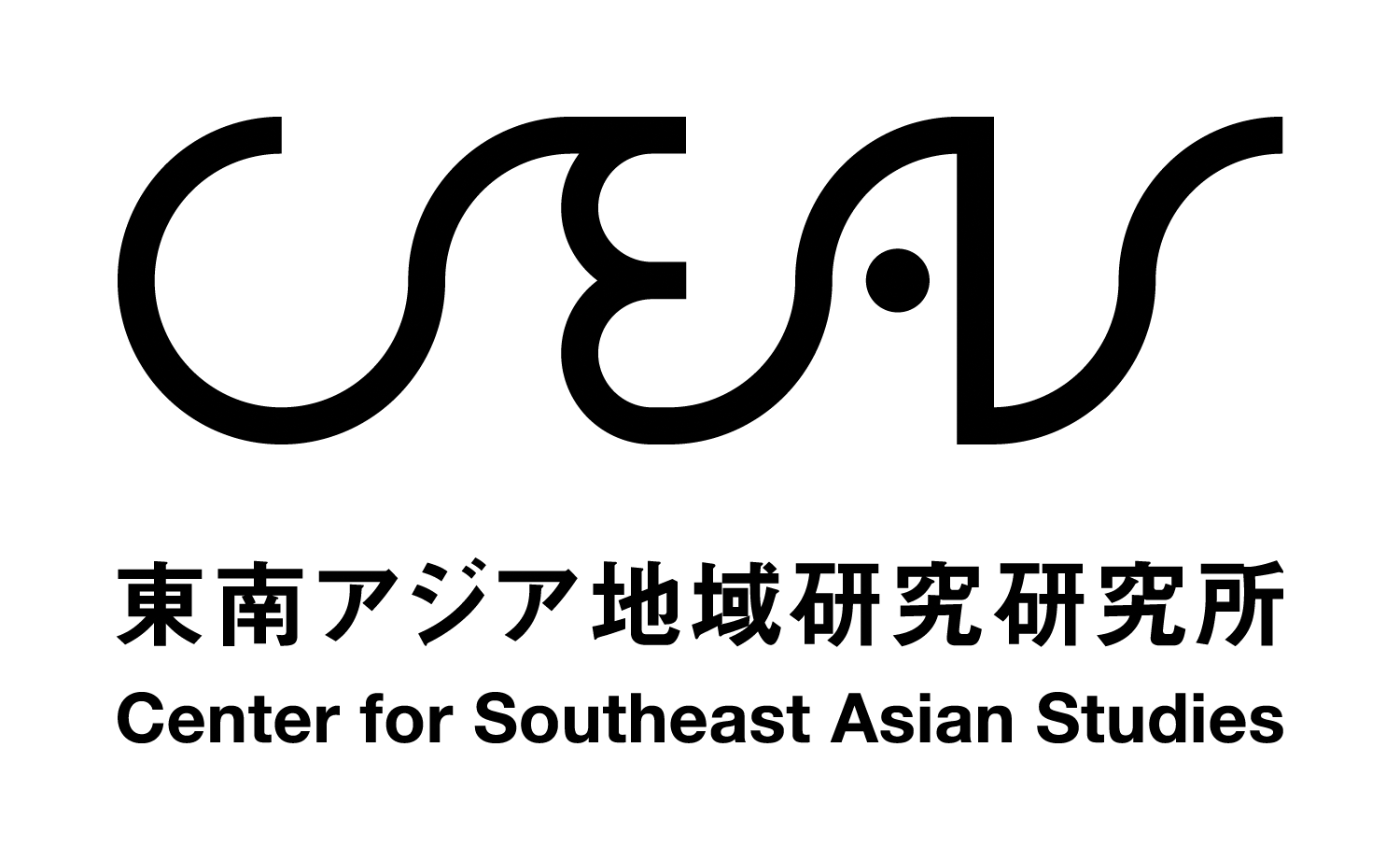(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科グローバル地域研究専攻 博士課程 /
京都大学東南アジア地域研究研究所 日本学術振興会特別研究員(DC1))
私は現在、中央アジア・ウズベキスタンの沙漠地帯(草原や山間部を含む)に暮らす人々の生活技術に着目して研究をすすめています。「絨毯織りからみるウズベク牧畜民の『伝統』と生活文化」というテーマで、これは第15回日本学術振興会育志賞の受賞対象ともなりました。構想中の博士論文では、歴史人類学的アプローチによりウズベク牧畜民の生活誌を描くことを目指しています。彼らは身の回りの環境からどのように材料を選び取り、作り、使うのか。その一連の流れを、まさにその地に生きる人々の手から手へとつながれてきた生活文化として描きたいと考えています。
ウズベク牧畜民とは?
本研究のキーワードとして定義した〈ウズベク牧畜民〉という複合語は、中央アジアについて学習したことがある方には少し違和感のある表現かもしれません。一般に、ウズベク人の定義は「テュルク系(ムスリム)定住民」とされていますし、ウズベキスタンは、シルクロードで栄えたオアシス都市や綿花栽培で有名なように、定住民文化と結びつけて連想されることが多いからです。中央アジアの歴史を理解する上でキーとなる「北の遊牧民と南の定住民」というフレームも、南側に位置するウズベキスタンの領域と定住民イメージのむすびつきをより強固なものにしてきたかもしれません。
しかし、歴史研究に登場する「遊牧ウズベク」という用語が示すように、本来「ウズベク」という名は、15~16世紀にキプチャク草原から南下した遊牧部族集団の総称として用いられたものでした。彼らとそれ以前にこの領域に到来した集団を含む遊牧部族の末裔のなかには、放牧による家畜飼育を主たる生業とし、部族意識や文化様式を保持する人々がいます。本研究が対象とするのはまさしく彼らです。なかでも私のインフォーマントは、ウズベキスタンの南部に位置するスルハンダリヤ州ボイスン郡で伝統的な絨毯織りの技術を継承する人々が中心です。複雑に入り組んだ地形を有する同国では、むしろ南部地域の方が環境面でも文化面でも遊牧的な特徴が強いとみなされているのです。つまり本研究は、一般にオアシス定住民のイメージの強いウズベキスタン(中央アジア南部)のなかでも、さらに南部地域に暮らしてきた人々の遊牧文化に光をあてるものということになります。

このように、外国人からはとらえづらい彼ら〈ウズベク牧畜民〉をどうして見つけることができたのか。それは、私の関心が「平織り絨毯をつくるテュルク系遊牧民」に常にむけられていたからです。2020年に入学した5年一貫制博士課程の前期(修士課程に相当)では、コロナ禍で海外に渡航できなかったこともあり、私は中央アジアの絨毯生産にかんするロシア語の研究蓄積を読み込むことに専念しました。それで、ウズベキスタンのオアシス都市のバザールは中央アジア絨毯の貿易拠点であり、そこから同心円状に広がる農村地帯(牧村を含む)に絨毯の生産地が点在していることを理解しました。同時に、中央アジア絨毯研究で最も参照されてきた著作[1]でさえ僅かにしか言及していない生産地があり、それがウズベキスタン南部地域で、そこでは2008年のユネスコ無形遺産登録(ボイスン郡の文化的空間)が示すように、現代でも伝統的な絨毯作りが営まれていることを知りました[2]。とはいえ、その情報は20年近く前の現地調査に基づくものでした。私は、海外渡航が可能となった2022年、東南研地図室所蔵のソ連期に軍が作成した地図のコピーを片手に、一縷の望みを抱いてボイスンを訪問しました。残念ながら一部の集落ではすでに絨毯織りの慣習は失われてしまっていましたが、可動式の水平型織り機──主要な部品はたった2枚の厚板──が今も住民の生活のなかで働いていることを確認できました。

ともに生活するなかで技術を学ぶ
絨毯作りの技術を直接教わりながら参与観察をする。それは、洋服作りの実務経験をもつ私にぴったりの調査手法であり、そのようなアプロ-チで調査に臨むことはさほどむずかしいことではないと予想していました。けれども、現実はそう甘くはありませんでした。第一に、住民が絨毯作りを実行する時にその場に居合わせられないことが幾度もあったのです。これには2つの要因がありました。1つは、外国人研究者にたいするホスト国の滞在管理システムが想像以上に厳しかったことです。調査地に行く(首都を離れる)際には必ず事前に受入研究機関長の許可を得なくてはならず、出張期間も一度に半月が上限だったのです。もう1つは、住民が絨毯作りを実行に移すタイミングを正確にはよめないことです。例えば、毛刈りをするにもヒツジの群れがいつ帰ってくるのかはわかりませんし、絨毯を織るにも急な来客や悪天候、人手不足など、先延ばしにする理由はいくらでもありました。そうすると、私が首都に帰るべき日が先にやってきて、泣く泣く去るしかなかったのです。

第二に、村の生活や経済をこわすことなく教えてもらう方法を慎重に模索していたためです。私は、基本的に自然な流れで絨毯作りの営みが生起するときを待っていました。一見絨毯作りとは関係のなさそうなことにも目を配り、作り方を知らない住民(たとえば男性や村外から嫁いだ女性)との関係性や作らない時間の過ごし方にも着目していました。それから、どのくらいの謝礼をどのようなかたちで渡すか(渡さないか)についてもよく悩みました。お金を払った上で「私のために絨毯を織ってください」、「作り方を教えてください」と頼めば、かんたんに絨毯織りは生起したことでしょう。しかし、そのような立場や関係性を私は望みませんでしたし、何より生活の営みとして絨毯作りをとらえてみたかったのです。可能な限り住民の生活に私がとけこみ、彼らのやり方に則って教えてもらうことを目指しました。村の女性たちの服装をまねて頭にスカーフを巻き、食事の準備を手伝い、同じ釜の飯を食べ……。まるで、嫁入り修行にやってきたかのようでした。

そうして、帰国の約1か月前になってようやくさまざまな条件がそろい、私は、念願の模様のある平織りの技法を2種類教えてもらうことに成功しました。やはり実際に織ってみると、見るだけでは十分に理解できなかった織りの構造はもちろん、作り手がどんなことに気を配っているのか、織り機にむかっていない間に流れる時間にはどんな意味があるのか、背景を含めた全体的な視点から絨毯作りをみつめることができたように思います。

民族誌学者のポジショニングをさぐって
これまで文化表象あるいは「民族誌を描く」という研究者の営みをめぐって、「われわれの」文化と「彼らの」文化という語法が問題視されてきたところがあります。私は、そこに2人称〈あなた〉を加えてみたいのです。時にヨソモノとして異文化の輪郭をなぞり、時にナカマとして肩を並べるように、〈あなた〉は〈われわれ〉とは異なる存在であるけれども、時空間をともにするときには〈あなた〉と〈わたし〉は〈われわれ〉にもなりうるでしょう。今後は、私が平織りの技法を習得するうちに興味を示しはじめた村の若い女性たちに、その技法を伝えていきたいと思っています。それらをよく知る先輩女性たちの協力を得て、技術継承の機会を再生産したいのです。その活動のなかで、私は研究者として観察者のポジショニングをとることも、嫁(もどき)として協働することもできるはずです。そうしてウズベキスタンの遊牧文化にかんする民族誌を描き、それを礎にテュルク系遊牧民の伝統文化の解明へと研究を展開させてゆきたいです。
注
[1] Мошкова, В. Г. 1970. Ковры народов Средней Азии конца XIX–начала XX вв (19世紀おわりから20世紀はじめの中央アジアの人々の絨毯). Ташкент: Издательство «ФАН» УзССР.
[2] Гюль, Э. 2019. Ковры Узбекистана: история, эстетика, семантика (ウズベキスタン絨毯:歴史、芸術性、意味). Ташкент: Аrt Flex.
本記事は英語でもお読みいただけます。>>
“Learning the Living Arts and Techniques of Uzbek Herders”
by Natsumi Shida