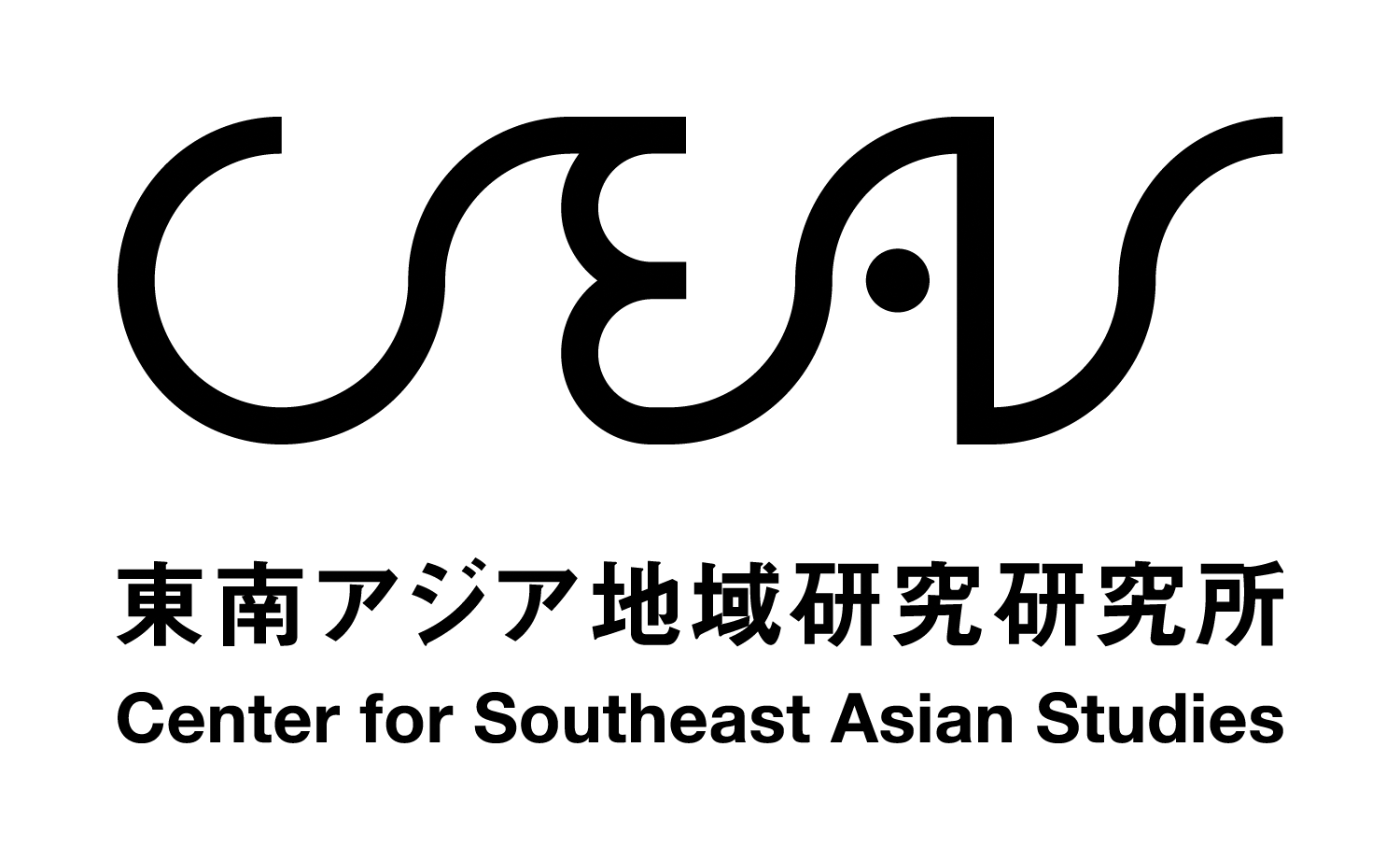土屋 喜生(東南アジア地域研究、近現代史)
2025年5月、ノースカロライナ大学出版局よりCold War Asia: Unlearning Narratives, Making New Histories(『冷戦のアジア:歴史の語り直しと再構築』、以下CWAと略記する)が刊行されました。本書は、シンガポール国立大学(NUS)歴史学科で教える益田肇准教授をプロジェクトリーダーとして、同大学を拠点に進められた国際共同研究「冷戦再考:アジアの草の根の経験」(原題Reconceptualizing the Cold War: On-the-ground Experiences in Asia)の成果であり、益田氏が編者を務めています。本書の全体像については編者による紹介記事(益田 2025)、プロジェクト初期に実施されたワークショップについては拙報告書(Tsuchiya 2019)があります。それらとともに、NUSで学び益田の弟子を自認する私の立場から、益田肇という人物と我々の研究について紹介した以下の文章をご覧いただきたいと思います。
NUSでの出会い:「歴史の中の紛争、紛争の中の歴史」
NUS東南アジア研究科での修士課程も終わりに近づいた2012年、進路に迷っていた私は、フィリピン史家で同年にNUSを退職したレイナルド・イレート教授からこう勧められました。「君は哲学が得意だからいい歴史家になるだろう」。
イレート教授の言葉にそそのかされ、2013年8月から歴史学科博士課程に転入した私は、移動直後に学科長にこう言われました。「君は日本人だね。プロとして生き残りたいなら、自国の歴史くらい教えられるようにならないと。だから益田肇の近現代日本史の授業を手伝ってほしい。彼も日本人で、10年後には学界のスーパースターになるよ」。
NUSでは奨学金を受ける大学院生に授業のアシスタントを務める義務を課しており、この日に私は初めて益田肇という名前を知ります。益田は元々毎日新聞の記者で、そこからアメリカに渡り、コーネル大学で歴史学の博士号を取得しました。私が出会ったとき、彼はNUSに着任して2年目、ほぼ無名の助教授でした。そして私は彼の講義「近現代日本史:歴史の中の紛争、紛争の中の歴史」のアシスタントを務めることになります。
この講義名には、のちにCWAへとつながる益田の一貫した視点──「人々のなかの冷戦」や「社会戦争(social warfare)」──がすでに表れていました。米騒動や幕末動乱期の不安と希望、戦時下の女性の社会進出とその後の逆コース期のリストラ、バブル経済期80年代後半にフリーターという言葉に込められた希望と不安まで、時代を横断して社会内部の葛藤に光が当てられ、単なる出来事の羅列ではなく、社会の変化に対して人びとが抱いた憧れや期待、嫉妬や恐怖といった感情がたどられました。義務教育で学んだ他人事のような日本史とはまるで異なる、どこか親しみのわく授業で、私自身も益田のアシスタントとして教えることに充実感を覚えていました。そして後に私は、イレート教授の博論の指導教授だったO. W. ウォルターズが「君は数学が得意だから立派な歴史家になるだろう」と言って工学の道を歩んでいたイレートを歴史学へと向かわせたことを知ります。
「人々のなかの冷戦」
私が本当の意味で益田肇を「学界のスーパースター」になるべき人物と認識したのは、2015年、大学院で彼が担当していた「冷戦再考」という授業を聴講したときでした。NUSの授業形式はシンプルで厳しく、毎週英語の専門書を一冊丸ごと読み込み、書評を提出します。2つか3つの授業を履修すれば、学期中に30〜45冊という読書量になります。
その学期の授業では、当時定説となっていたジョン・ルイス・ギャディスの米ソ冷戦史、デタント政策を東西両陣営による社会運動の制御策と解釈したジェレミー・スリの研究、地球規模の資本主義と共産主義の対立として冷戦を再解釈したオッド・アルネ・ウェスタッドの研究、ベトナムや朝鮮半島の経験を踏まえ「冷たくない冷戦」があったと主張したクォン・ホニクの研究(ギャディス 2004;Suri 2005;ウェスタッド 2010;Kwon 2010)などがテキストとなりました。いずれも重要な研究で、しかもそれらは、冷戦の中心には米ソ対立があり、その延長、あるいはコインの裏側として第三世界の参加や社会運動、ベトナムや朝鮮の「熱戦」等があるという見方を共通の前提としていました。
院生としてこれらの研究書に取り組んでいた最中に、益田肇の初の英語単著Cold War Crucible: The Korean Conflict and the Post War Worldが出版されました(同書の日本語翻訳改定版として『人びとのなかの冷戦世界:想像が現実となるとき』が2021年に岩波書店より刊行)。本書を初めて読み終えたときの印象を端的に語ることは難しいですが、一言で言えば衝撃を受けました。なぜなら、我々が一学期をかけて読んできたすべてのテキストの前提となっている「東西対立としての冷戦」という大きな物語をぶち壊し、実は非常に似通っていた両陣営の動態を同じ尺度で眺めるというまったく新しい歴史だったからです。
そして問わずにいられなかったのは、「一体どうやってこの本を書いたのか?」ということでした。本書に凝縮されている多種多様な史料、世界中に散在する無名の人々の声を伝える史料をどのように見つけ、学部生でも十分に読める叙述形式へとまとめたのか。当時のNUSでは天才的な研究者や影響力のある思想家など様々な人物と出会うことができましたが、Cold War Crucibleを読んだとき、それまでに感じたことのない、「私にもこのスケールの本が書けるだろうか。いや、無理そうだ」という絶望と感動とが入り混じった複雑な気持ちになりました。
今からたった10年前の2015年当時の冷戦研究では、「誰が起こしたのか」「誰の責任か」という問いが当たり前で、そこに疑義を挟む人はわずかでした。そのような状況に対して「そもそも冷戦とは何だったのか」と問い、世界各国50以上の文書館で集めた史料を証拠として使いつつ、「冷戦は現実になった想像だ。それは様々な国の多くの人々にとって利用価値があるファンタジーだったから再利用されつづけたのだ」と断言する益田のラディカルな見方に、多くのベテラン歴史家たちは戸惑いを隠しませんでした。私たち大学院生の間でも、その方法論のすごさや論旨の斬新さに圧倒されつつ、超大国や権力者中心的な見方を続ける者、困惑する者、そして私のように冷戦研究の新時代の幕開けを感じて興奮する者など、様々な反応を引き起こしました。そして彼からもっと学べると考えた私は、(東)ティモールに関するグローバルな知識生産の歴史を研究した博士論文での指導や彼の「冷戦再考」プロジェクトでのポスドクを通して、段々と彼の弟子に成って行きました(Tsuchiya 2024)。
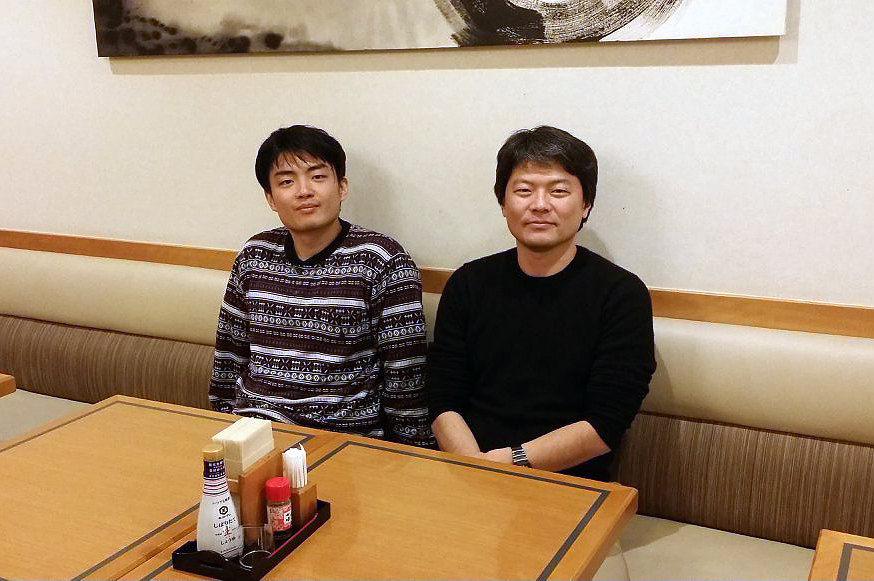
冷戦再考プロジェクト
CWAを生んだ冷戦再考プロジェクトは、「そもそも冷戦とは何だったのか」という益田の問題意識を発展させ、「アジアの一般市民にとっての冷戦とは一体何だったのか」という問いに対し、各国で収集したオーラルヒストリーを利用することによって帰納法的に答えようとするものでした。しかし、80人以上の研究者が参加したこのプロジェクトでは、最初から全員が益田の問題意識に賛同していたわけではありません。したがってCWAでも、一般市民にとっての冷戦が多様な観点から検討されており、2つの陣営による国際紛争、現地の文脈にそって翻訳された国際的対立、あるいはローカルな問題を処理するために権力者の言葉を借りたもの、さらには私が主張したように「2つの陣営による対立としてイメージされた多数のローカルな紛争」など、論者により様々な提示がなされています。
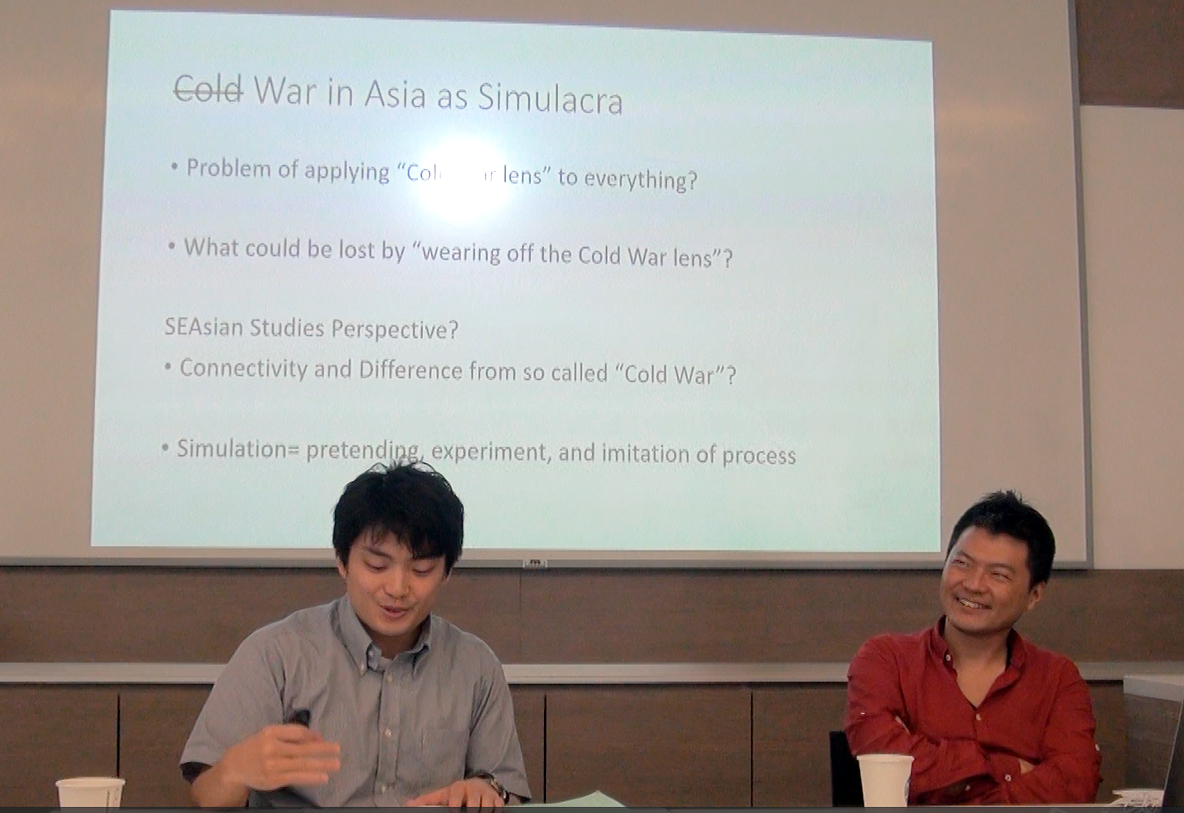
また益田は、旧来の冷戦観を「冷戦を天気(所与の環境)のようなものと見なしている」と批判し、冷戦の論理を利用し続けた一般市民が現実を作り出すある種の権力を持っていたと想定しました。これに対し、1965年のインドネシア軍による「共産主義者」の虐殺や、米軍による空爆に苦しんだラオスやベトナムの人々を研究する立場から、「冷戦はまぎれもなく天気のようなものであり、強大な権力を持つ少数者が大多数の一般市民に強いたもの」と反論する研究者もいました。これはインドネシアや米国の権力者たちの戦争責任を追及しようとする現在の人権派の論調とつながっています。
しかし、冷戦再考プロジェクトの核心には、権力者を権力者たらしめているのは多くを語らない多数の支持者たちであり、権力者の行為とともに、一般市民の経験・感情・思想を理解しなければならないという問題意識がありました。それゆえ、CWAに収録されている全ての論考は、冷戦の被害者とも加害者ともなりえたアジアの一般市民たちを理解しようとする点において共通の目的を持っています。さらに言えば、このような主張には、益田や私が日本人であることが関わっているかもしれません。私たちは、「日本を第二次世界大戦に向かわせたのは、戦争する国家に拍手を送り、兵隊やその家族となった一般大衆ではなかったか」という問いを共有していました。[1]

そして、益田は地域研究畑の研究者や学生たちに対しては、以下の問いを度々投げかけてきました。
・地域研究者は、既存の「大きな物語」にどう挑戦し、代わりとなる物語を提示できるのか?
・世界史やグローバルヒストリーが「大きな物語」を提供し、地域研究者はその影響を調べるだけ──そうした知的分業の構造をどう乗り越えることができるのか?
冷戦再考プロジェクトは、アジア各地の研究者たちがフィールドの声と「冷戦」という概念のつながりを研究することで、グローバルに共有されていた何かを見つけようとするグローバルヒストリーでもありました。それは単に草の根の経験によって既存の冷戦史観を補足するだけではなく、世界認識の枠組みや歴史叙述そのものの再構築を地域研究に関わる人々に対して要求しています。「米ソ対立」や「長い平和」、「大国やグローバルサウスの指導者による外交ゲーム」といった従来の語りで綴じるのではなく、CWAはこう問うことで冷戦研究を新しい方向へと開きます。アジアの一般の人々にとって、「冷戦」とは一体何だったのか。フィールドの経験や声に耳を傾ける際、私たちはどこまでグローバルな事象を語ることができるのでしょうか。
注
[1] この問いへの答えとしては、益田肇『人びとの社会戦争:日本はなぜ戦争への道を歩んだのか』(岩波書店)が2025年9月5日に刊行された。
参考文献
ギャディス、ジョン・ルイス. 2004. 『歴史としての冷戦:力と平和の追求』赤木完爾・齊藤祐介訳、慶應義塾大学出版会.
Kwon, Heonik. 2010. The Other Cold War. Columbia University Press.
益田肇. 2025. Cold War Asia: Unlearning Narratives, Making New Histories 編著者からの紹介、京都大学東南アジア地域研究研究所ニュース(https://kyoto.cseas.kyoto-u.ac.jp/publication/cold-war-asia/、2025年5月28日アクセス)
───. 2021. 『人びとのなかの冷戦世界:想像が現実となるとき』岩波書店.
Suri, Jeremi. 2005. Power and Protest: Global Revolution and the Rise of Détente. Harvard University Press.
Tsuchiya, Kisho. 2019. Workshop Report: Reconceptualizing the Cold War: On-the-ground Experience in Asia 21-22 May and 22-23 June 2019. H-Diplo.
────. 2024. Emplacing East Timor: Regime Change and Knowledge Production, 1860-2010. University of Hawai‘i Press.
ウェスタッド、O・A. 2010. 『グローバル冷戦史:第三世界への介入と現代世界の形成』佐々木雄太監訳、小川浩之・益田実・三須拓也・三宅康之・山本健訳、名古屋大学出版会.