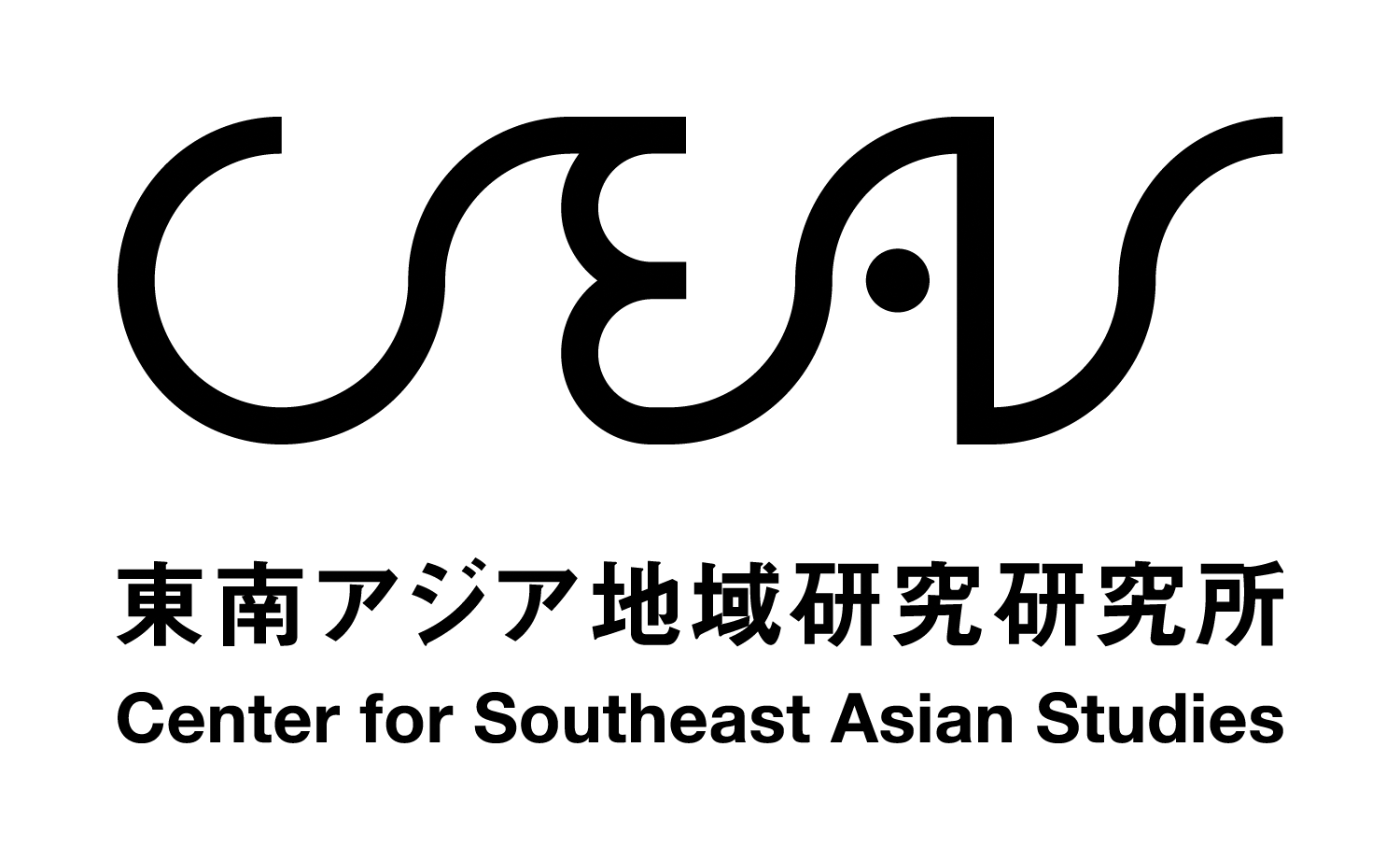山本 博之(地域研究、メディア研究)
私は幼少期からウルトラマン(および他のウルトラヒーローたち)が好きだった。ふだん地球人の姿をしているウルトラヒーローが地球の侵略や破壊を企てる宇宙人に「同じ宇宙人」「宇宙人どうし」と言っているのを見て、地球人は宇宙人ではないのかと不思議な感じがした。
大学生のときに『ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義』という本に出合った。『ゴジラ』や『宇宙戦艦ヤマト』といった日本の特撮・アニメ作品の設定は国際政治のリアリズムの立場から見て合理的でないと指摘する本で、テレビの世界を現実と重ねて捉えるという発想がなかった私にはとても新鮮に感じられた。ウルトラヒーローも分析の対象で、ウルトラヒーローが自らの生命を危機にさらしてでも自分と何の縁もない地球人を守ろうとすることについて、米国の軍事力で守られていることを当然のことと考える戦後日本の意識が重なっていると批判して、日本の政治的・軍事的自立の必要性を訴えた。
誰もが名前を聞いたことがあるような作品にはそれを生み出した国・地域や時代の意識が反映されており、作品を読み解くことで社会通念を捉えるという手法には学ぶところが多いと感じた。その一方で、他者から助けを受けることを弱さと見て、助けが必要でなくなることを望ましいとする著者の考え方には違和感を覚えた。
ただし同書は私のその後の進路に大きく影響を与えた。なぜ外国人が自分たちを助けてくれると思って疑わないのかという問いは、地域研究を専門とした私がその後も自問し続けることになった。なぜ外国人である私がその地域の研究をするのか。私の研究は対象地域にどのような積極的な意味を持つのか。
そのような思いを抱きながら私が長期滞在したマレーシアのサバ州では、私は外国人でありながら仲間として受け入れられているという意識を強く抱いた。マレーシアは民族間の境界が明確であるように見えるが、その仕組みは舞台裏で外来者や混血者が調整役になることで機能してきたという側面に私の関心が向いた。そこから、プラナカンと呼ばれる外来者・混血者に着目してマレーシアの現代史を捉え直すとともに、多彩な外来文化がマレーシアで出合って新たな価値が生まれ、プラナカンを通じて世界に発信される側面にも目を向けるようになった。
2022年に公開されたリブート映画『シン・ウルトラマン』では、初代ウルトラヒーローであるウルトラマンと地球人の最初の出会いが語り直された。地球人の姿になったウルトラマンが地球人を理解するために図書館で『野生の思考』を借りて読む場面があった。地球人は宇宙規模で見れば未開社会なのだろうが、その習慣や制度にも宇宙文明に通じる普遍性があるとウルトラマンは考えたのだろうか。
最初の1冊として悪くない選択だろうが、もし私に機会が与えられたならば、ウルトラマンには次に『想像の共同体』を勧めただろう。人文社会系を中心に多くの研究に今日でも影響を与え続けている同書は、人間は言葉によるコミュニケーションのために限定された範囲で運命共同体を想像して、そのため異質な他者を排斥するという議論だと誤解されることも多いが、同書の底流には自立のための戦いに臨む人どうしは境界なく連帯できるという信念がある。これが宇宙規模でも普遍性がある議論なのか、宇宙人と地球人のプラナカン的な存在であるウルトラヒーローたちと議論してみたい。
(イラスト:Atelier Epocha(アトリエ エポカ))
本原稿は英語でもお読みいただけます。>>
“Ultraman and Imagined Communities:
Heroes and the Imagination Beyond Borders”
by Hiroyuki Yamamoto