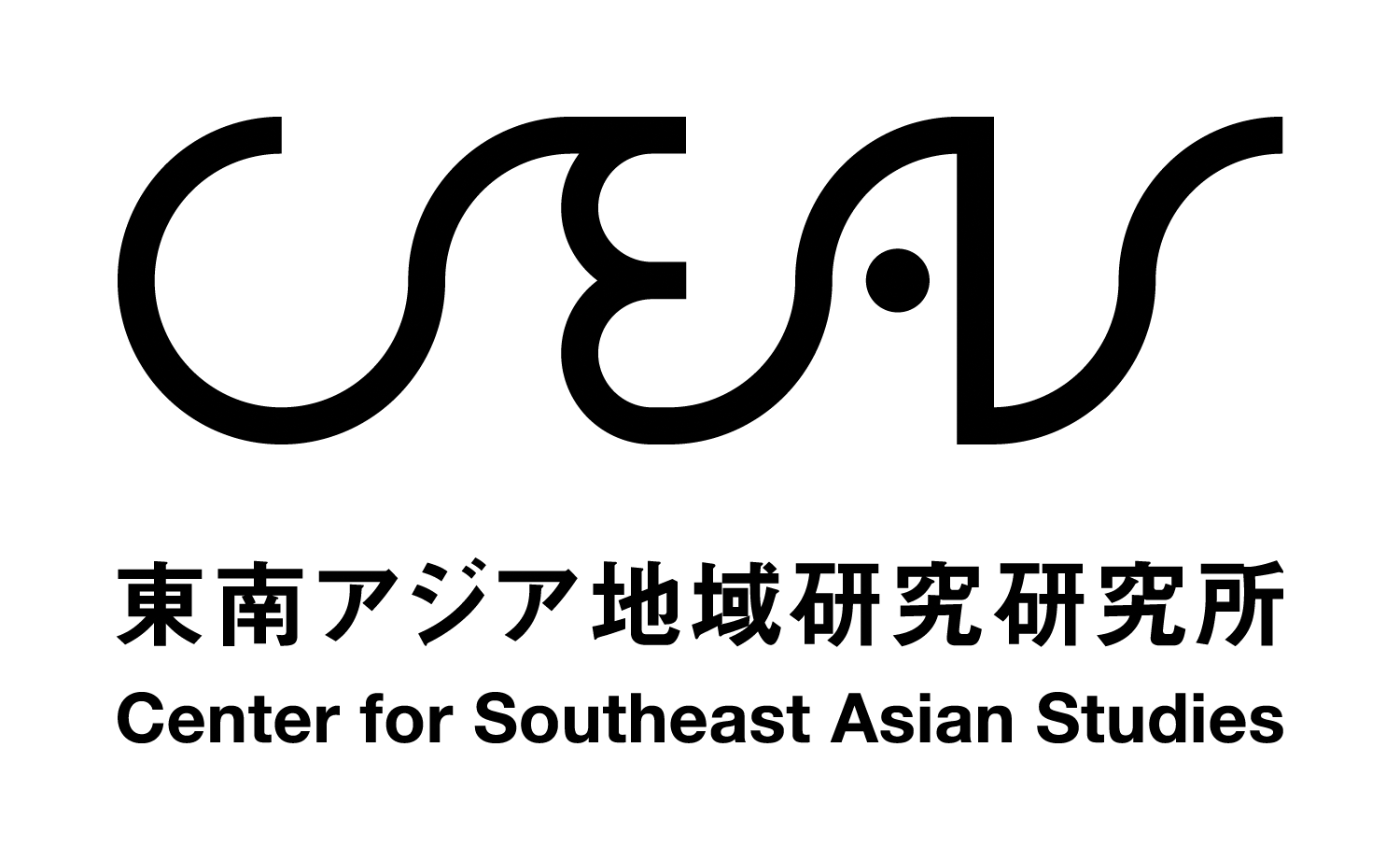速水洋子教授 退職記念インタビュー
速水洋子氏は京都大学東南アジア地域研究研究所・教授(2024年3月退職)。1992年にブラウン大学(アメリカ)で人類学博士号を取得。1996年から当時の東南アジア研究センターに助手として着任した。タイ北部山地からミャンマーの広域に居住する少数民族カレンの宗教と社会の動態について研究し、その成果として英文叢書Between Hills and Plains: Power and Practice in Socio-Religious Dynamics among Karen (Kyoto University Press and Trans Pacific Press, 2004) などを出版。また同地域にてジェンダー、家族、民族をテーマに調査し、『差異とつながりの民族誌──北タイ山地カレン社会の民族とジェンダー』(世界思想社、2009年)などを出版。東南アジアにおける家族やケアについての共同研究も実施してきた。現在は山地のみならず北部タイの中心都市チェンマイを中心に、高齢者とケアをテーマに研究している。2018年4月~2022年3月京都大学東南アジア地域研究研究所長。
1. 研究について
──研究者を目指すようになったきっかけを教えてください。高校時代、大学時代はどんなことに関心をお持ちでしたか?
高校生の頃は、海外に出かけるような仕事がしたいという漠然とした思いがあるくらいでしたが、大学入学当初から文化人類学に関心がありました。文化人類学教室では先輩方が意欲的に読書会や研究会をしていて、刺激はたくさんありました。そんな中で私はあまり真面目な学生ではなかったのですが、学部2年目の後半から始まったフィールド調査実習が勉強意欲に火をつけてくれました。
高校・大学と部活で山に登っていました。山頂の気持ちよさもありますが、山深く尾根伝いに何日も歩いてから、下山するにつれて川の音が大きくなり人里の気配が始まる、その感じが好きでした。調査をするならそんな山麓の村でしたい、また当時から宗教と身体的な表現に関心を持っていて、神楽など芸能を含んだ祭りの調査をしたいと思っていたこともあり、調査は南アルプスの南麓、下伊那地方の霜月まつりに決めました。結局3度ほど滞在させていただいたうえで体験した極寒の山村で繰り広げられた祭りは圧巻でした。この体験とその後これを卒業論文にまとめるプロセスが、私に文化人類学の面白さを教えてくれました。様々な儀礼をめぐる理論的な枠組を検討しながら、自分で経験した村の日常、学んだ村の歴史と祭りの時空との関係を理解する楽しさを味わいました。
──大学院ではどのような影響を受けたでしょうか。
大学院に入学した時(1981年アメリカ・ブラウン大学)、宗教実践における身体性やパフォーマンスといったことに関心がありました。でも入学当初は、すぐに自分の関心にフォーカスするよりも、まずは広く学ぶことを求められました。学説史や社会理論、考古学や言語人類学といった人類学のなかでも多分野から構成されるコア・コースを履修しました。また自身の調査に向けて口述試験とプロポーザルの用意をするなかで、多くの文献を読まされました。結構大変でしたが、院生同士の日常のやりとりがこうした経験を楽しく刺激的なものにしてくれました。ジャワ村落調査に基づいて民族誌を書かれたロバート・ジェイ教授と言語人類学的な関心から芸能やパフォーマンスを研究されて自らもオペラ歌手として舞台にも立たれたウィリアム・ビーマン先生に指導いただき、また当時の人類学でもジェンダー研究に注目が集まっていて、80年代からジェンダー研究を牽引されたルイーズ・ランフィア先生やリーナ・フルゼッティ先生など、個性豊かな先生方から学ぶ機会を得ました。そんななかで問題意識を形成していきました。今から考えるとこの大学院の最初の3年ほどの学びはその後の調査や研究に大きく影響しました。
調査対象を絞るうえで最も影響を受けたのは、奇しくもかつて東南研で助手を務められた飯島茂先生の『カレン族の社会文化変容』でした。そこでは国家統合の道を歩むタイの現状をふまえて変容する少数民族世界が動態的に描かれていました。中でも祖霊祭祀の儀礼への言及と、カレン1にはキリスト教徒が多いという事実に興味を持ちました。ひっそりと行われるという祖霊祭祀の儀礼とはどんなもので、キリスト教徒になってこの儀礼を放棄するのだとしたらなぜそのような選択をするのか、タイという仏教徒が圧倒的マジョリティの国で少数民族がキリスト教に改宗するとはどういうことなのか、と関心を掻き立てられました。
博士論文に向けた調査のためにタイに到着したのは1987年のことでした。各地歩き回った末に、チェンマイの町から北西に150キロのカレンの村を調査地と決めました。松林と広葉樹林が混在する標高千メートルほどの美しい高原地帯で、住込みを決めた村は人口の4割ほどがキリスト教徒で、それ以外は祖霊祭祀を行っていました。その後の研究の内容は時期的に重なりながら大きく三つくらいのテーマに分けられるかと思います。
カレンの宗教実践:社会の動態と力の源泉への希求
──カレンの村を調査地と決められてから、さまざまな研究課題に携わって来られました。それぞれのテーマはどのように生まれてきたのでしょうか。まず、カレンの宗教と社会の動態に関する研究についてご紹介いただけませんか。
当初の調査は先ほど述べた関心から、少数民族カレンがタイ国家の周縁においてどのように宗教実践を選び、それは少数民族としての位置づけとどのように関わるのかを問うものでした2。祖霊祭祀の儀礼は家族の安寧を守るために実施するのですが、様々な規則に則って正しく遂行することが求められます。たかが儀礼と言うなかれ、居住形態、家畜飼育、現金収入源、社会関係などある意味で生活のすべてがこの儀礼をめぐって規制を受けるのです。そしてたとえば儀礼参加者の誰かが突然健康を害するようなことがあると、あれこれとこの儀礼の作法を誤ったことに原因を求めるのです。よそ目には作法通りに供犠の家畜を共食するというごく地味な儀礼ですが何とも厄介なのです。興味深いのは、徹底的にこれを守ろうとする一方で、何か他に説得力のあるやり方があれば、まるごと乗り換えることもしばしばみられることでした。乗り換えを可能にしてくれるのは、祖霊の報復から守ってくれる何らかの力に寄り添うことです。言わば代々の慣習を生真面目に守り続ける伝統志向と、その生活を放棄して別の力を「よる辺」として新しい生活を選ぶ革新志向という二つの方向性が共存しているのです。この革新の手段になる力の源泉は、キリスト教への改宗、僧侶による祖霊追放の儀礼、クーバと呼ばれる仏教聖者への帰依、そして大小様々な宗教運動に参加すること等、私の調査地だけでも複数ありました。さらに同じカレンの居住する地域と歴史を広く見渡せば、実に様々なものがあり、宗教運動に至っては18世紀後半から既にビルマ側で報告されています。
故チャールズ・カイズやジェームズ・スコットは、カレンやゾミアの山地少数民族がキリスト教に改宗するのは、低地国家を担うマジョリティ仏教徒との差異化を図るためであると論じています。民族の差異を宗教によってさらに太く線引きするというのはわかりやすい話です。しかし本当に彼ら自身がこのような目的意識をもって宗教を選択していたのでしょうか?たしかに結果論としてキリスト教化することで平地仏教徒と差異化され、その筋書きはビルマでは民族闘争の中で政治化され、リアリティを持つようになります。しかし様々な宗教の選択肢から時には仏教、時には宗教運動やキリスト教を選んできた調査地の人々からは、そのような意識は読み取れませんでした。むしろ、その時アクセスできる有効な「よる辺」に従って新しい生活を送ることが最優先なのだと理解しました。
では、こうした「よる辺」探しによるキリスト教への改宗、宗教運動や聖者への帰依は、なぜこのように広域にしかも頻繁に起きてきたのでしょうか?カレンの事例に限らず類似のこうした運動について、研究者は「剥奪された弱者」の革命として低地国家権力やマジョリティとの関係や、近代化と「文明との接触」などによって説明してきました。私にとってこの問いへの答えは広域のカレン地域で調査を重ねるにつれて少しずつわかってきたように思います。あちこちで出会う聖者や宗教運動の指導者が点と点をつなぐように人々の語りのなかでつながっていくにつれ、まさにこうしてつながる伝承の系譜が人々に語り継がれ、広がりのなかで少しずつずれや違いはありつつ紡がれ続けてきた語りこそがその答えのように思えます。このような語りが共有されているからこそ人々は系譜をつぐ次の指導者・聖者を求めるのです。彼らは植民地化、民族闘争と近代国家統合、グローバル化などの大きな動きのなかで翻弄されつつ霊的・物質的をひっくるめてより良い生活を求めるなかで自分たちの「よる辺」を様々に見出して、国境線を越え、歴史の折々を通じて、周囲の諸民族のものも取り入れつつ宗教実践を展開してきました。私のカレン宗教の研究は、次第に地域的・時間的に対象を広げ、こうした「伝統型」と「革新型」が様々な形で展開する様子を追っていきました。
その中でも特に二つの流れをたどりました。その一つが、カレン・キリスト教史です。1830年代に始まったビルマにおけるバプテスト宣教は、特にカレンへの宣教の目覚ましい成功により、宣教史に刻まれる偉業とされています3。宣教師の目から見ればカレンを改宗させることで野蛮な民族を文明化する営みだったこの布教の成功は、カレンを物語の主語にしてみれば革新志向のなかで神や聖書に力の源泉を見出した結果であり、宣教師はその物語の舞台で役目を果たしていたともいえます。今一つは、クーバと呼ばれる仏教聖者たちへのカレンの集団帰依です4。村も従来の生活も捨ててカリスマ的な指導者の系譜を継承した仏教聖者のもとに参集し安心を得て生活を営む、あるいは民族闘争のなかでカレン難民が聖者による辺を求めてきた過程を追いました。
以上、「そんな大事な祖霊儀礼なのにやめるってどういうこと?」という疑問から始まって、国境の両側でカレンのキリスト教や仏教、宗教運動など豊かな宗教世界を追いかけつつ、近代国家や「中心」に視点を置いた研究とは異なる少数民族の側から宗教動態を追い、宗教とは何かを考えてきました。
差異とつながり、そして家族
──先生は女性とジェンダー、家族に関するご研究も深めておられます。
これもカレンが始まりでした。お話しましたように、大学院でジェンダーについて学ぶ機会がありました。それとともに、調査地では私は背格好も見た目も彼らと変わらないので、村にいればカレンの女性たちに似た扱いを受けることも多く、彼女たちと過ごす時間が長かったことから、結婚・出産・育児から、老いて死するまで女性の経験に関心を持ちました。子を成し母となる限りにおいてカレン女性の生活は母方居住のサザエさん生活で、女性親族に囲まれて大変なのは男性のようでもありました。しかし女性が一歩村から出て、あるいは村外からくる平地タイ族の男性の目にさらされることには警戒感が強く、そうした場面でジェンダーと民族が同時に意識されることを目の当たりにしました。カレン女性は北タイのタイ族男性にとって嫁として望ましく、また性的な眼差しで見られる対象でもあるのです。カレン女性は従順で、よく働き、貧しさに文句も言わず、高額な結納金も不要といわれていました。しかし一度タイ族男性と暮らして捨てられた女性は、二度とまともな結婚はできないとして、親たちはそのようになる前に、早く相応しいカレンの男性とめあわせようとする傾向がみられました。当時はチェンマイの町で山地出身の貧しい女性たちが多く売春に携わった時期で、タイ人に捨てられて身を持ち崩すカレン女性という定型化した話をよく耳にしました。一方、行政は何か地元の行事があると、「山地の女性は民族衣装を着てくるように」求めました。このように民族の接するところでジェンダーがその力関係を如実に表し、カレンという少数民族であることをより一層際立たせるのです。そこでジェンダーの差異と、民族の差異が交差するところで力関係が強化され、女性がそれを弱者としてどのように経験するかを論じました5。ただし、彼女たちはたとえば北タイの男性との結婚を通じて新しいつながりを形成していくことにもなります。彼らの事例から、差異は必ず断絶をもたらすのではなく、つながりの契機にもなるということも強調したかったのです。
村での日常生活をみていれば当然、家族は一つの重要な単位のように思われる一方で、カレン語には「家族」にあたる言葉がありません。東南アジアの家族といえば、東南研の大先輩である坪内良博先生、立本成文先生が提示した「家族圏」概念があります。私たちがよく知る近代家族とは異なる、開かれた「圏」としての家族で、これはカレンの事例を考えるにも有効でした。一方、近代国家建設にあたっては各国の指導者、特に開発独裁の指導者たちは「家族」言説をふんだんに利用していました。いずれにせよ産業化が少しずつ進むなかで実態としての家族の形も変わっているにもかかわらず、東南アジアにおける家族そのものに関する実証的な研究はあまりなされていません。こうしたことから、拠点大学交流事業の場を借りて、小泉順子先生と一緒に東南アジアにおける家族とその変容について、また家族イデオロギーとその歴史について、日本および同地域各国の研究者と共同研究をしました6。各地からの文書や実態に基づく皆さんの研究から、近代化のなかでどのように家族が変貌し、どのように家族の絆が維持・変容を遂げているのかが少しずつ見えてきました。
東南アジアにおける高齢期の生き方とケア
──最近は、東南アジアにおけるケアと高齢化というテーマでご研究を進めておられますね。
GCOEプロジェクト「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」(2007–2011年度)に参加した折に、ケアというテーマに取組み、私自身はまずカレンの調査村で「ケア」を考えることから始めました。ケアとは関係性だとすると、村でどのようにケアが通常の社会関係のなかに埋め込まれているのかを見ながら、彼らがケアをどのように語るか、耳を澄ませました。ケア論は基本的に先進産業社会で盛んに論じられていますが、東南アジアではどのように語られ実践されているのかを、その後の科研プロジェクト「東南アジアにおけるケアの社会基盤」へと続けて共同研究しました7。
その後、より喫緊にタイで高齢化とケアを論ずるならば、山を下りて平地社会の研究が必須であると考え、平地タイ社会で実地調査をすることにしました。まず、高齢化が進行するタイで、家族やコミュニティによるケアがどのように変動しているか、実態として高齢者ケアがタイ社会の変動を背景に、どのように担われているかを検証することにしました。チェンマイ市内や郊外で、高齢者をめぐる活動の活発な地域、NGOのメンバーが訪問する家庭、当時雨後の筍のように開設されつつあった小規模の高齢者施設、寺院、介護士学校、高齢者学校、行政の担当者やボランティアなど、様々な場面でケアがどのように実践されているか調査しました。経済発展と社会変化のスピードを優に飛び越えて高齢化が進展するなかで、どのようにケアが実践され語られるか、それを見ることはタイにおける家族や地域社会の変動を見ることにもつながると考えました。
もう一つ、思いがけない研究の方向性が加わることになったのは、都市の高齢者施設での聞き取り調査によるものでした。毎日のように施設に通って、彼らがここに入居するようになった経緯とともに語る人生や、日々の過ごし方をつぶさに観察し聞き取る調査から、多くのことを学びました。私は歴史学者ではないので彼らの語りを聞くことは何か史実と突き合わせてその整合性や正確さを確認するものではありません。語りのなかで彼らが今、この施設から自身の人生をどう振り返り、どう高齢期をここでの生活と折り合いをつけているのかを聞き取ることが目的でした。高齢期と終末期の迎え方は、個としての人、そして人と人のつながりをどう考えるかという価値観に根付いており、それぞれの工夫があることを学びました8。
──実に幅広く様々な課題に取り組んでこられましたが、これらのテーマはどのような関係にあるのでしょうか。またそれらを貫いてどのような問いをお持ちでしょうか。
ばらばらに見える様々なテーマは、私にとってはいずれもカレンの村の体験から始まっています。山地にある周縁世界と近代との接点が広がり、国家及び市場に包摂されて行く山地の変容を宗教を皮切りに、市民権、森林権、観光、家族、民族などを拾いながらみてきたといえるかもしれません。ただし、ここまで、「カレン」と当たり前の単一カテゴリーのように呼んできました。村にいるとあまり問うこともないこのカテゴリーは広域に調査を広げると、同じカレンとして、共通性はありつつ語彙や発音の違い、習慣や衣装の違いも少しずつ見られます。圧倒的に違うのは、タイとビルマそれぞれの国家における布置とその歴史的変遷ですが、カレンは民族闘争の主体であったり、森林権の主張の主体であったり、民族集団として主張することもあります。では、カレンとは誰なのか、民族はどのように語られその外延はどこにあるのか。歴史を通じて変化して今があり、研究者もそのプロセスに関与していることを含めて考えてきました9。
私たち研究者は当事者の日常から遠い枠組や語りを持ち込みます。そこで語られる大きな筋書や概念が当事者、特に弱者の視点からはどれほど意味があるのか問いなおすことで、見えなかったものが見えてくること、そのうえでよりマクロな制度やプロセス、地域的広がりとそれらの動態のなかで理解することも重要と思います。調査して語りを紡ぐ研究者として自分自身がその力関係にどのように加わっているか自覚に努めつつ。
2. 調査地とのつながり
──タイとの出会い、カレン人との出会いを教えてください。そして調査地の人の語りで一番心に残っている言葉や折に触れて思い出す言葉があれば教えてください。
この村を初めて訪れてから既に36年になります。言わば私の人類学研究のホームベースにさせてもらっていて、新しいテーマについて考える時には、まずこの村でどうなっていたかと思い巡らせて、とりあえず村へ行って話を聞いてみることから始めます。日本にいても折にふれて、彼らだったらこういうときどうするだろう、と考えます。当時の子供たちはもう思春期の子供や孫を持つ年齢に達し、お世話になった大人たちは老境に達しました。今年の2月には、「孫世代」の結婚式で村を訪れる予定にしています。花嫁になる人は、チェンマイの大学で中国語を学び、中国に留学した経験があり、今は北タイの私立校で中国語を教えています。いずれ日本に遊びに来たいと言っています。調査を始めた頃、女性が村から出ることに伴うハードルが高かったことを考えると、隔世の感があり、いろいろな意味で日本との距離も縮まっています。そしていつも村を去る時になると、たぶん社交辞令か半分くらい本気か「今度来るときは、もっと長居しなさい。村に一軒家を建ててあげるから」と言ってくれます。
──調査中に、調査に夢中になって日本のご家族に連絡するのを忘れ、北タイ全土に向けた放送で呼び出されたという印象的なエピソードがあります。そのときのことについてもう少し教えていただけませんか。
今でこそ村の多くの皆さんが携帯電話を持っていて、町にいる家族とも常にコンタクトを取っていますが、最初の調査当時は電気も水道も電話もありませんでした。調査中日本の家族には月に一度山を下りて町の郵便局から国際電話をかけていました。ある時、見るべき儀礼などが続き町に降りる日が伸び伸びになったことがありました。当時は、チェンマイの放送局から北タイ全土に1日2回流れるカレン語ラジオ放送があり、村の人々は冠婚葬祭や催事の日程を遠く離れた村の親戚などに伝えるのに個人的なアナウンスを流してもらっていました。ある日このカレン語ラジオ放送で、「日本から来たヨーコさん、ご家族に連絡を入れてください」という放送が流れたのです。なかなか連絡のない私を心配して家族が伝手をたどってこのカレン語放送にメッセージをゆだねたのでした。村では5世帯に一つくらいラジオがありましたが、これが流れた日は、どこへ行っても「おいおい、家族が心配してるらしいよ」などと言われ、さすがに吃驚して翌日チェンマイに降りました。今では日本からでも村の人たちとSNSで連絡しあっていることを考えれば、この30年あまりの変化は凄まじいものがあります。
──カレンのフィールドにしばらく行けなかった後、久しぶりに行ったときに、村の人々に「あなたの夢を見た」と言われたと伺っています。そのとき、速水先生の相手への想いと同時に先方の先生への想いもあるのだと感じました。速水先生のフィールドとのつながりを聞かせてください。
久しぶりに村を訪れると、誰かに必ず言われるのが、「昨日の晩、あんたの夢を見た」という話です。あまりに頻繁にいわれるので、社交辞令のようなものかなと思っていたのですが、あながちそればかりでもないようです。彼らにとって夢は、「クラ」と呼ぶ魂の行為を映すものと理解されます。村を訪ねようとしている私の魂が、その前夜に彼らの魂と夢で出会っているとしても不思議はなく、そうした前提のもとで私を迎えてくれる表現なのだと理解するようになりました。村で過ごしていて、夢見が悪いときなど、うっかり朝起きて村の人に話すと、「それはいけないね。儀礼をしよう」という運びになりかねません。悪い夢を見るのは、私がぼーっと町を歩いているときに37ある魂のいくつかをうっかり落としてしまい、それが道端の犬の糞やら、良からぬものにくっついてしまっているのだ、と言って魂を呼び戻す儀礼をするというようなことになるのです。
──お子さんが生まれたあと、初めてお子さんを連れてフィールドワークに行かれたときに、フィールドの人たちとの経験が変わったとおっしゃっていました。具体的にどのように変わったでしょうか。
出産・育児でしばらくは調査に出かけられなかったのですが、子供が4歳になったころ家族に預けて、そして5歳になった時には初めて一緒に連れて調査地を訪れました。丁度現地で最初の調査時のホスト・ファミリーの長女にも女の子が二人いて、上の子が息子と同年でした。すぐに仲良くなって言葉は通じないのに楽しそうに田んぼや山道、竹づくりの今にも床から足が抜けそうな家の中で走り回っていました。こうして私の家族の存在が村の皆さんの中でも実在のものとして認知されたことで、私も村で単なる時々やってくる日本人ではなく、ソぺフ(息子のカレン名)の母として認識されるようになったようです。
3. キャリアとライフイベント
──研究者になる決意はどのようにされましたか?
学部3年の終わり頃からは就職活動を始めましたが、男女雇用機会均等法以前の時代で、それまであまり考えたことがなかった女性としてのキャリアのあからさまな限定性に衝撃を受けました。丁度同じころに卒業論文を書く面白さを経験していたこともあり、結局就職はしばらく横においてもう少し勉強してみようと決めました。というわけで最初から研究者を目指していたわけではありませんでしたし、どこかの時点で、「研究者になるぞ」と思い決めたわけでもなかったように思います。この辺りについては別の記事をご参照ください10。
先述の学生時代からの話でおわかりいただけるかと思いますが、大学院に入る時に研究者になると思い決めていたわけでは決してありませんでした。自分に向いているのか、他の道を考えるべきではないか、という迷いはいつもありました。そして博士論文を書きあげた頃に子供ができて、出産・育児で忙しかった時期は、一人ポッツリと取り残されていくような感覚を味わいました。それでやみくもに公募に応募したりしながら、何度も打ちのめされていました。ただ書くことがあるかぎりは書こうと、迷いを紛らわすように書いて投稿を続けて、それがその後につながっていきました。
──研究を続けていくなかでどんな時に面白さを感じますか。逆にしんどいなぁ、と感じるときはどんな時ですか?
調査・研究の興奮は、主に四つの場面で生じるかと思います。一つ目はフィールド調査中に意外な事実を見つけたとき。二つ目はそれをどう考えるかというヒントを別のフィールドやあるいは誰かの論文・著書で見つけたとき。三つ目はそれらをもとに考えがひらめいたとき。四つ目は、それを文字にせよ語るにせようまく伝えられたとき。そして最も私にとって「しんど/楽しい」のは、四つ目の言葉にしていく段階のように思います。
──学生との関わりや指導を通じて研究の関心が変わったり、広がったりしたことはあるでしょうか。どのような経緯がありましたか?
特にどの経験がということは挙げられないのですが、どの院生もそれぞれ独自の個性でテーマと調査地を開拓していきます。そのいずれの段階も、私にとっては新しい冒険を横から見せてもらっているようで楽しいものですし、学生が苦しい時はこちらも苦しいです。また自分の知らないテーマについてよくも「指導」などと言えたものだと思いますが、とても勉強になります。そして成果が出たときには自分のことのように嬉しいです。
──研究者として、教育者として、目指してこられた理想の方はおられますか?あるいは「このようでありたい」と心がけておられたことがありましたか。
目指す理想というのとは少し違うかもしれませんが、挙げるとすれば個人的な恩も含めて、故林行夫先生です。共同調査などで垣間見る機会のあった林さんの、相手の懐に入って徹底的に話を聞く調査者としての技と姿勢は、決してマネができるものではありませんでしたが、手本にしたいと思ってきました。また、日本の学会に縁が薄かった私に声をかけて研究会などに誘ってくださった林さんがいなかったら、私は東南研に来ることもありませんでした。私も林さんに習い、できる限り内外の若い研究者が東南研に来る機会を支援したいと心がけてきました。
教育者としてというような大上段のお話ではないのですが、20代というのは男女問わず迷いの多いときです。特に日本のジェンダー感覚のもとで成長した女性は、わき目もふらずに研究に没頭する前に自分にそのような能力や資格があるのだろうかと迷いがちです。自分の学生には男女問わず、迷うことは悪いことではないけれど、追究したい問いがあるなら追究するように促してきました。そのように自分のドライブになるような大きな問いを持つことの大切さ、そのためには読むことの大切さを伝えるように努めてきました。私にできることは、そのためのサポートをして一緒に面白がり励ますことに尽きると思います。
4. 今後の計画
──今後の野望を聞かせてください。
野望と言えるようなことではないのですが、2016年から実施してきた高齢者とケアの研究については、まだまとまったものを出せていません。そうこうするうちに、現地の状況はどんどん変わってきていますので、あまり現状と齟齬がない形で何とかこれを形にしたいと思います。調査開始当時はそれほどでもなかったのですが、今まさにタイの人文社会系の研究者の間でもこのテーマへの関心が広がっていて、高齢化先進国日本の対応を知りたいと言って、日本に来る人も増えています。たとえば昨年もこの目的で一か月日本に来られたタイの研究者と日本の各地を回って、私自身全く恥ずかしながら日本の現場をほとんど見てきていなかったことを痛感し、大変勉強になりました。今後もこうしたタイや東南アジアの研究者とこのようにやりとりができたらと思っています。
──どのようにタイのフィールドとつながっていくご予定でしょうか。
2月にも、山の村で結婚式があると知らせを受けているので行く予定にしています。村とのつきあいは今まで通り、それが調査や研究につながる場合があるかないか、家が建つかどうか(?)は別として続きます。また新しいテーマで新たな気持ちで向き合ってみたいとも思います。
(2024年1月9日)
謝辞
本メールインタビューの実施にあたっては、速水ゼミ卒業生の皆様に設問のご協力をいただきました。記してお礼申し上げます。(広報委員会)
注
- タイとビルマに居住しチベット・ビルマ語族に属する言語を話す人々で、当時タイでは「山地民」の一グループとしてリストされていた。人口は当時タイでは37–8万とされた。 ↩︎
- Between Hills and Plains: Power and Practice in Socio-Religious Dynamics among Karen (2004年)等として刊行。 ↩︎
- ”Karen Culture of Evangelism and Early Baptist Mission in Nineteenth Century Burma”(2018年)ほか。 ↩︎
- “Labour of Devotion: Material Construction and Charisma of Saintly Monks in the Myanmar–Thai Border Region”(2022年)ほか。 ↩︎
- 『差異とつながりの民族誌 北タイ山地カレン社会の民族とジェンダー』(2009年)。 ↩︎
- 小泉順子・Ratana Tosakul・Chalidaporn Songsamphanとの共編著The Family in Flux in Southeast Asia: Institution, Ideology and Practice(2012年)。 ↩︎
- 木村周平・西真如と共編著(『人間圏の再構築──熱帯社会の潜在力』2012年)。その後科研費プロジェクトの成果として編著(『東南アジアにおけるケアの潜在力──生のつながりの実践』2019年)を出版。 ↩︎
- “Between State and Family: Biopolitics of Elderly Care and Emerging Communality in Northern Thailand”(2019年)。 ↩︎
- “Redefining Otherness from Northern Thailand: Notes Towards Debating Multiculturalism in the Region”(2007年)。 ↩︎
- 「「もう少しやってみたい」をつづけて」(京都大学男女共同参画推進センター、2010年)。 ↩︎