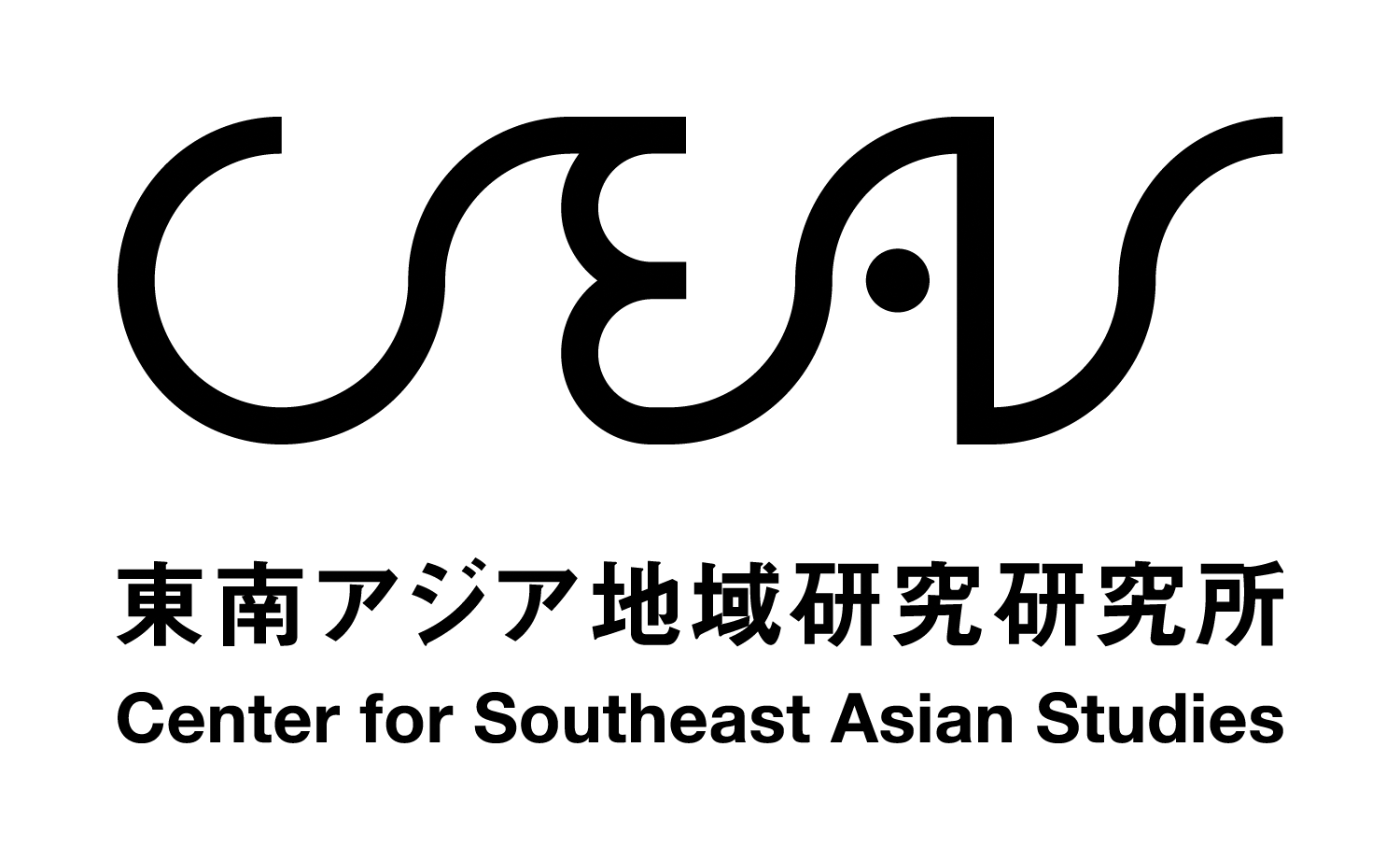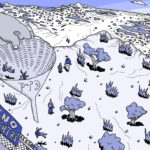西尾 善太
(フィリピン地域研究、文化人類学)
2023年3月、編著『現代フィリピンの地殻変動』(花伝社)が出版されました。本書は、私を含め、2010年代に調査を行ってきた若手研究者の長い会話から生まれたものです。大学院生の頃からマニラや日本で管を巻いて飲んできた友人たち、そこでは人類学、政治学、農学、都市研究など、多様なディシプリンの垣根を越えて議論が交わされてきました。8月8日に開催された合評会では、さまざまなバックグラウンドをもつ人が集まり、アカデミアに限られない応答がなされました。このエッセイでは、本書についての簡単な内容紹介に加えて、編者として私がとくに深く関わった親密性をめぐる問題についてご説明したいです。

かつて「アジアの病人」と呼ばれた状況から一転し、年間平均6%に達する経済成長率を記録するフィリピン。先進的な社会福祉制度も開始され、いわゆる“まとも”な社会へと舵を切っていくようにみえながらも、2016年、大統領選に勝利したロドリゴ・ドゥテルテは、麻薬戦争によって裁判にもかけず多数の人々を殺害しました。白黒では判断することができない、2010年代のフィリピンの激動をどう考えたらいいのだろうか。本書は、このフィリピン社会の変化を、政治制度の近代化(第1部「フォーマリティへの欲望」)と親密性の変容(第2部「ままならないインティマシー」)から考察しました。第1部は、賄賂、汚職、一族による政治の独占、非近代的な農業など、フィリピンの後進性として論じられてきた特徴に変化が生じていることに注目しています。2010年代にみられた特徴とは、非属人的なシステムへの移行、いわゆる近代化の進展でした。本書の二つある序論のうち、原民樹さん(批判的序論「2010年代のフィリピン政治をどう理解するか─社会民主主義への転換」)は、社会民主主義的な路線へとフィリピンが向かっていると評価しています。
一方の第2部は、“まとも”な社会に向かう裏側で多くの問題が生じていることに注目しています。私は第2部の親密性概念のレビューを担当しました。序論で日下渉さん(序論「新時代のフィリピン人─なぜ「規律」を求めるのか」)は、「つながりで貧困を生き抜く社会」からの変容を指摘しています。フィリピンを訪れれば、人びとのあいだで密に張り巡らされた関係を見ないことはないでしょう。非属人的なシステムを長らく拒んできた一つの要因がこの親密な関係性であり、2010年代に変容を余儀なくされたものもこの親密性でした。しかし、どこにでも見られる親密な関係性だからこそ、それを捉えることは非常に難しいものです。第二部の執筆者である田川夢乃さん、飯田悠哉さん、吉澤あすなさん、久保裕子さんは、フィリピンの最も重要な領域に体当たりで研究されてきた人たちです。親密性を必ずしも専門的に学んだわけではなかった私は、Facebookのグループチャットをつくり、インフォーマルな会話をはじめました。

田川さん(第7章「「親しみやすさ」の複数性─コールセンターとKTVの労働世界」)と飯田さんは、親密性がグローバルな資本と結びついて暴力を帯びる側面を論じています。かつて日本からの売春ツアーの行き先となったマニラ。性産業では、働く女性にとって単なる「仕事」でありながらも、その仕事にはパフォーマンスとしての親しさがお客さんとの間で演じられる。こうした親密さは、性産業に限らず、コールセンターなどフィリピンで急成長する産業でもサービスの中心となっています。日本の農業を支えるフィリピン人労働者をフィールド調査する飯田さん(第8章「OFWの身体に対する「遅い暴力」─農村男性の出稼ぎ先における痛みをめぐって」)は、仲間同士のあいだで親密性が日々の労苦をケアしながらも、それは現在の搾取的状況を持続させうる危うさをみています。親密性が商品化されてサービスとなること、あるいは無償の行為として経済の一部に深く埋め込まれること。こうした親密性の囲い込みがフィリピンの順風満帆な経済成長を支えているのです。
一方、親密性が経済に囲い込まれるだけでなく、それに抗する潜在力となっていることに目を向けるのが吉澤さんと久保さんの論考です。コロナ禍を経て久々のフィールド中の吉澤さんからグループチャットにこんな言葉が寄せられました。「暴力とか規範とか囲い込みとかいうけど、フィリピンの親密性ってなんの意図性もないso whatなもので溢れているよね!」と。空港で女性の職員にパスポートを求められ、年齢を聞かれる。「あなた〇〇歳なのね、私は〇〇歳よ!」という突然の自分語り。何の目的もなく、ただ近づく。ヴィサヤ地域の「リホック」という言葉を頼りに、忙しく動きつづけながら日々立ちあらわれる問題に奔走する女性たちを吉澤さんは描いています(第9章「他者への応答としての「リホック」─元OFW女性の日常から見る現代フィリピンの共生と分断」)。久保さんは、流産や中絶の経験者が行う胎児へのケア(第10章「消費される未来、沈殿する過去─妊娠期における喪失経験と女性たちの応答」)を論じています。カソリック教徒が多数のフィリピン社会では、中絶は悪であり罪なのです。胎児を喪失した経験は、社会的存在として認知されないため嘆かれることも、その悲しみを受け止められることもない。カソリックに根ざす社会規範がその経験を排除するからです。だからこそ、久保さんはその経験に対して女性たちが行った些細な、たとえば、胎児を包んだそのタオルを手元に残し続けること、にケアを読み取ろうとする。胎児とのあいだで結ぼうとする親密な関係性、宗教的規範に囲い込まれながらも行われる親密な行為は、囲い込みに対するオルタナティブを提示しています。

8月8日の合評会のタイトルは、「これからの「地域」との関わりと応答に向けて」でした。終わりのない会話を続けてきた私たちが、本書を通してさらなる会話、議論、そして応答を始めていくための場としたい、そんな思いから開催しました。学術的な質問、率直な想いがのった問いかけ、アカデミックな場にはじめてきた学部生の言葉、さまざまな背景をもつ人が集う場となりました。こうした応答が可能な場をこれからも持続させていきたい、そう強く感じる機会となりました。