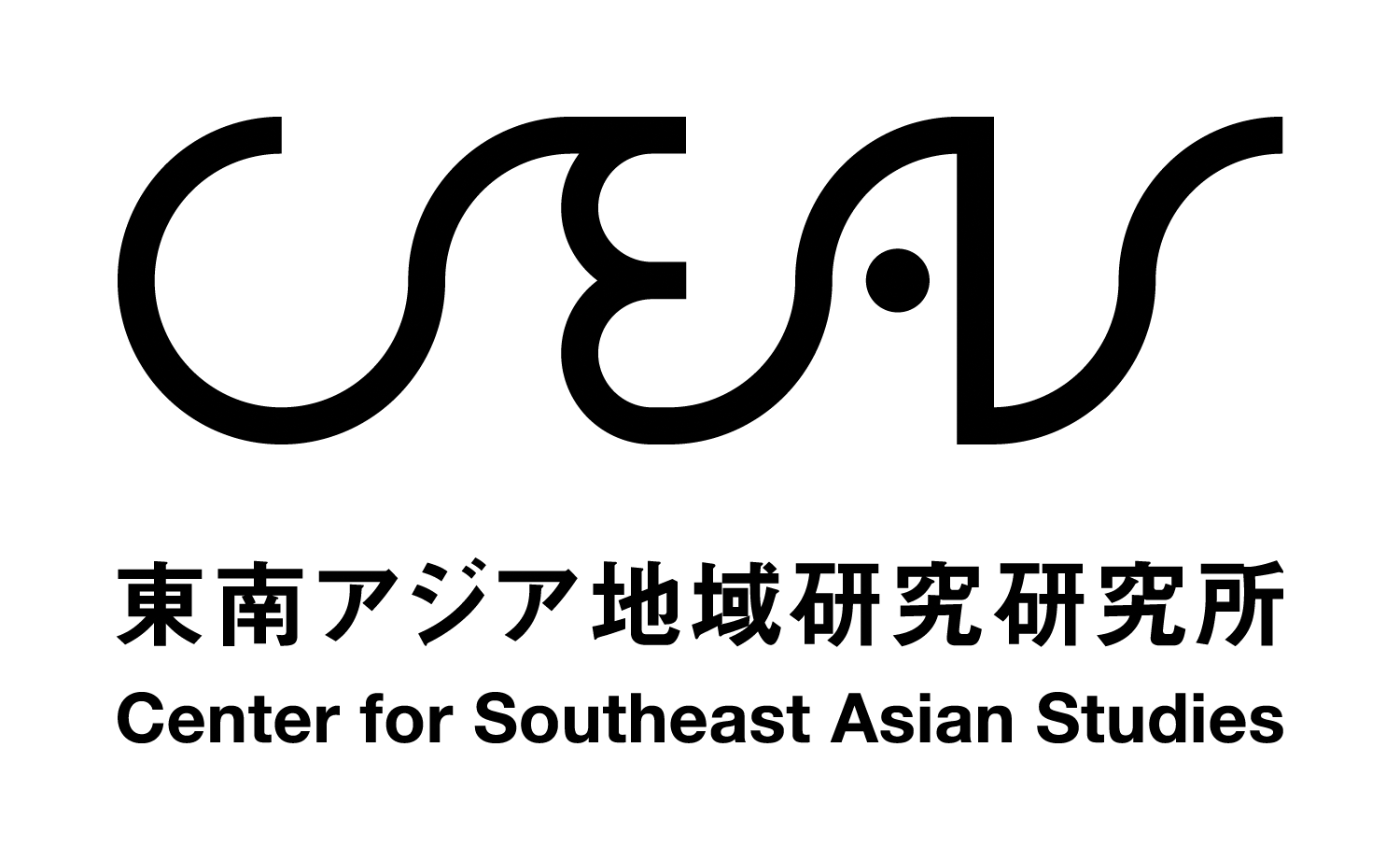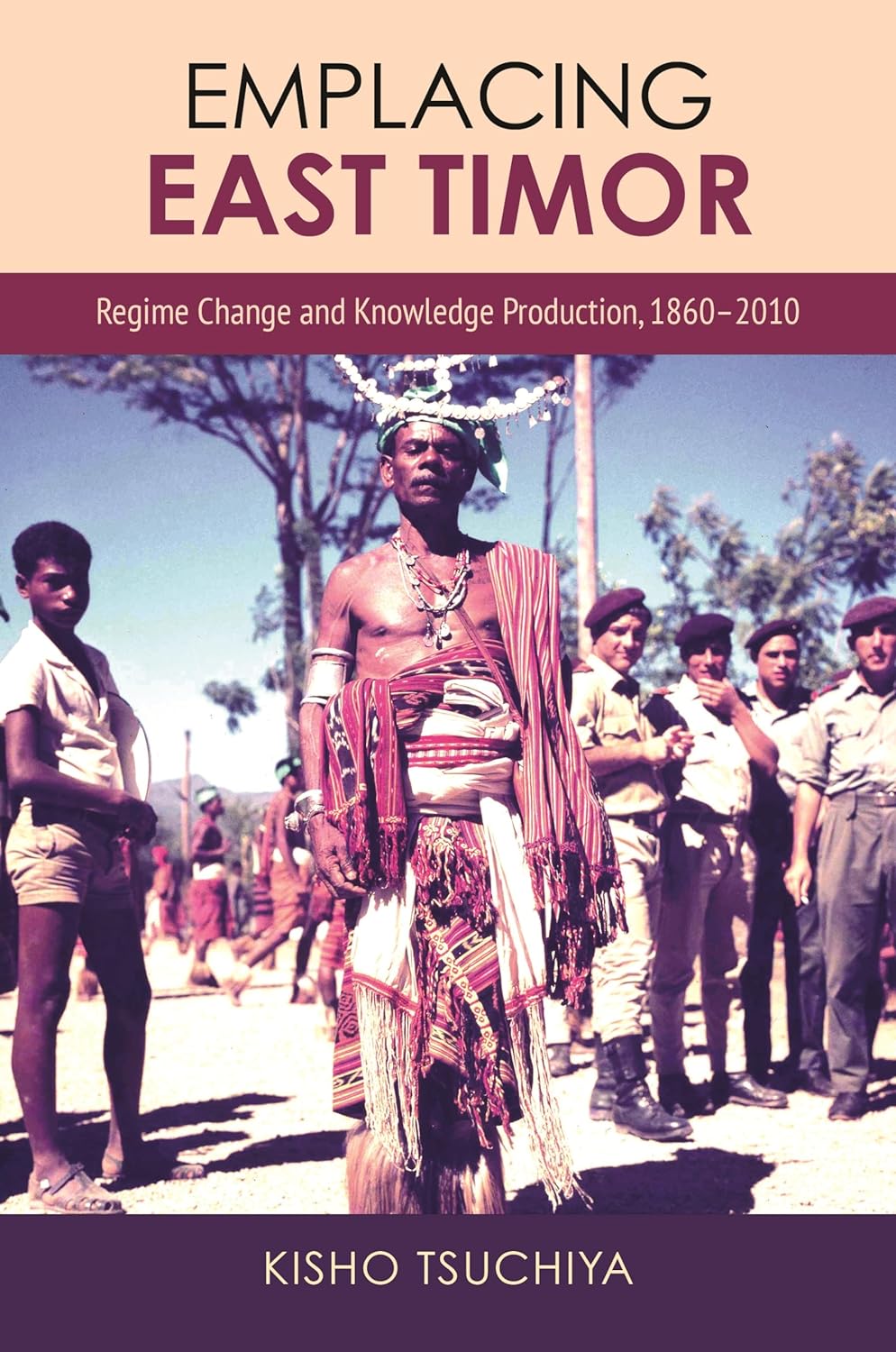土屋 喜生(東南アジア研究、近現代史)
執筆の背景
2000年代の終わりごろ、私はまだ学部生でしたが、国連東ティモール選挙支援チームで仕事をする特別な機会に恵まれました。当時20代前半だった私は、国際協力に対して理想主義的な期待感をもっていて、いわゆる平和構築・人道支援・民主化等の「実験場」として紹介されていた東ティモールで働くことに興奮していました。
しかし、実際に東ティモールでの勤務を始め、町や村の人々とテトゥン語で会話をし、国連機関内部で流通している情報に触れていると、日本にいる時に文字情報として知っていた東ティモールや国連のイメージと、現場での印象や人々の常識、現地での国連の評判は大きく乖離していることがわかってきました。
当時、東ティモールは、「インドネシアによる武力占領から解放された新しい独立国家」、そして「国連の平和構築活動の成功例」等として海外の学生たちに紹介されていました。しかし、実は全ての東ティモール人たちが、2002年の独立後の国家や社会に満足していたわけではありませんでした。国連主導の急激な変化は、新しい秩序や民主的に運営される国家をもたらしつつも、様々な面で社会的緊張を作り出しており、私が東ティモールを訪れたのはそうした不満が爆発した2006年の暴動の直後でした。「国連に対する抵抗運動」、あるいは独立運動を続ける人々もいて、選挙管理の仕事に関わっていた私は、彼らによる選挙ボイコットを直接に経験することとなりました。彼らによれば、「東ティモールの独立を助けた」はずの国連は、「新たな植民地主義」の象徴であり、「独立のための闘争は続いている」のでした。
一方、我々国際協力に関わる人々には、これらの思想や運動の意味や文脈が全然わからない。そして「国際協力の実験場」は、今でも反植民地主義闘争の現場でもあり、意図せず私は「植民地職員」のような存在になったのです1。
このような背景もあり、私は特定の場所(例えば東ティモールのような)について、国際的に、あるいは国内で流通する知識が作られていく過程、そこに介在する人間関係やお金の働き、そしてそこで生きる人々にとっての場所の意味やそこでの彼らの経験に関心を持つようになりました。本書Emplacing East Timor: Regime Change and Knowledge Production, 1860–2010(『エンプレイシング・イースト・ティモール:政権交代と知識生産、1860年代から2010年代まで』ハワイ大学出版会、2024年。邦訳は未刊行)はかつての私のような、国際協力に関わる人々が経験するジレンマに対して、東ティモールの近現代史や知識の生産に関わる諸問題を説明しようとするものです。
タイトルについて
本書のメインタイトルはEmplacing East Timorであり、意訳すると「東ティモールを(人間にとって意味のある)場所に変える」ということです。まず、場所と空間という二つの概念には違いがあります。つまり空間は人間にとって空虚であるものの、それが人間にとって何か意味を持った時に場所となる、と考えます。私は「emplacing」という言葉を「空虚な空間を意味ある場所へと変えること」という意味で用い、場所に意味を与える人間の活動や表象行為を表現しました。19世紀半ばまでを生きた多くの人々にとって、ティモール島は単なる空間に過ぎませんでした。しかし現在では明らかに場所として認知されています。それは、この場所を巡って戦争や紛争が行われ、人々が運動を展開したり占領したりし、私のような研究者や作家が場所に関連付けられた言説や思想を作り出してきたからです。
本書の狙い
本書を書くにあたり、主な目的が三つありました。まず、私が国連職員として勤務していた時、どれだけ既存の歴史書を読んでも、新生国家でのティモール人たちが依拠する多様な政治理論や対立の背景が全く理解できませんでした。その原因の一つは、先行研究群が、断片的な情報で構成されており、言説としても非常に政治化されていたことでした。そこで、私の最初の狙いは、ポルトガル語圏、英語圏、日本、そしてインドネシアや東ティモールにおける学術的な伝統を統合することにより、近現代のティモール島史をより包括的に描きつつ、既存の様々な(東)ティモール論を批判しつつ紹介することでした。
本書の第二の狙いを述べます。ティモール人たちが表現してきた様々な政治思想を彼らの文脈で理解するためには、彼らが東ティモール(あるいはティモール島)という場所にどのように、またどのような意味を与えたのか、そして先行する知識を借用したり、それに対抗した表現によって自分たちの論旨を正当化してきたことを知る必要があります。その際、注意しなければならないことは、彼らがよりどころにしようとした知識の大部分は、元々「ティモール」という場所を「植民地」として底辺に位置付けようとした植民地学者等の海外の著者たちによって作られたものだということです。したがって、本書の第二の狙いは、19世紀半ば以降の(東)ティモール論の系譜とその背後にあるグローバルな力関係やネットワークを明らかにすることでした。
最後に第三の狙いは、このような力関係や個々人の表現活動を越えた、より深いティモールの歴史、繰り返される政治のパターン、知識生産の構造を理解することでした。なぜなら、長期にわたる構造と反復、規則性、そして長期的な変化などを説明することにより、歴史家は一般の人々の理解の一助になれるからです。
発見したこと
本書には、様々な発見が含まれています。中には、読者のために明示されている発見もあれば、暗示されているだけのものもあります。そのため、読み方によってかなり異なる印象を与えるものとなっています。ここでは、明示されている主要な発見を2つ紹介します。
一つ目の発見は、「歴史を知っている」「ティモールを知っている」はずのいわゆる有識者や様々な団体のスポークスパーソンたちは、専門分野を離れた情報を扱ったり、自分の主張を通す必要がある時、先行する知識を非常にいいかげんに借用したり、エキセントリックな解釈を駆使する傾向があるということです。例えば、「インドネシア」という語を広めたジョージ・ウィンザー・アールは、「(マレー人種とパプア人種を区別するには)一目見るだけで十分だ」と書き残しており、またアールよりも頻繁に引用されるアルフレッド・ラッセル・ウォーレスは、西ティモールのクパンに1泊2日滞在し、ティモールの女性たちが大きな声で会話するのを聞けば「目で見なくてもマレー人種ではないとわかる」と豪語しています。20世紀以後の科学の基準から考えれば、彼らのティモール人論というのは人種主義に基づく個人的な印象の域を出ないものだったのです。そして1970年代末、インドネシアによるポルトガル領ティモールの武力占領が国際問題となったとき、東ティモール独立のための国際運動に関わった人々は、「目で見なくてもマレー人種ではないとわかる」と書いたウォーレスを引用して「東ティモール人はパプア人種」とし、インドネシアと東ティモールの戦争は「外国勢力による侵略だ」と証明しようとしたのです。つまり、人権運動の言説は、植民地時代に作り出されたいい加減な人種主義に基づく情報を選択的に利用していたということです。本書ではこのような例を多数挙げつつ、人間性の喜劇的な面を暴露しています。
しかし、より深刻な発見は、近現代東ティモール史における暴力による政権交代のサイクルと、このサイクルを形成する長期的要因、およびこれらが社会と知識の生産に与える影響についてのものです。過去150年ほどのティモール島の歴史には、人口の数割を消失させる大規模な戦争や紛争、それに伴う権力構造の変遷、新しい体制による安定と社会的緊張の深化、そして再び暴力の顕在化と体制移行という、30年程度の期間を経て反復するパターンが見られます。本書の結論では、このような暴力のサイクルを形成した要因のいくつかはまだ存在し続けていると論じています。しかし「植民地」「東南アジアのキューバ」「人権侵害の場」「抵抗運動の場」「国際協力の実験場」等、その時々の国際社会が語るティモールの物語や場所のイメージは、長期的な傾向よりも時事ネタの背景として作り出されるため、そこに住む人々の長い経験や世界観や日常生活を圧殺してしまうということが起こるのです。21世紀に生まれた新しい国、東ティモールの平和構築を長期的な観点から考えるには、繰り返される歴史的なパターンを考慮し、我々情報生産者の責任を認識する必要があります。このような意味で、私は本書を歴史学や地域研究の学生や研究者だけでなく、国際協力に携わる人々やこれから国際協力を志そうと考えている若い人々にも向けて執筆しました。ご一読をいただければうれしいです。