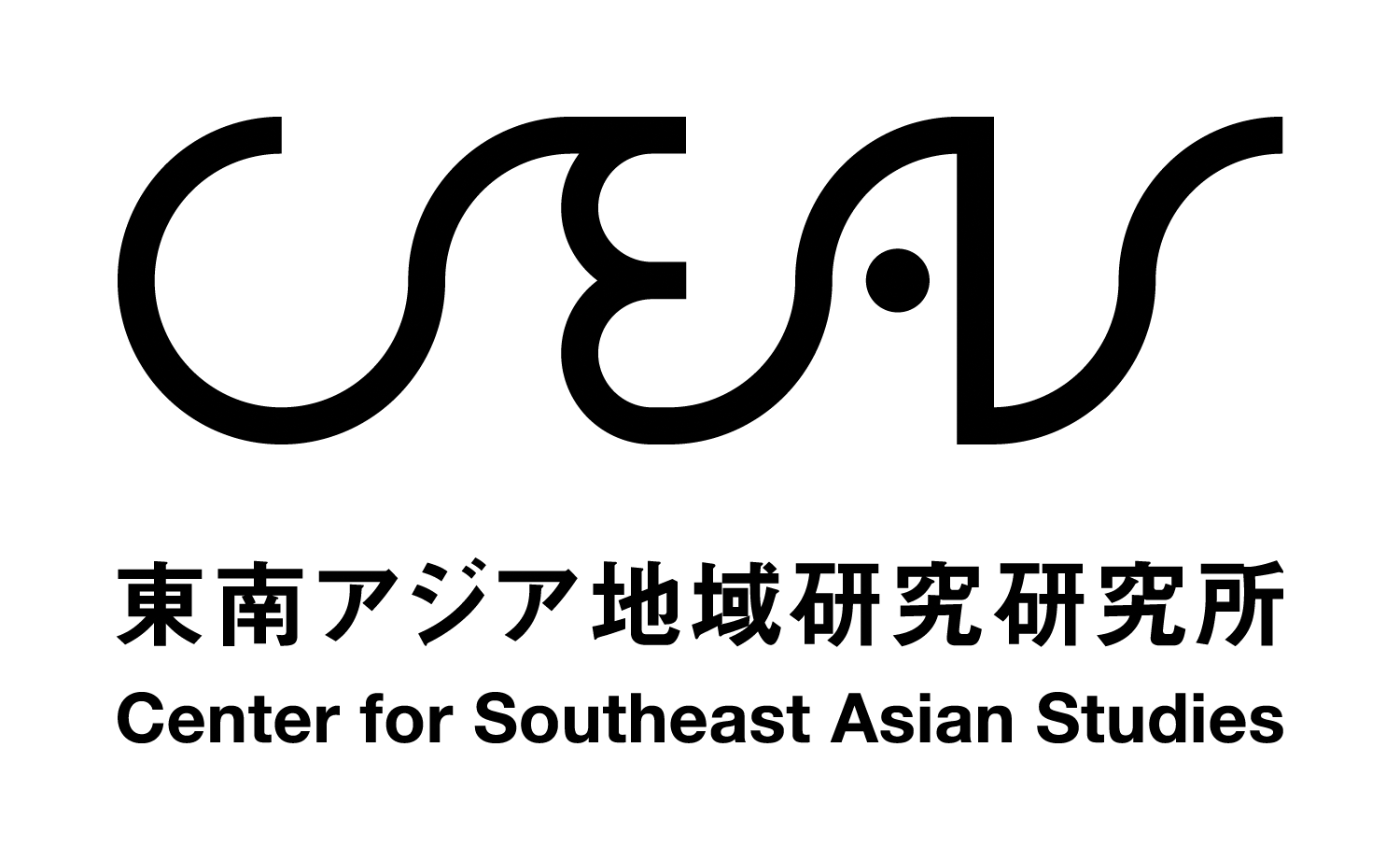久納 源太 (地域研究、都市研究)
それは、乾季のジャカルタでのことだった。私は二人の友人と街で有名な刑務所に向かっていた。受付を終えると、首から下げる訪問者証を渡され、ブルーライトに反応するスタンプを手の甲に押された。マットが敷かれた面会エリアは、受刑者と訪問者らが自由に交流できるスペースとなっていた。訪問者が増えるにつれ、係の受刑者がマットの追加に勤しんでいた。しばらくすると、私たちが会いに来た男性──ここでは仮に「アフマド」と呼ぼう──が面会許可証を手に現れた。塀の外での彼の生活は不安定で、いわゆる軽犯罪や薬物依存に満ちたものであった。しかし、中に入ると状況は「違った」。その良し悪しには触れず、彼はそう言った。刑務所の中では、悪名高いギャングのリーダーや殺人罪で服役中の元警察高官など、外では決して関わることのない大物たちと出会う機会があったのだ。彼が巻き込まれる喧嘩も、もはや個人的なものではなく、監房内の縄張り争いに起因するものになっていた。彼自身、中央・西ジャカルタで逮捕された囚人たちが集う「バルプス(Barat=西とPusat=中央の略)」と名付けられた同盟に加わり、他のグループと競い合っていたのだった。
このようなインドネシアの刑務所文化を、ジョシュア・バーカーは『恐怖の国:ポストコロニアル都市の警察』(2024年、原題State of Fear: Policing a Postcolonial City、邦訳は未刊行)の序章で鮮明に描いている。著者は1990年代半ばにバンドンの刑務所を観察しているが、面会エリアに限られた私の経験とは異なり、彼は監房内部にまで立ち入ることができたようだ。監房が実質的に受刑者の支配下にあったという著者の記述は、アフマドから聞いた話と一致していた。刑務所を訪れる際に強く感じる印象のひとつが「恐怖」だという。思い返せば、著者が言うように、私たちもまた単純に恐怖を感じていた。パノプティコンを連想させる建築や監視技術から厳格な手続きに至るまで、刑務所内で見聞きした多くのものからは、歪さが感じられる。監房内部の縄張り争いに関する話もその一つだ。このように恐怖が発現する独特な様相を、著者は二つの世界の衝突として表現している。一方には、犯罪やテリトリーという不透明な世界があり、他方には、官僚的な警察・監視活動という明確に現れる世界がある。その両者の住人が恐怖を担保にした「安全」を主張し合う有様は、刑務所の壁を越え社会全体を形作っている。本書は、このことを、長年にわたり警察活動の日常的側面を探求することで示している。
話を戻すと、アフマドは、ある都市カンプン(集落)にて、非公式な駐車場の管理や時折の薬物取引で生計を立てていた。彼の駐車場管理グループは、大通り沿いの駐車スペースを管理する中で、他の地区のならず者集団と頻繁に衝突していた。グループの長は近隣自治会の会長と密接な関係を保ちながら、自治会と共に大通り沿いの事業者から「警備費」を徴収していた。これらの慣行は、著者の言うところの、ならず者の支配圏と結びついた地域的なテリトリーの現れだ。このテリトリーは本質的に非恒久的であり、継続的なケアが必要となる。ケアの行為には、装飾用の門の建設や共同のベンチを作るといった些細な活動から、夜警をめぐる実践という不可欠な行動までが含まれる。地域的なテリトリーは、多くの人々が強い帰属意識を抱くものであり、その正当性は市民権や民族、政治的集団といった他の帰属の枠を凌ぐ。隠れたテリトリーが入り組んだこの世界は、まだまだ奥が深いことに改めて気が付かされた。
(イラスト:Atelier Epocha(アトリエ エポカ))
本記事は英語でもお読みいただけます。 >>
“Prison, Territories, Neighborhood” by Genta Kuno