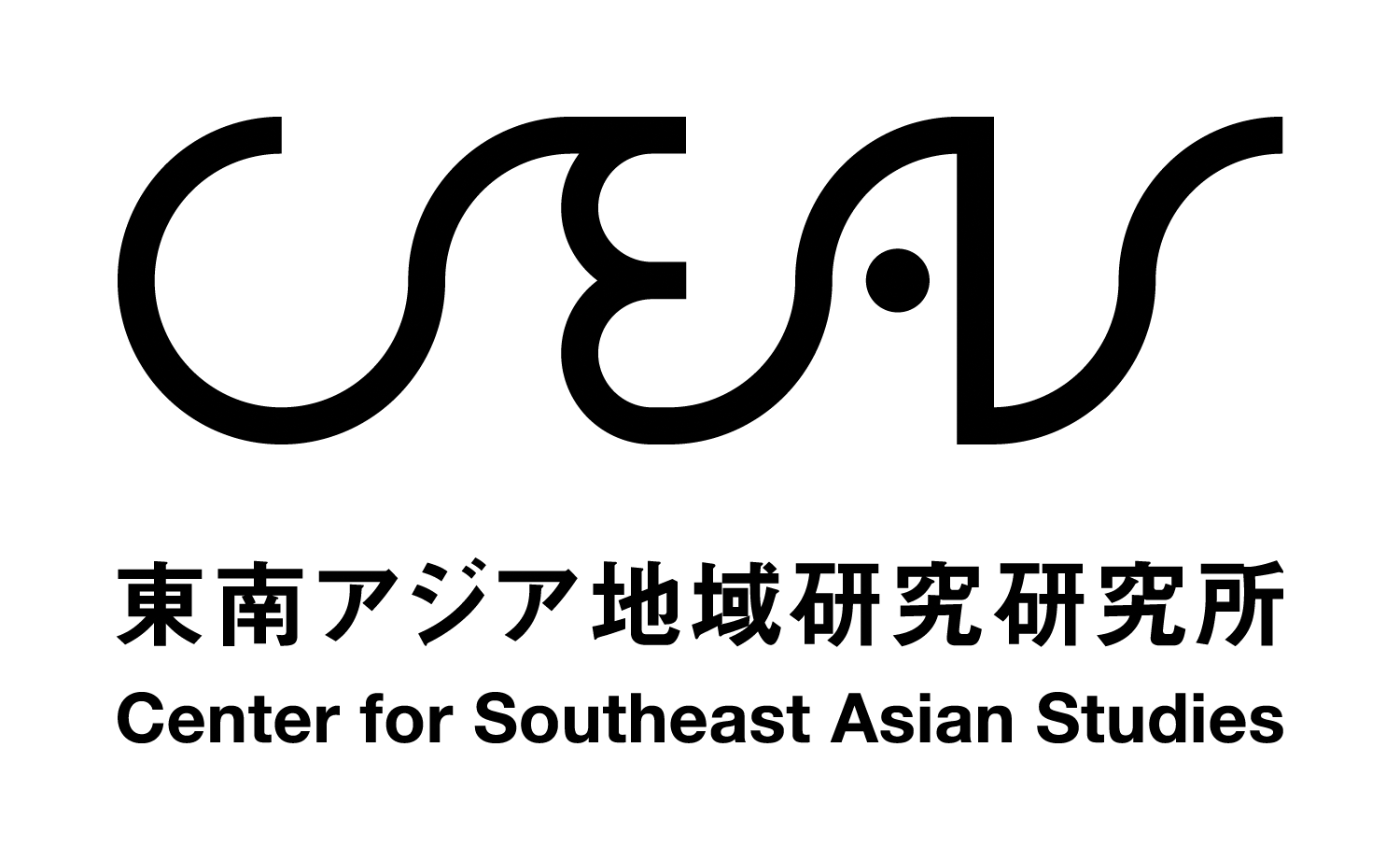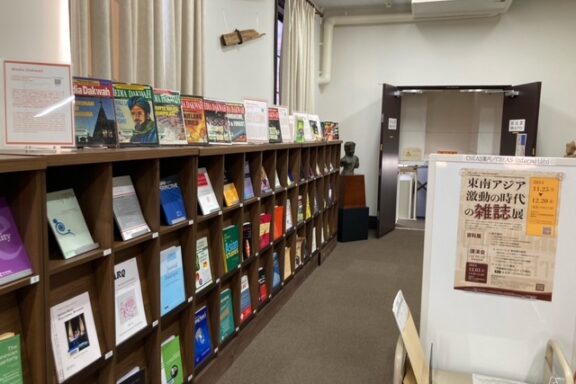神谷 俊郎(京都大学東南アジア地域研究研究所連携研究員/京都産業大学URA)
東南アジア地域研究研究所は、2024年11月1日(金)、特別講演会「〈京都織物〉と渋沢栄一:京都近代産業の礎を築いた人々」を開催しました。
京都織物(後に京都織物株式会社)は、西陣織の発展と近代洋式絹織物産業を興す目的で、1887年(明治20年)、「近代日本資本主義の父」とも称される実業家・渋沢栄一の強力な後押しを受けて設立されました。本研究所図書室本館は、この京都織物の本社社屋として1889年(明治22年)に建造された、明治期を象徴する赤レンガ造りの「モダン建築」で、その歴史的意義と文化財としての重要性が認められ、2024年8月に文化庁登録有形文化財に登録されました。
この登録を記念し、また、渋沢をあしらった1万円新紙幣が巷間に出回り始めた時宜もあり、我々が住み働く京都の町の産業振興に渋沢がどのようにかかわっていたのかを知る機会とすべく、渋沢研究をライフワークとされる京都産業大学経営学部の松本和明教授(経営史)による講演を企画しました。
松本教授には、「京都織物」と「モダン建築」をキーワードに、約1時間、主に関西の企業関係者や一般市民の聴衆約50名を前にご講演いただきました。「図書室のレンガはどこで製造されたのか」という話題を皮切りに、渋沢の来歴、渋沢の思想の柱である「官尊民卑の打破」「合本主義」「道徳経済合一」「競争と協調」などへの解説のあと、京都織物を巡る話題に移りました。
明治初期、奠都により「首都」の座を奪われた京都は、大変なピンチを迎えます。京都の経済をどうにかしなければならない。京都織物の設立構想は、京都の産業の再興だけでなく、地域の将来・発展・存続を見据えた新機軸でした。

長谷信篤[1](初代京都府知事)と槇村正直[2](第2代)は、勧業場や織工場を開設し産業の近代化を図ろうとします。北垣國道[3](第3代)は、織殿を官ではなく民で展開する必要があると考え、田中源太郎[4]、浜岡光哲[5]、内貴甚三郎[6]、渡辺伊之助[7]、中井三郎兵衛[8]に声をかけ、さらに東京の渋沢栄一、大倉喜八郎[9]、益田孝[10]にも協力を求めます。大阪の熊谷辰太郎[11]も加わり、京都−東京−大阪が手を組んだ民間を中心とする事業方針が固まり、明治20年、資本金50万円(現在の価値で約50億円)で京都織物が設立されます。工場は愛宕郡吉田村下阿達(現在東南アジア地域研究研究所が立地する位置)に置かれ、内貴が委員長に就任、田中、浜岡、渡辺、熊谷が役員、渋沢、大倉、益田が相談役に就きました。渋沢栄一は筆頭株主となり、同社に対する強い支援の意志を示しました。
京都織物は、ヨーロッパ式の機械生産を導入し、絹・繻子(サテン)・綿織物の生産を手掛けていきます。特に繻子は華やかな光沢で高級感があり、フォーマルウェアやパーティドレス、コートやジャケットの裏地などに使用されます。繻子生産に力を入れたのは、日本の近代化に伴い、洋装の需要が増えることを見越してのことでした。渋沢は非常にきめ細かく経営に関わり、繻子織を軸に据え、工場を増築し、輸出にも振り向ける展開を見せました。また、海外(フランス)への練習生(研修員)派遣による人材育成・技術レベルの向上を図るなど、会社の発展を後押しし続けました。
渋沢栄一は後年、京都織物株式会社について、様々な困難があったものの、最終的には非常に強固な会社になったと述懐しています。絹・繻子・綿織物と、戦略商品を明確にしたことが成功の要因でした。堀川北大路の紫野に、さらに北陸地方の石川や福井にも工場を建てて事業範囲を広げていきました。こうした規模の工場が、京都の産業の近代化、ひいては日本の繊維産業の発展に大きく貢献したことは強調してもしすぎることはありません。
渋沢が退いた後は、田中源太郎、息子の一馬[12]、高島屋の係累である飯田政之助[13]や新七[14]などが経営を担いました。1937年(昭和12年)に発行された社史(五十年史)の序文で、当時の会長飯田新七は、同社が「浮薄を戒め、質実を尚び、穏健着実なる経営の下」、堅実経営を重視しつつ、時代に即した新しい製品を国内外に展開していることを誇っています。1932年(昭和7年)の東洋経済新報は「償却は十分ではないものの、借金がなく資金繰りにも問題がなく、案外堅実だ」と評価しています。
残念ながら戦後、会社はなくなってしまいますが、京都大学がこの地を買い取り、引き継いでいることは、地域の在り方として大変に重要なことだと思います。


なお、図書室本館のレンガ建材について、松本教授は当初、「渋沢が埼玉県に設立した日本初のレンガ工場である日本煉瓦製造か、もしくは大阪窯業による国産レンガではないか」と推測されていたのですが、残念ながらそうではなく、実際にはフランスから直輸入されたレンガであるとのこと。ただし、稲畑勝太郎[15]など京都織物の社員が研修で派遣されたのはフランスだったので、おそらく彼らの人的ネットワークが生きた形でレンガが輸入されたのでしょう。
後半は対談の部とし、聞き手として本研究所の貴志俊彦教授(東アジア史)が登壇しました。貴志教授から、京都織物が立地する敷地(つまり当研究所の敷地)の由来についての補足的紹介があったあと、お二人の間のダイアローグは、東アジア(中国、朝鮮、台湾)における渋沢の活動と評価、渋沢と同時代に大阪で活躍した藤田伝三郎[16]や五代友厚[17]、さらには清代中国の実業家張謇[18]にまで話題が及び、国内外に広がる渋沢の影響力を知ることのできる、充実した内容の対談になりました。

最後に貴志教授から松本教授に向けて「渋沢と東南アジアの関係について、何か情報をお持ちですか?」という問いかけがあり、松本教授は「渋沢はアジア全体には確かに目を向けていたけれども、東南アジアをどのように考えていたかは調べがついていません。もし研究を進めるなかで新たな発見があればお知らせします。共同研究のテーマになりますね」という言葉で会は締め括られました。
─────
本講演会は、11月に開催された「2024京都モダン建築祭」の連携企画として開催されました。ご協力いただいた各位に御礼申し上げます。
注
[1] 長谷信篤[ながたに のぶあつ]:京都府知事(初代)、貴族院議員。
[2] 槇村正直[まきむら まさなお]:京都府知事(第2代)、貴族院議員。
[3] 北垣國道[きたがき くにみち]:京都府知事(第3代)、貴族院議員。
[4] 田中源太郎[たなか げんたろう]:実業家、政治家。亀岡銀行(現・京都銀行の母体)、京都鉄道株式会社(現・JR嵯峨野山陰線)他多数の企業の設立に関わる。
[5] 浜岡光哲[はまおか こうてつ/みつあき]:実業家、政治家。京都新報(現・京都新聞)他多数の企業の設立に関わる。
[6] 内貴甚三郎[ないき じんざぶろう]:実業家、政治家。京都織物会社委員長、初代京都市長、京都商業会議所(現・京都商工会議所)会頭。
[7] 渡辺伊之助[わたなべ いのすけ]:西陣織仲買商。
[8] 四代目中井三郎兵衛[なかい さぶろべえ]:実業家、政治家。中井商店(現・日本紙パルプ商事)社長。
[9] 大倉喜八郎[おおくら きはちろう]:実業家。鹿鳴館、帝国ホテル、帝国劇場などを設立。
[10] 益田孝[ますだ たかし]:実業家。三井物産社長。多数の会社の設立に貢献。
[11] 熊谷辰太郎[くまがや たつたろう]:銀行家。第一銀行取締役。
[12] 田中一馬[たなか かずま]:実業家、政治家。京都電燈社長。
[13] 飯田政之助[いいだ まさのすけ]:実業家。高島屋呉服店初代社長。
[14] 四代目飯田新七[いいだ しんしち]:実業家。高島屋第2代社長。貴族院議員。
[15] 稲畑勝太郎[いなばた かつたろう]:技術者、実業家。稲畑産業創業者。
[16] 藤田伝三郎[ふじた でんざぶろう]:実業家。藤田財閥の創始者、大阪財界の重鎮。
[17] 五代友厚[ごだい ともあつ]:実業家。大阪商工会議所の初代会頭、大阪財界の重鎮。
[18] 張謇[ちょう けん/Zhāng Jiǎn]:清朝中国の実業家、民族資本家、政治家。