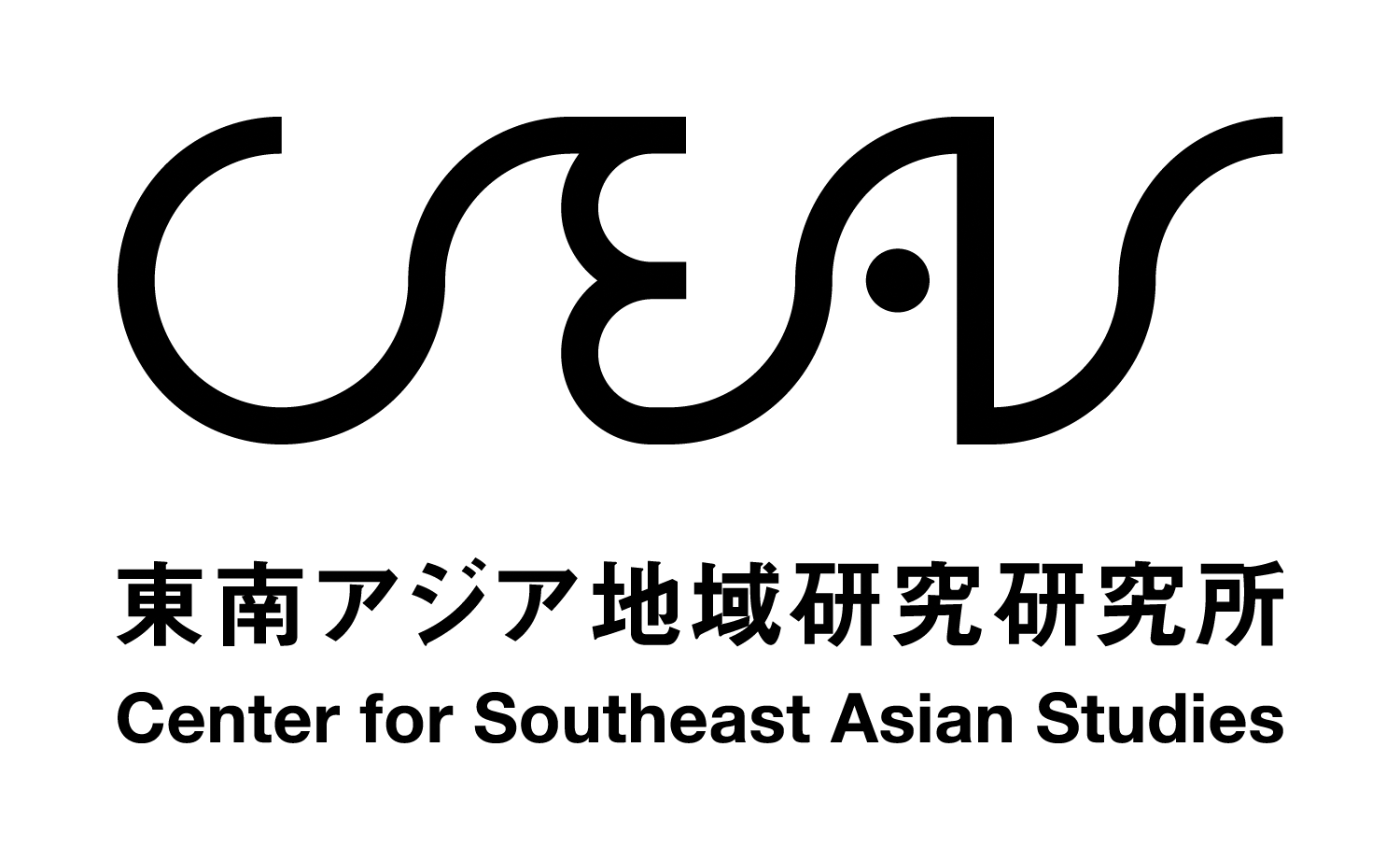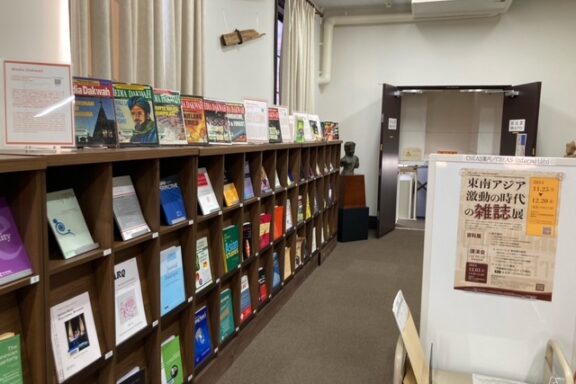久納 源太(地域研究、都市研究)

8月末に韓国釜山で韓国東南アジア学会と日本の東南アジア学会との合同会議が開催され、日本からの参加者として私も参加しました。当初は日本側が現地参加を予定していたのですが、台風の影響で会議はハイブリッド形式で開催され、日本側の参加者のほとんどはオンラインでの参加となりました。
東南アジアを対象とした会議に参加すると、しばしば「東南アジア」という地域概念の曖昧さに気付かされます。私たち地域研究者は、それぞれの国や集団が持つ文化、気候、政治の多様性をまとめて「東南アジア」という名前のもとに扱うというくくりの特殊さを理解している一方で、その地域を研究対象とし、東南アジアに関する会議に集まっています。基調講演を行った長津一史先生は、この「特殊」な研究対象としての地域の起源について、特に日本における「東南アジア海洋世界」をテーマに、ナマコや海の民というキーワードを用いて説明されました。この講演からも、東南アジアという脆くて特殊な看板は、それぞれの国で発展してきた学術的な伝統によって支えられているのだと改めて感じました。また、このような国際共同会議が、研究成果を共有する機会としてだけでなく、学術的な伝統の多様性を直接感じる場として非常に有意義であると実感しました。
多様性といえば、今回のセミナーのトピックの幅広さも印象的でした。日本側からの参加者が参加した英語セッションは5つのパネルに分かれており、「パネル1:ディアスポラ、インターフェースと交渉:海の民の視点から見た東南アジアのダイナミクス」、「パネル2:ソーシャルメディア、言説の創出と社会変革」、「パネル3:金融、投資、政治経済」、「パネル4:権力、知識、歴史」、「パネル5:分裂と区別:アイデンティティの政治」という内容でした。日本側の発表者には韓国側のコメンテーターが付き、その逆も同様に行われました。私も、有難いことに、発表者およびコメンテーターとして参加する機会を得ました。
コメンテーターとしては、ミャンマーにおける反軍政運動に関する発表(全北大学校東南アジア研究所Dr. Jinyoung Park氏)を担当しました。発表では、デジタルプラットフォームがディアスポラグループによる反軍政運動の資金調達の場としてどのように機能しているかについて説明されました。特に、軍事政権が「違法に」支配している土地に対して投資を行う形で資金調達しているプラットフォームもあるということに驚きました。インドネシアにおける都市住宅分野に興味を持つ私としては、開発業者と地元住民や移住者との土地紛争がしばしば問題となることから、ミャンマーでも同様の問題が起こらないか、懸念を投げかけました。例えば、軍事政権を打倒した暁にプロジェクトが始動した際、政府によって強制的に保有された土地の投資が将来的な紛争を引き起こさないかという点についてです。しかし、質疑応答の中で、私は、ミャンマーの反軍政運動支持者の状況はそのような潜在的な土地紛争の枠組みを適用できるものではないことを学びました。むしろ、軍事政権によって没収された土地をデジタル空間で取引することは、抵抗運動を経済的に支援するだけでなく、そうした行為自体が抵抗を意味しており、抵抗運動を概念上、維持する上で重要であることを学びました。
地域研究者、少なくとも私は、異なる地域の現象について素朴な疑問を投げかけることを、前提知識が不足しているからとためらうことが少なくありません。しかし、そうした素朴な質問は、時には自分自身の考え方や関心を投影する鏡になり、それを通じて自分の関心や思考回路について、新しい知識を得るきっかけになり得ます。まさに、今回のセミナーでのコメンテーターとしての役回りを通じて、ミャンマーの抵抗運動について学ぶだけでなく、私自身の土地紛争に関する興味が現代のインドネシアの状況に限定されているかもしれないことに気がつきました。
また、今回の学会では、長く愛読している論文の著者からフィードバックをいただく機会もありました。ジャカルタのインナーシティにおけるゲーテッドコミュニティの形成過程を記録してきたキム・ジーフン氏(インハ大学)が、私の「ジャカルタにおけるゲーテッドコミュニティと政治的志向性の関係」をテーマとした発表に対するコメンテーターを務めてくださいました。本発表では、ジャカルタ住民の政治的意思決定にゲーテッド・コミュニティが与える影響について報告しました。過去10年間のゲートの多寡と選挙結果に関する広範な空間データを活用し、ゲーテッド・コミュニティと投票行動との関係を実証的に分析しました。ゲーテッド・コミュニティの住民が保守的な傾向を示す欧米の都市における調査結果とは対照的に、私は、ジャカルタにおいて、ゲートの密度が高い地域ほど、非自由主義的な立場を示す候補者への支持が減少していた傾向を発見しました。このような結果を踏まえ、「非自由主義的逃避(illiberal escapism)」という概念を用いて、ジャカルタにおけるゲーテッド・コミュニティの住民が、ゲートで自らの居住空間を封鎖し都市の不安や公共空間から社会的に距離を置いている一方で、非自由主義的な影響に反対する政治的選択をする状況を説明しました。
質疑応答の際、キム先生は詳細な意見をくださっただけでなく、彼自身が初めてジャカルタの路地にあるゲートに遭遇し驚きを感じたところから、それを研究対象として探求しはじめたというエピソードも共有していただきました。このやりとりを通じて、私は研究の世界に飛び込んだ最初の動機となった感動を再起しました。また、それを遠く離れた文字の上でしか知らなかった先達と共有でき、大変嬉しく思いました。
今回の学会テーマは「激動する世界の中での東南アジアの力と知恵」(Searching for Southeast Asian Powers and Wisdom in the Turmoil World)でした。これを振り返ると、激動する世界の中で、私のような研究者、あるいは東南アジア研究自体が生きていくために必要なものは、この学会が提供してくれたような──訓練を受けた地域やフィールドとして探求する地域で括られがちなパースペクティブの枠を越える──空間に遭遇する力と知恵ではないかとも思いました。次回こそ、ぜひ対面形式での開催が実現することを願っています。

本記事は英語でもお読みいただけます。>>
”Cross-Border Encounters: Reflections on the 2024 Korea-Japan Conference
of Southeast Asian Studies” by Genta Kuno