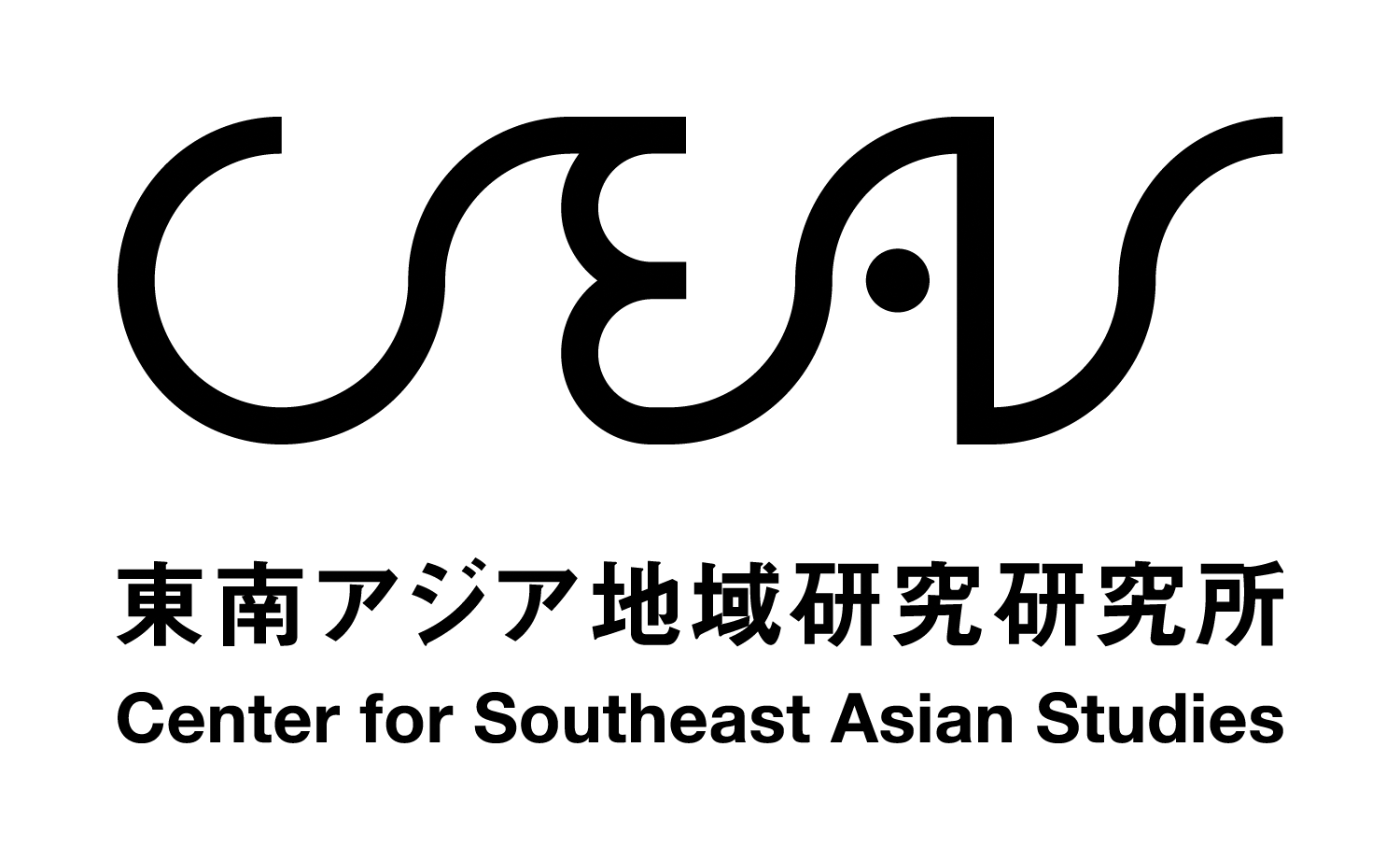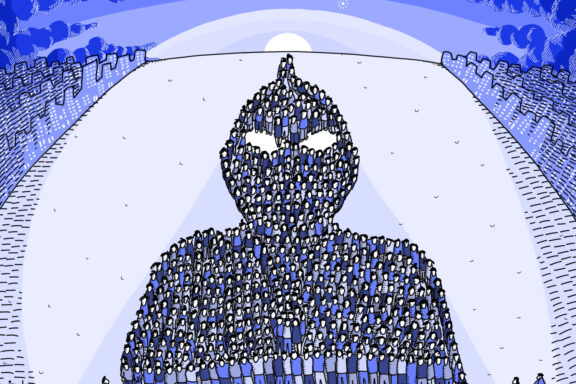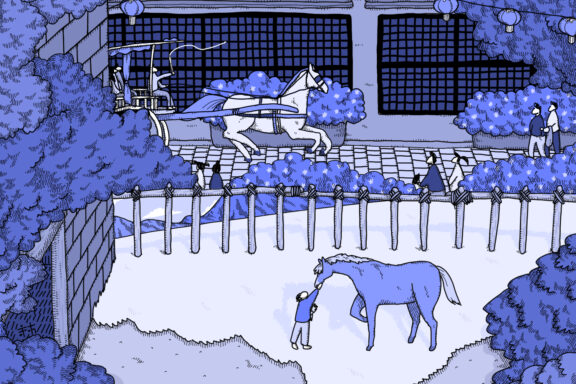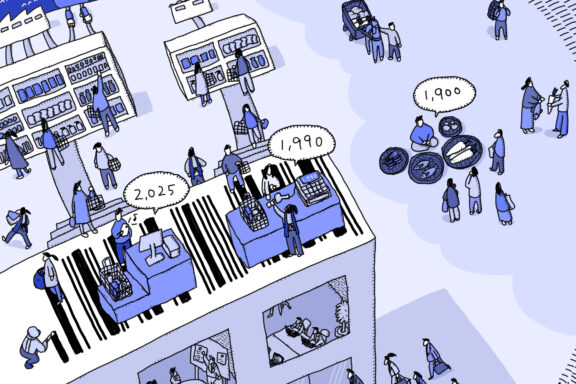帯谷 知可(中央アジア近現代史、中央アジア地域研究)
つい最近、ベラルーシ出身のある女性と同席する機会があった。ウクライナ支援のボランティア活動に携わっているそうだ。それはロシア語を解する日本人が集った場だったのだが、開口一番、彼女は「ロシア語では話したくないんです。でも皆さんとコミュニケーションを取る手段は他にはないから仕方ありません。ロシア語で話しますね」と、完璧な美しいロシア語で言った。
ロシアによるウクライナ侵攻から2年9か月以上が過ぎ、今も戦争は続いている。最初に侵攻の報に接してから、石を飲み込んだような心持ちがおさまらない。その理由を自己分析するに、報道されるウクライナでのロシア軍の信じ難い蛮行やさまざまな統制の強まるロシアの国内情勢もさることながら、エスニックな境界の曖昧な、広域に及ぶロシア語話者の世界(それは間違いなくかつてのロシア帝国とソ連による統治の産物なのだが)に、もはや元に戻すことのできない亀裂と分断が生じており、そのことを受け止めるのが苦しいからではないかと思い至った。ロシア語を学んだことを入口に中央アジア研究に携わるようになった私も、そうしたロシア語話者の世界の片隅でロシア語の恩恵に与ってきた。研究対象地域である旧ソ連中央アジアのウズベキスタンで、私が姉のように慕う親友はウクライナ生まれでベラルーシ人の血も混じったロシア語話者だが、思い返してみても彼女が「何人」なのか、お互いの間でこれまで突き詰めたことはないし、それでよかった。別の友人はウクライナ人とアルメニア人のハーフだというが、ロシア語で生活し、ロシア人だと自認している。こうした例は実に多様で、枚挙にいとまがないのだけれど、戦争がもたらした亀裂に落ち込めば、否応なくウクライナか、ロシアか、という二者択一を迫られることになる。
この間、ウクライナに関する書物がいくつも刊行されてきたが、私にとってとりわけずっしりと重い印象を残したのは、『現代思想』の2022年6月臨時増刊号「総特集 ウクライナから問う―歴史・政治・文化」である。何しろまるごと1冊の総特集であり、ウクライナから発せられた「声」の翻訳2本、日本を代表するソ連・ロシア研究者である塩川伸明と池田嘉郎による「討議」(対談)、38本もの論考、加えて「アンソロジー」として訳者解題付きの「ウクライナ人の世界を知るための四文献」が収められている。
38本の論考の執筆陣には、多様な分野のウクライナとロシアの専門家だけでなく、中東欧研究、モンゴル史・モンゴル研究、中東研究、ヨーロッパ研究、日本研究、国際政治学、ジェンダー・フェミニズム研究等の研究者、ジャーナリスト、そして日本人だけでなくロシア、ベラルーシ、フランスの論客も含まれる。
地域から世界を考え、世界から地域を考えるのが地域研究だとすれば、この1冊は総体としてとても「地域研究的」である。それと同時に、ウクライナ戦争を語る人文学の底力—それは執筆者たちの決意や使命感のようなものかもしれない―が痛切に伝わってくるように感じる。例えば、ロシア文学者の中村唯史はそれを「たとえどんなに些細であろうとも、普遍や正義を装いながら暴力的に分断と抑圧を強いてくる二項対立の図式への抵抗、異議申し立て」(66頁)と表現している。
そして、戦火や抑圧のなかにいる人々のことを思えば、宝箱のようなこうした書物をたやすく手にすることができる環境にたまたまいることの幸運を私たちは噛みしめねばならないと思うのである。
(イラスト:Atelier Epocha(アトリエ エポカ))
本記事は英語でもお読みいただけます。>>
“The Power of the Humanities in Addressing the Ukraine War”
by Chika Obiya